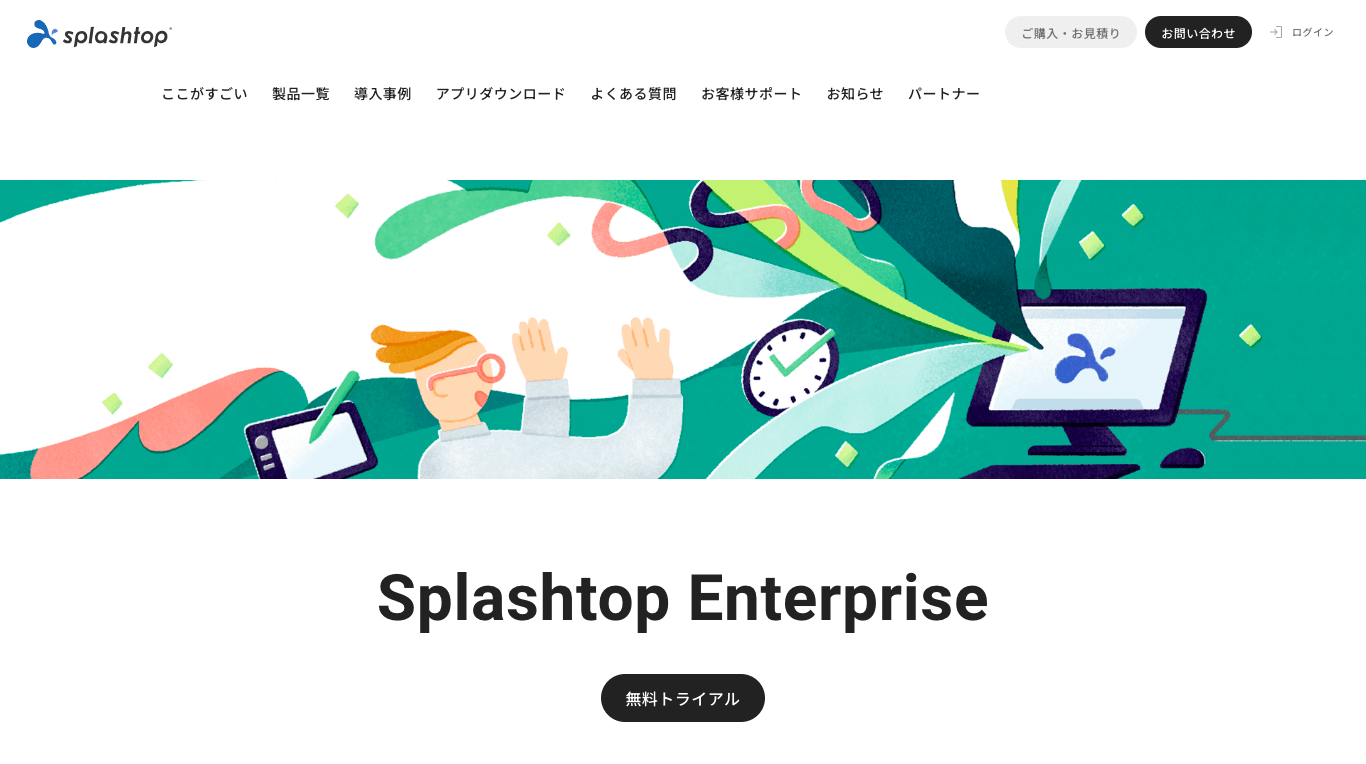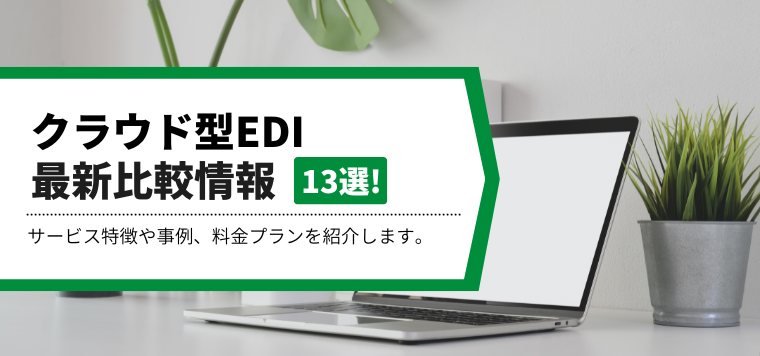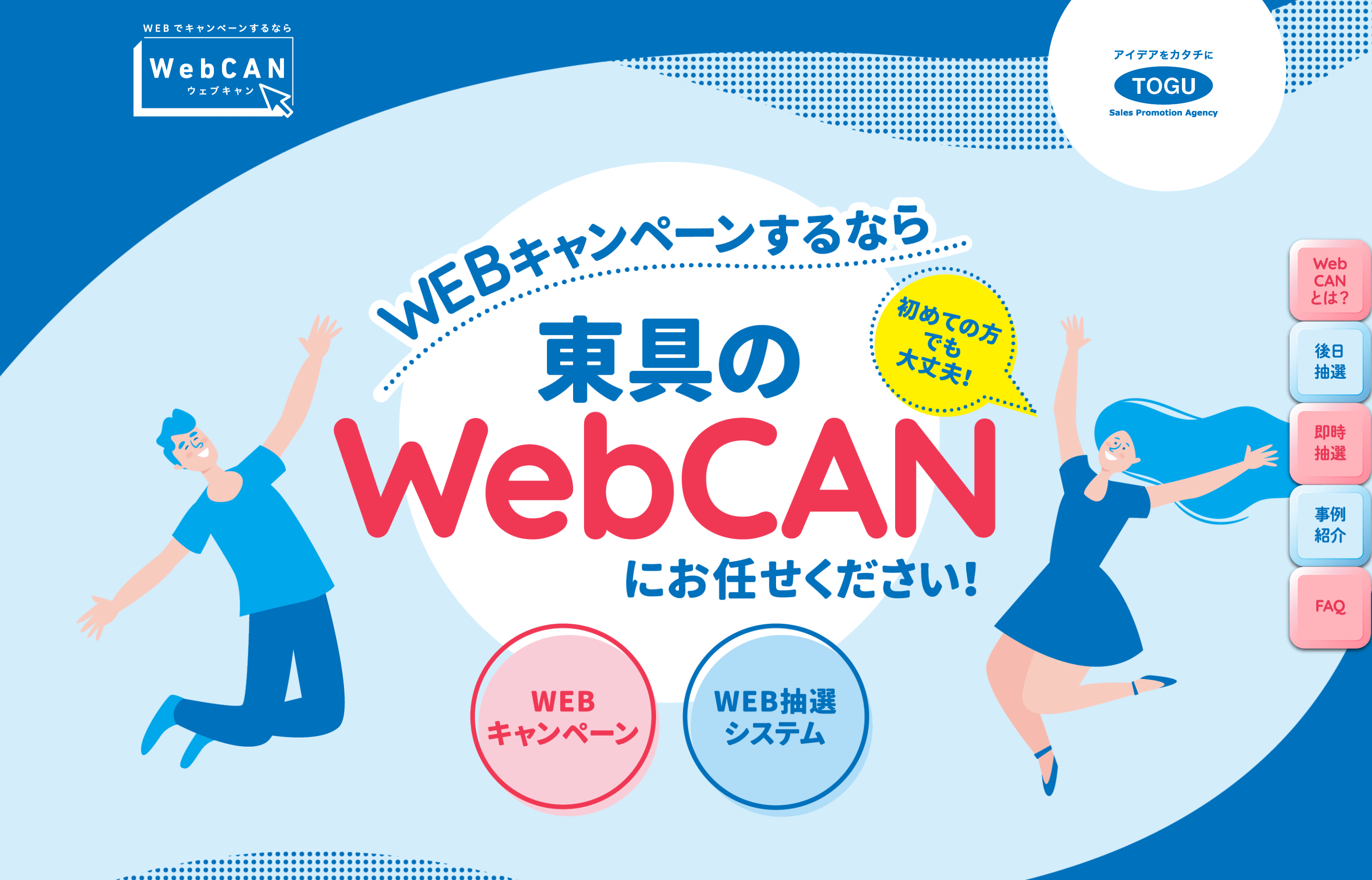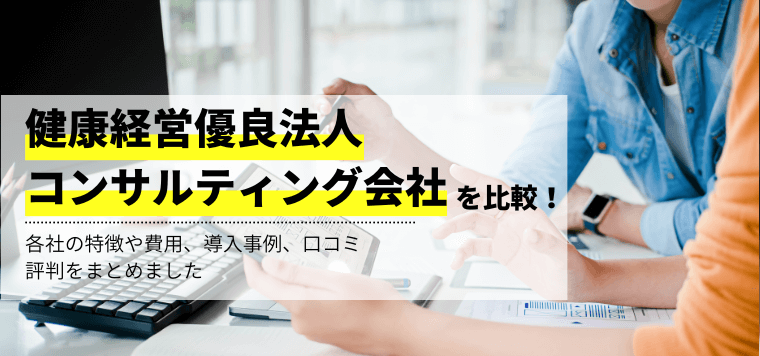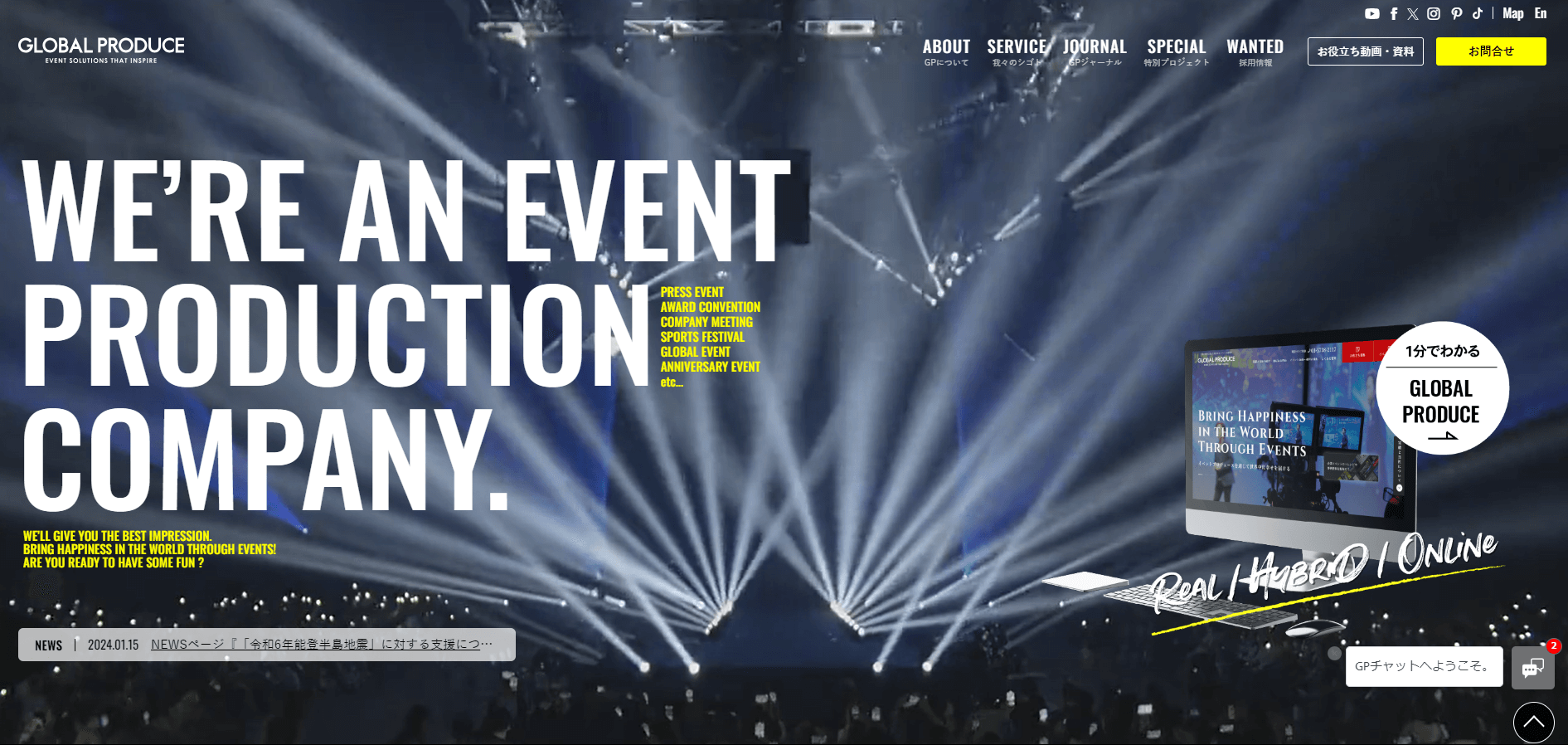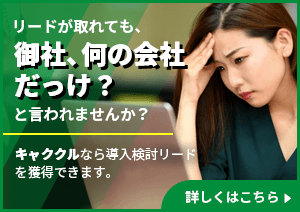第三者保守サービス会社を比較!導入事例や口コミ評判、価格を徹底調査
最終更新日:2024年07月26日
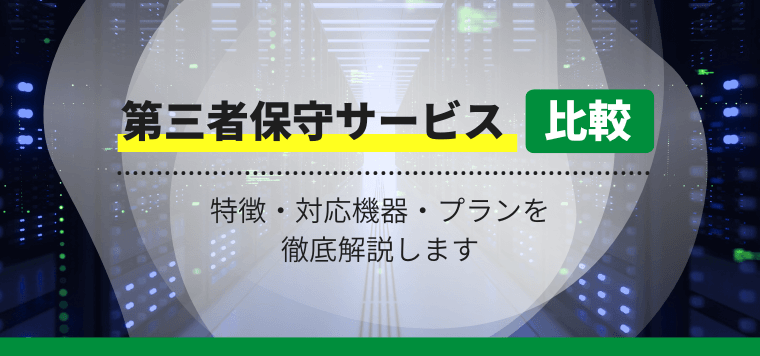
第三者保守サービスは、サポート期間が終了した機器に対して、第三者の企業が提供するサポートサービスです。安心して機器を使用継続するための保守サービスが受けられるほか、「保守コスト削減」「窓口集約」「IT機器のライフサイクルの最適化」といったメリットがあります。
この記事では、おすすめの第三者保守サービスの特徴や事例などをまとめました。ぜひご活用ください。
第三者保守サービス提供会社22選
ここでは、第三者保守サービスを提供している会社を22社紹介します。自社に合う会社選びの参考にしてください。
画像をクリックすると、資料ダウンロードページに移動します。
| 会社名 | 対応機器メーカー |
|---|---|
 【PR】ブレイヴコンピュータ 【PR】ブレイヴコンピュータ |
国内外の主要メーカーを中心に400社以上対応・40,000台以上の実績 オラクル(旧サンマイクロ)/日立/富士通/NEC/HP/Cisco/DELL/東芝など 資料ダウンロードはこちら >> |
| カーバチュア | DELL EMC / HPE / IBM /日立/ SUNマイクロ/ BROCADE / Lenovo など |
| ゲットイット | ARISTA/AVAYA/BROCADE/CISCO/DELL EMC/ETERNUS/Fortinet/富士通/F5 BIG-IP/Hitachi(日立)/HP など |
| データライブ | HPE/DELL EMC/Cisco/NEC/Sun (Oracle)/F5 big-ip/富士通/日立/IBM/NetApp/Juniper/Brocade など |
| Evernex | 記載なし |
| リミニストリート | 記載なし |
| SAT(エスエーティ) | ORACLE(Sun)/HPE/DELL/IBM/Lenovo/富士通/日立/NEC/EMC/NetApp/CISCO/Brocade/F5/Juniperなど |
| インフォメーション・システム・サービス | IBM/HPE/Cisco/SUNマイクロ/Dell /EMC/Lenovo/BROCADE/NetApp/f5/Juniper |
| アプライド・テクノロジー | Cisco/DELL/HP/Data Domain/NEC/IBM/Oracle・Sun/NetApp/Juniper/富士通 |
| シェアード・ソリューション・サービス | DEC/Compaq/HPE/SUNマイクロ/IBM/DELL/DEC/Ciscoのネットワーク製品/NEC/富士通など |
| ネットワンネクスト | Cisco/Juniper/BROCADE/Extreme/Accton/ADVA/APRESIA/Arista/ARRIS/Big Switch Networks/Citrix Systemsなど |
| アイエスエフネット | 記載なし |
| JBサービス | Lenovo/JBAT(旧APTi)/Canon/YAMAHA |
| KSG(国産産業技術) | SUNマイクロ/富士通/oracle/HPE/DELL EMC/DELL/IBM/Cisco/ヤマハ/f5/Juniper/Extremenetworks/BROCADE/NETSCREEN競合他社のサービス特徴 |
| アクシスコンピューテック | 記載なし |
| ネットブレインズ | 記載なし |
| ビジネスコネクト | 記載なし |
| アルファテック・ソリューションズ | IBM(LENOVO)/DELL/EMC/Cisco/FUJITSU/NEC/Oracle (SUN)/HITACHI/NetApp/Juniper/F5/Brocade など |
| インフィニティコミュニケーションズ | サン・マイクロシステムズ(現日本オラクル社)/ヒューレット・パッカード/DELL/富士通/日立など |
| システック井上 | Alpha/VAX/HP/Sun/DEC/Compaqなど |
| TID(ティアイディ) | 旧サンマイクロシステムズ |
| フィールドワン | DEC/SUNマイクロ/HP/Ciscoなど |
【PR】国内外の主要メーカーを中心に400社以上対応・40,000台以上の実績
ブレイヴコンピュータ株式会社(つなぎ保守)

ブレイヴコンピュータ株式会社の第三者保守「つなぎ保守」の特徴
自社運営のコンタクトセンターでエンジニアが対応するマルチベンダー
ブレイヴコンピュータ株式会社は、「つなぎ保守」という第三者保守サービスを提供しています。国内外の主要メーカーに対応するマルチベンダーです。サーバー保守はもちろん、サーバー以外にもストレージ、ネットワーク機器、テープ装置類も対応しています。 24時間365日、障害の受付をしているので、保守窓口の一本化が可能です。また、自社運用のコール・コンタクトセンターには自社カスタマーエンジニアが常駐。経験豊富な専門家にいつでも直接相談できる第三者保守サービスです。
オンサイト保守に対応している
ブレイヴコンピュータ株式会社オンサイトの第三者保守にも対応しています。障害発生機器のログを送信後、自社カスタマーエンジニアが解析して、オンサイト保守実施の必要性があれば、各拠点からオンサイト保守が出動。障害機器の交換・正常稼働を確認して、最終的に使用した保守部材の補充まで実施します。現場で機器を直接見てもらえるので、障害の解消もスピーディです。
お客様ごとに保守用パーツをストック
保守用パーツは国内外の市場から調達して自社内で検品しています。エージングを実施後にお客様専用パーツとして各保守拠点において管理しています。お客様ごとに保守用リペア・パーツがストックされる管理体制が整っている第三者保守サービスです。
ブレイヴコンピュータ
「つなぎ保守」に関する
サービス詳細資料はコチラ
動画でわかる第三者保守サービス「つなぎ保守」
ブレイヴコンピュータ株式会社の第三者保守「つなぎ保守」が選ばれるポイント
【ポイント①】豊富な実績がある
ブレイヴコンピュータ株式会社の提供する第三者保守サービス「つなぎ保守」は、 600社以上の企業の保守を引き受けた実績があります。機器台数にして、40,000台超の契約実績です。様々なメーカーや障害への対応経験を活かして、最適な保守を提供してもらえます。
【ポイント②】自社エンジニアが24時間365日対応
障害受付のフリーダイヤルは、24時間365日稼働です。保守対応の知識と実績がある自社のカスタマーエンジニアが対応してくれるのが安心ポイント。自社カスタマーエンジニアと直接会話ができます。
【ポイント③】国内外の主要メーカー機器に対応可能
ブレイヴコンピュータ株式会社の第三者保守サービスは国内外の主要メーカーの機器に対応するマルチベンダーサービスです。保守を一本化できます。お客様ごとに保守用のパーツをストック。迅速な対応が可能です。ストレージ機器やネットワーク機器の保守にも対応しています。
ブレイヴコンピュータ
「つなぎ保守」に関する
サービス詳細資料はコチラ
ブレイヴコンピュータ株式会社「つなぎ保守」の事例
病院におけるコンパクトサーバー保守
メーカーの発売時期から9年経過して保守終了から2年近く経過している病院に導入されていたコンパクトサーバー。現役で活躍していたため、まだ数年は稼働させたいという希望で、「つなぎ保守」を導入しました。第三者保守ベンダーの選定で重視したのは、保守料金の妥当性と障害発生時の対応。 24時間365日の電話対応を提供している「つなぎ保守」を選んだとのことです。
参照元:ブレイヴコンピュータ株式会社公式サイトhttps://www.brave-com.jp/case/
物流の基幹サーバー保守
新型コロナウイルスのパンデミックが起きた2020年、使用中のサーバーが保守切れになり、対応を検討する必要に迫られました。サーバーリプレース、データベース、その他アプリケーションの改修費用の見積もりは高額。先行きが見えない経済状況の中で、大きな金額の支出の決断が出来ず、コストを抑えるために第三者保守サービスを選択することになりました。障害発生時の対応に安心感が得られたこと、近くに保守拠点があることで「つなぎ保守」を選択。物流の基幹サーバーのため、長時間のダウンタイムが発生して物流業務が止まると大きな痛手になります。障害発生時は迅速な復旧が必要なため対応スピードは大きな決め手になったそうです。
参照元:ブレイヴコンピュータ株式会社公式サイトhttps://www.brave-com.jp/case/
病院のサーバーをまとめて保守
更新時期の異なる十数台のサーバーをまとめて保守した事例もあります。サーバーの導入時期がバラバラになっており管理が大変なため、ライフサイクルを合わせたいという希望。ハードウェア保守だけが終了してしまうシステムを延命するために第三者保守を検討したとのことです。保守実績、カスタマーエンジニアの知見、見積価格、保守拠点を総合的に判断して、「つなぎ保守」を契約。ハードディスク障害の対応はメーカー保守と遜色ないとの評価を受け、大規模システム更新延長にあわせて保守契約も延長されました。
参照元:ブレイヴコンピュータ株式会社公式サイトhttps://www.brave-com.jp/case/
ブレイヴコンピュータ
「つなぎ保守」に関する
サービス詳細資料はコチラ
ブレイヴコンピュータ株式会社「つなぎ保守」の対応メーカー・機種
- オラクル(旧サンマイクロ)
- 日立
- 富士通
- NEC
- HP
- Cisco
- IBM
- DELL
- EMC
- APC
- 東芝
- Juniper
- アライドテレシス
- Brocade
- f5
- Alteon
- ATEN
- ADIC
- NetApp
- Nokia
- ストラタス
- Extreme
※MPSP(マルチプラットホーム・保守サービス・プログラム)適用により国内外の主要メーカー、主要機種に対応可能
ブレイヴコンピュータ株式会社の第三者保守サービス・プラン
- Plan1:リードタイム5時間目標でオンサイト
- Plan2:土日祝日を含む翌日9時~17時でオンサイト
- Plan3:土日祝日を含まない翌営業日平日9:00~17:00でオンサイト
- Premium:リードタイム2時間目標でオンサイト
※Plan1は、対象エリア:関東、関西、東海、九州北部、東北南部、道内道央
※Premiumは、対象エリア・時間:東京23区、平日8時~20時、対象機種:富士通 PRIMERGY/ETERNUS
※価格は要見積もり
企業概要
| 会社名 | ブレイヴコンピュータ株式会社 |
|---|---|
| 会社所在地 | 東京都千代田区岩本町3-9-2 PMO岩本町5階 |
| 公式HP | https://www.brave-com.jp/solution/tsunagi/ |
ブレイヴコンピュータ
「つなぎ保守」に関する
サービス詳細資料はコチラ
まだある!第三者保守サービス会社カタログ
パークプレイステクノロジーズ(旧カーバチュア)

パークプレイステクノロジーズの特徴
パークプレイステクノロジーズは世界各地に常駐しているエンジニアが、24時間365日対応できる第三者保守サービスを提供しています。サービスセンターと部品拠点があり、高度なハードウェア交換を提供。グローバルな技術をサポートしています。日本は一カ所拠点があるようですが詳しい情報は公式サイトに記載がありませんでした。お客様からの連絡後、必要と判断した場合は、4時間以内にフィールド エンジニアがオンサイト対応します。
パークプレイステクノロジーズの対応機種
DELL EMC/HPE/IBM/Cisco/Juniper/日立/NetApp/Lenovo/SUNマイクロ/BROCADE/Quantum/Intel
パークプレイステクノロジーズのプラン
ありませんでした
パークプレイステクノロジーズの会社概要
| 会社名 | パークプレイステクノロジーズ |
|---|---|
| 会社所在地 | 日本拠点の住所記載なし |
| 公式HP | https://www.parkplacetechnologies.com/third-party-maintenance/network-maintenance/ |
ゲットイット

ゲットイットの特徴
株式会社ゲットイットは、オンサイト保守と預託保守、スポット保守に対応している第三者保守サービスを提供しています。障害の状況によって必要と判断した際に、フィールドエンジニアが設置場所に駆け付けてパーツの交換や修理を行うオンサイト保守プランが用意されています。また、「保守が切れていた」「サーバーが壊れてしまった」といった一時的な問題にスポット対応が可能。希少機器にも対応している第三者保守サービスです。
ゲットイットの対応機種
ARISTA/AVAYA/BROCADE/CISCO/DELL EMC/ETERNUS/Fortinet/富士通/F5 BIG-IP/Hitachi(日立)/HP/IBM/JUNIPER/NEC/NETAPP/SANRISE/SANRISE/Sun (Oracle)/Supermicro(スーパーマイクロ)/東芝 MAGNIA
ゲットイットのプラン
- オンサイト保守
- 預託保守
- スポット保守
- パーツデリバリー
ゲットイットの会社概要
| 会社名 | 株式会社ゲットイット |
|---|---|
| 会社所在地 | 東京都中央区築地3-7-10 JS築地ビル4F |
| 公式HP | https://www.get-it.ne.jp/index.php/eosl |
データライブ

データライブの特徴
データライブ株式会社の第三者保守サービスは、全国1600社85000台の実績を誇っています。ITハードウェアのサードパーティー長期保守サービスを提供。今後EOSLを迎える機器も含めて、10万台規模の長期保守に備えて備蓄を進め、長期保守期間中の保守パーツ枯渇リスクの軽減に取り組んでいます。機器メーカー、導入ベンダーを問わない単一のコール窓口を用意。問い合わせを一本化できます。
データライブの対応機種
HPE/DELL EMC/Cisco/NEC/Sun (Oracle)/F5 big-ip/富士通/日立/IBM/NetApp/Juniper/Brocade
データライブのプラン
ありませんでした
データライブの会社概要
| 会社名 | データライブ株式会社 |
|---|---|
| 会社所在地 | 東京都文京区本郷2-38-4 本郷弓町ビル |
| 公式HP | https://www.datalive.co.jp/ |
Evernex

Evernexの特徴
エジプト、ケニア、モロッコ、ナイジェリア、南アフリカなどに拠点があり、世界中の 45 か所のオフィスから 165 以上の国で事業を展開しているグローバルな会社です。日本での活動実績は記載がありませんでした。グリーンITを推進して、単一の窓口を通じて、費用対効果の高いグローバルなエンドツーエンドの資産ライフサイクル管理の一環として第三者保守サービスを提供しています。
Evernexの対応機種
ありませんでした
Evernexのプラン
ありませんでした
Evernexの会社概要
| 会社名 | Evernex |
|---|---|
| 会社所在地 | 記載なし |
| 公式HP | https://www.evernex.com/ |
リミニストリート

リミニストリートの特徴
2005年に設立され、世界29拠点がある会社です。NTTや京セラ、西松建設など日本の有名企業との取引実績があります。第三者保守サービスとして、ソフトウェア向けの包括的な保守サービスを提供しています。問題の解決、セキュリティの強化、技術スタックの他の要素とのアプリケーションの連携、パフォーマンスチューニング、法規制コンプライアンスに対して、平均20年の経験を持つサポートエンジニアが対応しています。24時間年中無休の第三者保守サポートにも対応可能です。
リミニストリートの対応機種
ありませんでした
リミニストリートのプラン
ありませんでした
リミニストリートの会社概要
| 会社名 | Rimini Street, Inc. |
|---|---|
| 会社所在地 | 公式サイトに記載なし |
| 公式HP | https://www.riministreet.com/jp/resources/ebook/seven-reasons-why-it-teams-love-third-party-support/ |
SAT(エスエーティ)

SAT(エスエーティ)の特徴
SAT(エスエーティ)の第三者保守サービスは、45社以上のメーカーの1585機種(2022年2月現在)に対応しています。各ITメーカーで保守を経験したエンジニアが在籍し、年間1700件を超える障害解析実績があるため、パーツに至るまで被疑箇所の特定ができる知見があります。24時間365日、障害コール対応や部材のデリバリー、オンサイト対応を実施。駆け付けまで4時間を目標とするプランもあります。
SAT(エスエーティ)の対応機種
ORACLE(Sun)/HPE/DELL/IBM/Lenovo/富士通/日立/NEC/EMC/NetApp/CISCO/Brocade/F5/Juniper/アラクサラネットワークス/Supermicro/Extream/ヤマハ
SAT(エスエーティ)のプラン
- Plan1:SAT営業日受付→翌SAT営業日対応
- Plan2:SAT営業日受付→翌日対応
- Plan3:SAT営業日受付20時まで→翌日対応
- Plan4:24時間×365日受付→翌日対応
- Plan5:24時間×365日受付→切り分け後駆け付け4時間目標
SAT(エスエーティ)の会社概要
| 会社名 | 株式会社エスエーティ |
|---|---|
| 会社所在地 | 東京都府中市府中町二丁目10-10 多磨ビル |
| 公式HP | https://sat-corp.jp/maintenance/s4p/ |
インフォメーション・システム・サービス

インフォメーション・システム・サービスの特徴
インフォメーション・システム・サービスの第三者保守サービスでは、IBM社メインフレーム装置の保守運用の経験がある元IBM技術員が保守を担当しています。社内技術教育も常時実施して、品質の高い保守サービスを提供しています。クライアントの約30%が金融系企業です。24時間365日対応可能。技術員が現場に待機して障害に対処するスタンバイサービスや現場に訪問して保守作業を提供するオンサイト保守、修理期間は代替機で対応する代替保守など、様々な第三者保守サービスに対応しています。
インフォメーション・システム・サービスの対応機種
IBM/HPE/Cisco/SUNマイクロ/Dell /EMC/Lenovo/BROCADE/NetApp/f5/Juniper
インフォメーション・システム・サービスのプラン
ありませんでした
インフォメーション・システム・サービスの会社概要
| 会社名 | インフォメーション・システム・サービス株式会社 |
|---|---|
| 会社所在地 | 東京都北区赤羽2-51-3 NS3ビル |
| 公式HP | https://www.isskk.com/hoshu.html |
アプライド・テクノロジー

アプライド・テクノロジーの特徴
アプライド・テクノロジーは、厳しい品質チェックをクリアした中古の保守部材を使用する第三者保守サービスを提供しています。自主レンタルアップ品を活用することで、保守運用コストを大幅にカット可能です。日本はもちろん、世界中の提携パートナー企業から保守部材を仕入れ、安定的なシステム延命を実現します。専任の営業スタッフと保守経験豊かな技術スタッフがサポート。24時間365日、全国で対応している第三者保守サービスです。
アプライド・テクノロジーの対応機種
Cisco/DELL/HP/Data Domain/NEC/IBM/Oracle・Sun/NetApp/Juniper/富士通
アプライド・テクノロジーのプラン
- オンサイト保守
- センドバック保守
- スポット保守
アプライド・テクノロジーの会社概要
| 会社名 | アプライドテクノロジー株式会社 |
|---|---|
| 会社所在地 | 東京都新宿区下宮比町 2-26KDX飯田橋ビル 3F |
| 公式HP | https://www.atc.co.jp/maintenance/ |
シェアード・ソリューション・サービス
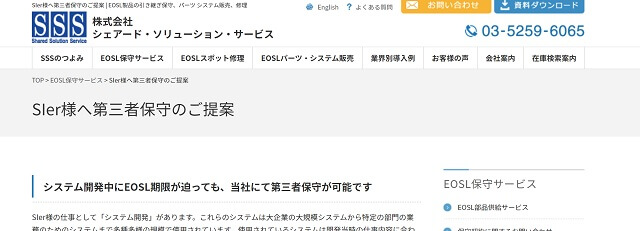
シェアード・ソリューション・サービスの特徴
株式会社シェアード・ソリューション・サービスには、DEC、COMPAQ、hpで保守サービスを行ってきた経験豊富なエンジニアが在籍。コンピューター保守に関連する認定資格を保有しているエンジニアが障害などに対応。メーカーの保守サービスが終了したシステムの保守を高い品質で引き継ぐ第三者保守サービスを提供しています。コンピューター機器の中古機やパーツなどの保守部品を国内外の提携先企業から直接取り寄せているため、入手困難なパーツでも調達可能です。国内外のメーカーの機器の保守に対応できます。
シェアード・ソリューション・サービスの対応機種
DEC/Compaq/HPE/SUNマイクロ/IBM/DELL/DEC/Ciscoのネットワーク製品/NEC/富士通など
シェアード・ソリューション・サービスのプラン
ありませんでした
シェアード・ソリューション・サービスの会社概要
| 会社名 | 株式会社シェアード・ソリューション・サービス |
|---|---|
| 会社所在地 | 東京都千代田区内神田1-11-10 コハラビル2F |
| 公式HP | https://www.3scom.jp/years/proposal.html |
ネットワンネクスト

ネットワンネクストの特徴
ネットワンネクスト株式会社は、全国約56カ所の物流拠点に、約7300種類、80000点を超える保守部材を配備しています。2時間以内に配送できる体制を構築しており、オペレーションセンターは、24時間365日体制。およそ90名のオペレーター、150名の後方支援部隊という組織で第三者保守サービスを提供しています。サービス拠点は全国約80カ所。全国で迅速に対応可能です。EOL機器のリプレイス計画を柔軟にして設備投資の悩みを解決するためにサポートしています。
ネットワンネクストの対応機種
Cisco/Juniper/BROCADE/Extreme/Accton/ADVA/APRESIA/Arista/ARRIS/Big Switch Networks/Citrix Systems/Force10/ForeScout/FXCなど
ネットワンネクストのプラン
ありませんでした
ネットワンネクストの会社概要
| 会社名 | ネットワンネクスト株式会社 |
|---|---|
| 会社所在地 | 東京都千代田区丸の内2-7-2JPタワー |
| 公式HP | https://www.netone-next.co.jp/service/maintenance/ |
アイエスエフネット

アイエスエフネットの特徴
株式会社アイエスエフネットは日本全国に16拠点をもち、約1,500名の正社員エンジニアと共に24時間365日、マルチリンガルでサービスを展開するITインフラ企業です。第三者保守サービスは明記されていませんでしたが、お客さまの技術部門へ人材サービスも提供しているため、保守に関するサービスも提供している可能性があります。全国展開で24時間365日の対応。マルチリンガル対応が可能です。
アイエスエフネットの対応機種
ありませんでした
アイエスエフネットのプラン
ありませんでした
アイエスエフネットの会社概要
| 会社名 | 株式会社アイエスエフネット |
|---|---|
| 会社所在地 | 東京都港区赤坂7-1-16 オーク赤坂ビル 3階 |
| 公式HP | https://www.isfnet.co.jp/operation/eosl.html |
JBサービス

JBサービスの特徴
全国43カ所にサービス拠点があり、技術員・コンタクトセンターが連携してハードウェア障害時の部品交換や復旧作業を提供します。保守・サービス専門部門として50年以上活動した経験と実績を活かして、高品質な第三者保守サービスを提供。国内外の主要メーカーに対応しており、保守窓口の一元化が可能です。IT機器以外にもデジタルサイネージやロボットなどの保守にも対応しています。
JBサービスの対応機種
Lenovo/JBAT(旧APTi)/Canon/YAMAHA
JBサービスのプラン
ありませんでした
JBサービスの会社概要
| 会社名 | JBサービス株式会社 |
|---|---|
| 会社所在地 | 東京都中央区八重洲二丁目2番1号 東京ミッドタウン八重洲 八重洲セントラルタワー13階 |
| 公式HP | https://www.jbsvc.co.jp/products/it/maintenance/eosl/eosl.html |
KSG(国産産業技術)

KSG(国産産業技術)の特徴
KSG 株式会社は、ソリューション提案からITインフラの構築・保守までトータルサービスを提供している新しい形のICT商社です。1986年に設立以来、ICTシステムインフラ構築など様々な経験を培ってきました。そうした経験を活かして第三者保守サービスも提供しています。障害発生時は、迅速にタイプ。他社で購入した機器でも保守サービスに加入できます。ISO9001、ISO27001も取得して、高品質な管理体制を構築している会社です。
KSG(国産産業技術)の対応機種
SUNマイクロ/富士通/oracle/HPE/DELL EMC/DELL/IBM/Cisco/ヤマハ/f5/Juniper/Extremenetworks/BROCADE/NETSCREEN
KSG(国産産業技術)のプラン
ありませんでした
KSG(国産産業技術)の会社概要
| 会社名 | KSG 株式会社 |
|---|---|
| 会社所在地 | 東京都千代田区神田錦町1-1 神田橋安田ビル1階 |
| 公式HP | https://www.ksgnet.com/advantage/hoshu.html |
アクシスコンピューテック

アクシスコンピューテックの特徴
コンピュータ関連機器販売、買取、レンタル、機器増設、撤去、コンピュータコンサルティングなどを提供している会社です。これらの事業で培った経験と技術を活かして、コンピュータ機器のメンテナンスに対応しています。機器故障時に現地での部品交換・修理に対応可能です。また、指定ヤードへ不具合機器を引き取りし、修理して返送する方法も用意しています。
アクシスコンピューテックの対応機種
ありませんでした
アクシスコンピューテックのプラン
ありませんでした
アクシスコンピューテックの会社概要
| 会社名 | 株式会社アクシスコンピューテック |
|---|---|
| 会社所在地 | 千葉県市川市相之川4-15-3友泉南行徳ビル502 |
| 公式HP | https://www.axis-comtech.com/ |
ネットブレインズ

ネットブレインズの特徴
保守サービスだけではなく、ITシステム管理・運用のすべてを任せられます。必要なサービスをヒアリングからオーダーメイドで設計。必要なサポートだけを選択でき、無駄がありません。1ヶ月無料トライアルを用意。実際にサービスを体験してみて、必要なサービスと不要なサービスの見極めを行う期間です。契約後に思った内容と違ったというトラブルを防ぐことにもつながります。専任のSEさらにスペシャリストが障害に迅速に対応。損失を最小限に抑えるサービスです。
ネットブレインズの対応機種
ありませんでした
ネットブレインズのプラン
ありませんでした
ネットブレインズの会社概要
| 会社名 | 株式会社ネットブレインズ |
|---|---|
| 会社所在地 | 東京都中央区明石町6-22 築地ニッコンビル 4階 |
| 公式HP | https://www.netbrains.co.jp/nbcss/index_c.html |
ビジネスコネクト

ビジネスコネクトの特徴
年間保守サービスでは、電話でのサポートはもちろん、エンジニアが直接機器のある場所まで訪問して修理の実施が可能です。契約時にお客様用の部品を用意しているため、迅速な対応ができます。また、年間保守以外でも、オンサイト修理や故障した機器を送って修理する2種類のサポートも用意。定期点検サービスも提供しています。ただし、2023年2月現在、第三者保守サービスの新規受付は休止しているので注意してください。
ビジネスコネクトの対応機種
ありませんでした
ビジネスコネクトのプラン
ありませんでした
ビジネスコネクトの会社概要
| 会社名 | 株式会社ビジネスコネクト |
|---|---|
| 会社所在地 | 東京都千代田区飯田橋2-5-2 エマタナカビル6F |
| 公式HP | http://businessconnect.co.jp/ |
アルファテック・ソリューションズ

アルファテック・ソリューションズの特徴
ITインフラ及び情報系アプリケーションシステムの企画・設計、開発・構築、導入・展開、保守・運用などを手掛けている1971年に設立された会社です。東京本社の他、新大阪オフィス、淀屋橋オフィス、長野オフィス、戸田センタ、曳舟センタの6拠点で活動しています。ITインフラに携わってきた経験を活かして、第三者保守サービスも提供。国内外のメーカーのEOSL製品の保守にタイプして、安定稼働できるシステムの保守延長を実現しています。
アルファテック・ソリューションズの対応機種
IBM(LENOVO)/DELL/EMC/Cisco/FUJITSU/NEC/Oracle (SUN)/HITACHI/NetApp/Juniper/F5/Brocade/Overland Storage/Quantum(クアンタム) /Tandberg Data(タンベルグ データ) / Extreme Networks
アルファテック・ソリューションズのプラン
ありませんでした
アルファテック・ソリューションズの会社概要
| 会社名 | アルファテック・ソリューションズ株式会社 |
|---|---|
| 会社所在地 | 東京都港区虎ノ門4丁目1番1号 |
| 公式HP | https://www.alphatec-sol.co.jp/ |
インフィニティコミュニケーションズ

インフィニティコミュニケーションズの特徴
大手外資系ICTメーカー出身の熟練した技術者が在籍。機器の障害復旧をサポートします。自社内で保守サービスのトレーニングを受講したり、新たな人員を配置したりする必要はありません。また、メーカー保守サービスより安価な料金を提案。年間契約ですので、障害対応の回数にも制限がありません。土日祝日も対応するプランや即日対応するプランなど、スピード対応が可能なプランが用意されています。
インフィニティコミュニケーションズの対応機種
サン・マイクロシステムズ(現日本オラクル社)/ヒューレット・パッカード/DELL/富士通/日立など
インフィニティコミュニケーションズのプラン
ありませんでした
インフィニティコミュニケーションズの会社概要
| 会社名 | インフィニティコミュニケーション株式会社 |
|---|---|
| 会社所在地 | 東京都千代田区 神田司町2-6 神田平沼ビル7F |
| 公式HP | https://www.infinity-c.co.jp/service/icsmart.html |
システック井上

システック井上の特徴
パートナー企業との技術提携により、迅速かつ徹底した予防保守を実施しています。パートナー企業が提携している米国企業より、直接EOSとなったパーツや製品を輸入し、動作検証を実施した製品を販売。納品後は保守サポートで安心して使い続けられる体制を整えています。オンサイト保守では、要望に合わせて24時間365日対応も含めて提案可能です。
システック井上の対応機種
Alpha/VAX/HP/Sun/DEC/Compaqなど
システック井上のプラン
ありませんでした
システック井上の会社概要
| 会社名 | 株式会社システック井上 |
|---|---|
| 会社所在地 | 長崎県長崎市稲佐町3番3号 |
| 公式HP | https://www.sys-inoue.co.jp/common/com8 |
TID(ティアイディ)

TID(ティアイディ)の特徴
既にEOSLとなってしまった旧サンマイクロシステムズ社製のシステムに対して、当社独自の保守サービスを提供しています。オンサイト保守では、当日対応や翌日対応、日時指定など、希望に合わせたタイプが可能。機器の設置場所へ伺い、部品単位・製品単位で修理作業を実施します。センドバック修理にも対応。本体先出し発送や不良品到着後発送の製品交換方式の修理、修理品到着後に部品単位で修理して返却する方式でサポートします。英語キーボードから日本語キーボードへ、HDDの大容量化、メモリ容量の増加等のアップグレードにも対応可能です。
TID(ティアイディ)の対応機種
旧サンマイクロシステムズ
TID(ティアイディ)のプラン
ありませんでした
TID(ティアイディ)の会社概要
| 会社名 | 株式会社 ティ・アイ・ディ |
|---|---|
| 会社所在地 | 東京都中央区日本橋大伝馬町12-19 TIDビル |
| 公式HP | https://www.tid.co.jp/ |
フィールドワン

フィールドワンの特徴
コストダウンにつながる延命保守サービスを提案しています。米国のサードパーティ・メンテナンス会社との技術提携により迅速な保守を実施。Alpha/Vaxシステムを始めとするHP社製、Sun Microsystems社のハードウェア/ソフトウェア、HPE社のストレージ(3PAR)に加え、CISCO、Juniper、F5等のネットワーク機器の安定稼動が可能です。電気機器や電気・ガス、化学、ガラス・土石、鉄鋼、機械など、様々な業種の企業で延命保守サービスを提供した実績があります。対応エリアの幅も広く、北は北海道から南は九州鹿児島まで対応可能です。
フィールドワンの対応機種
DEC/SUNマイクロ/HP/Ciscoなど
フィールドワンのプラン
ありませんでした
フィールドワンの会社概要
| 会社名 | 株式会社フィールドワン |
|---|---|
| 会社所在地 | 東京都新宿区原町3-87-4 NTビル1F |
| 公式HP | https://field-one.com/ |
第三者保守とは
第三者保守とは、ハードウェアの保守をメーカー以外の第三者に行ってもらうサービスです。
PC、サーバー、ネットワーク機器などIT機器は、メーカーの保守サポートを受けて管理します。しかし、メーカー保守は期限があるのが一般的です。保守の期限が切れると修理・交換対応が受けられません。
そうなる前に交換できればいいのですが、IT機器のリプレイスは時間とコストがかかります。
メーカーの保守を受けられなくなってしまうと、故障や不具合が発生した場合に業務に支障が生じてしまうリスクがあります。故障してから新しい機器に交換しようとしても、IT機器の手配には時間がかかるのが常です。
では修理をすればいいかというと、修理には時間と高額な費用がかかってしまいます。企業活動において、IT機器の保守は必要不可欠です。
そこでリプレイス以外の選択として検討したいのが、第三者保守です。メーカーの保守が受けられなくなっても、専門の第三者に保守を依頼することで、安定した企業活動ができます。
メーカーの保守が切れた機器を使用できる
第三者保守を利用すれば、メーカーの保守が切れてしまった機器でも継続して利用できます。保守が切れたことを知りつつも、だましだまし利用するのは大きなリスクです。
そのようなリスクを負うことなく、まだ使える機器を使用し続けられます。IT機器は新しい機器の方が利便性は高くなっているものです。しかし、新しい機器に変えると、慣れるまでに時間がかかることもあります。
使いこなせるまで業務に支障が生じる可能性も考慮すると、第三者保守を活用して、使える間は買い替えないのも手です。
機器のリプレイス準備に余裕ができる
保守が切れる時期というのは、故障が発生しやすくなる時期でもあります。新しい機器にリプレイスする時期が到来しているということです。しかし、機器のリプレイスは簡単にできることではありません。
費用の準備はもちろん、入れ替えに合わせて業務を調整する必要もあるでしょう。日常の業務が忙しいと対応の時間が取れません。第三者保守を活用することで、リプレイスのための準備期間を設けられます。
機器を買い替えるタイミングを調整でき、余裕をもったリプレイスの実行が可能です。
コスト削減になる
メーカーによっては、保守の延長ができることがあります。しかし、一般的に、延長保守は割高です。故障時の修理も高額になります。第三者保守であれば、メーカーの延長保守より安く保守してもらえる可能性があります。
EOSLと第三者保守の必要性
EOSLはEnd of Service Lifeを略したもので、「機器の保守サービスが停止する」ことを指します。EOSLと意味が似ている用語としては、EOL(End of Life)やEOS(End of Support)が挙げられます。
EOLは「メーカー販売、生産が終了する」ことを、EOSは「メーカーによる技術サポートが終了する」ことを示しています。
費用・時間の捻出や人的リソース不足が原因でリプレイスが困難であったり、機能的な問題で既存機器の継続利用が求められる場合など、サポート終了や期限切れとなった機器を使用し続けなくてはいけないケースはよくあります。
EOSLやEOL後の機器を、継続的に利用するために必要となるのが「第三者保守」です。
第三者保守サービスの導入メリット
メーカー保守よりコストが安い
第三者保守サービスは、一般的にメーカー保守と比較してサービス費用が安価です。メーカー保守の場合、年間保守費用以外にも、アップグレード、カスタマイズの保守などが上乗せされています。
しかし、第三者保守サービスは、不具合への対応などやるべきことの幅が限定的。ハードウェアの責任がないためアップグレードなどをする必要がなく、その分、費用を安くできます。
また、第三者保守サービスを利用すると、使用機器の稼働期間が延びます。メーカーのサポートが切れる度に新しい機器やシステムを購入すると、初期導入コストがかかります。
メーカーサポートが5年で切れる場合は20年で4回の機器・システム移行が発生しますが、第三者保守サービスを利用して10年以上の長期利用をすれば導入コストを抑えることが可能です。
同じ機器を継続使用できる
使い慣れた機器をそのまま継続利用できるのも第三者保守サービスのメリットのひとつです。正常に稼働している限りその機器を使い続けられます。買い替えの時期でも、第三者保守でつなぎ、移行のタイミングを調整することも可能です。
使い慣れた機器を新しいものに変えると、慣れるまでは業務スピードが遅くなるなどの支障が生じる可能性があります。第三者保守サービスを利用すれば、計画的な買換えが実現可能です。
保守がまとまる
メーカーの保守サービスは自社製品にしか対応していません。企業では、複数の機器・システムを使用しているでしょう。不具合が発生すると、その機器のメーカーに問い合わせる必要があります。問い合わせ先を探す手間もかかります。
第三者保守サービスにすれば、複数の機器・システムのすべてを任せられるため、マルチベンダー対応が可能です。窓口が一本化されるため、問い合わせがスムーズになります。
第三者保守サービスの導入デメリット
最新の状態で使用できない
機器やシステムは、日々新しくなっています。新しいものほど、利便性やクオリティは高まっているものです。
第三者保守サービスを利用して保守が切れた機器を使用し続けると、新しい機器の利便性やクオリティを活用できません。リプレイスしないことで気づかないうちに業務の無駄が発生している可能性があります。
メーカーの知的財産権侵害のリスクがある
第三者保守サービスに切り替えるときは検証作業の実施やアドオン開発などを提供する必要があります。これらがメーカーに対する知的財産権の侵害やライセンス契約違反に当たる可能性が否定できません。
アメリカでは、第三者保守サービス会社に対してメーカーが損害賠償を求める裁判を起こし勝訴しています。
第三者保守サービスの導入事例
パソコンの延命と継続利用を実現
浄水場の監視装置(データロガー)で使用する産業用パソコンがメーカー保守期限をむかえていましたが、新しいパソコンに入れ替えるとすれば、大規模な予算をかけて監視装置システム全体を更新しなければならない状況にありました。
しかし、使用する産業用パソコンの修理・保守を第三者に委託する方法があることを知ったことがきっかけで、パソコンの延命とシステムの継続利用を実現することができました。参照元:株式会社シェアード・ソリューション・サービス(https://www.3scom.jp/voice/moroyama.html)
年間保守サポート費用を従来の半額に削減
無添加化粧品や健康食品を展開する事業会社が、採用するERPであるSAP ECC 6.0システムの保守サポートを第三者保守に切り替え。
第三者保守契約により、安定したSAPアプリケーションを最低15年間にわたり運用することが保証され、高品質なサービスを従来の50%の年間保守サポート料金で受けられるようになった。参照元:Rimini Streer(https://www.riministreet.com/jp/press-releases/fancl-switches-to-rimini-street-support/)
製造業の現場におけるシステム延長
5年間のメーカー保守の後、1年間はメーカー保守を延長できたものの、その上で動かしているシステムをそのまま使っていくのか、改修していくのか、というところで、第三者保守を導入して、システム延長を選択。参照元:株式会社ゲットイット(https://www.get-it.ne.jp/interview_third-party_kokuyo/)
第三者保守サービス導入を検討する際によくある質問
Q1.第三者保守サービスの導入メリットを教えて下さい
メーカ保守と比べて、より安価にサービスを受けられる可能性がある点、メーカー保守切れ(EOSL)になった場合でも、修正・メンテナンスに対応してもらえる点、マルチベンダー対応が可能な点などが挙げられます。
Q2.第三者保守サービス導入にリスクはありますか?
知的財産権侵害やライセンス契約違反のリスクほか、アドオンが肥大化するリスク、第三者保守ベンダーの事業継続性に関するリスクなどがあります。ベンダーを選ぶ際には、安さだけでなく、実績や信頼性の高さも重視する必要があります。
第三者保守サービス会社の選び方
第三者保守サービス会社を選ぶ際は、「保守形態」「スピード」「実績」の3つをポイントに比較するのがおすすめです。それぞれどのようなポイントを見ればよいか解説します。
保守形態はオンサイト保守であること
保守のサービス形態には、大きく分けて「オンサイト保守」と「センドバック保守」があります。第三者保守を選ぶ際は、「オンサイト保守」を選びましょう。
オンサイト保守は、コンピューター機器やシステムが置かれている場所に直接来て保守をしてくれるサービス形態です。不具合が発生した場合は、担当の技術者がすぐに派遣されます。
目の前で修理してもらえるだけではなく、修理後の注意点なども教えてもらえるため、安心感が大きいです。メンテナンス品質が良い業者を選んでください。
一方センドバック保守は、故障した機器を窓口に発送して修理・交換してもらう形態のサービスです。機器が復旧するまでの間は、代替品を送ってもらえます。
機器を保守に送る前に代替品を送ってくれるシステムは「先出センドバック」です。先出センドバックは、代替品があるため、機器を使用できない期間が生じません。
しかし、後出しセンドバックの場合は、機器を使用できない期間が生じます。
また、機器を送ってしまうため、何が行われているか把握できず、修理中も修理後も不安が残りがちです。
対応スピードが速いこと
機器の不具合は、いつ発生するか分かりません。いざ発生したときは、対応スピードが重要です。不具合が発生したままでは業務に支障が生じます。不具合の内容によっては、利益の機会損失にダイレクトにつながる可能性もあるでしょう。
対応の遅れは、そのまま業務の遅れ、利益の減少につながります。第三者保守サービスを選ぶときは、迅速に対応してくれる業者を選びましょう。問い合わせへの対応スピードが遅い業者は注意してください。
ただし、スピードが速くても仕事のクオリティが低いなら意味がありません。丁寧で迅速な対応をしてくれる業者かどうかを見極めることが大切です。
実績が豊富にあること
企業活動において、IT機器やシステムは重要な役割を果たしています。その保守を任せる業者は、コストだけで選ぶのではなく、品質も見極めてください。品質を見極める方法のひとつが実績の確認です。
どんな企業の保守を請け負ってきたのか、どのくらいの実績があるのかをチェックしましょう。実績が豊富な業者を選んでください。
第三者保守サービスまとめ
第三者保守サービスは、メーカーの保証が切れた後、新しい機器に入れ替えるまでのつなぎのサポートです。安定して稼働している機器をサポートが切れた後も使い続けたいときに活用できます。
第三者保守サービスを選ぶときは、「オンサイト保守に対応しているか」「対応は迅速か」「実績は豊富か」の3ポイントをチェックするのがおすすめです。この記事で紹介した会社も参考にしていただきながら、自社の希望に合うサービスを提供してくれる会社を選んでください。
本記事は、2023年09月時点の情報をもとに作成しています。掲載各社の情報・事例をはじめコンテンツ内容は、現時点で削除および変更されている可能性があります。あらかじめご了承ください。