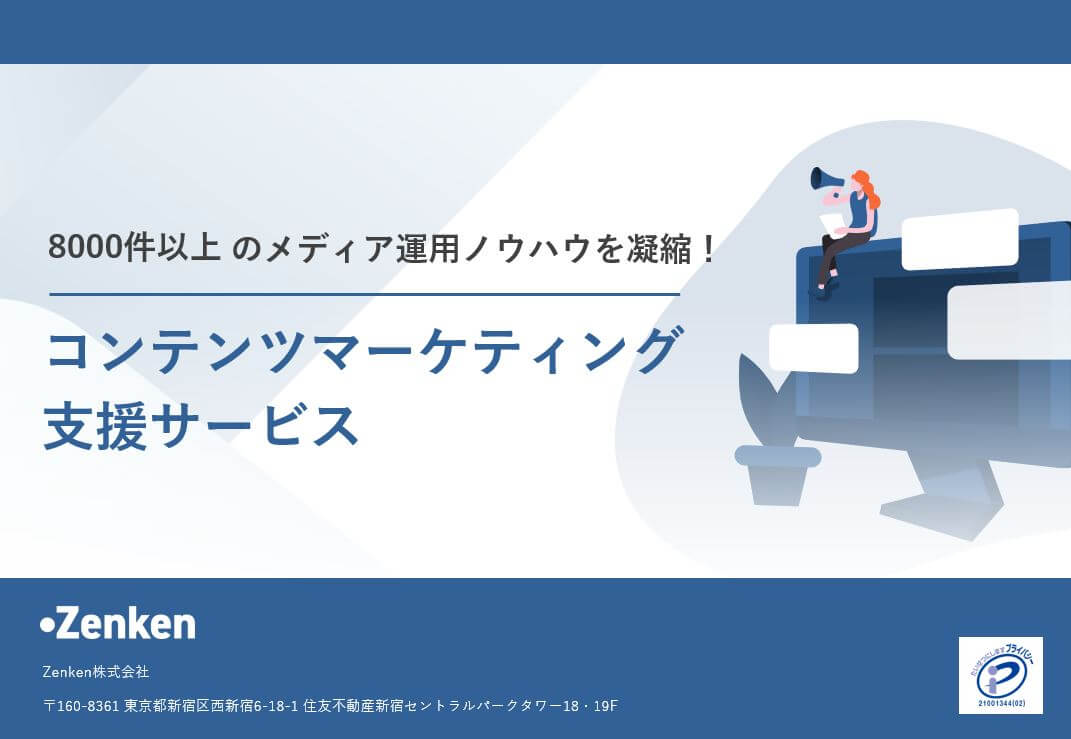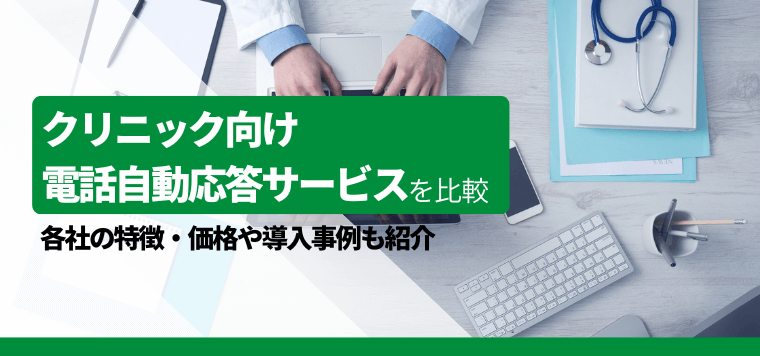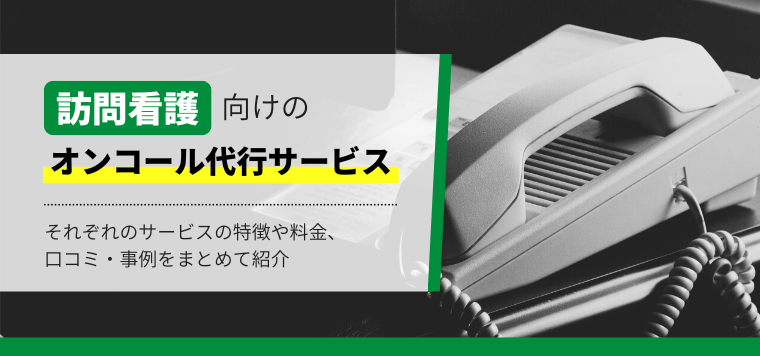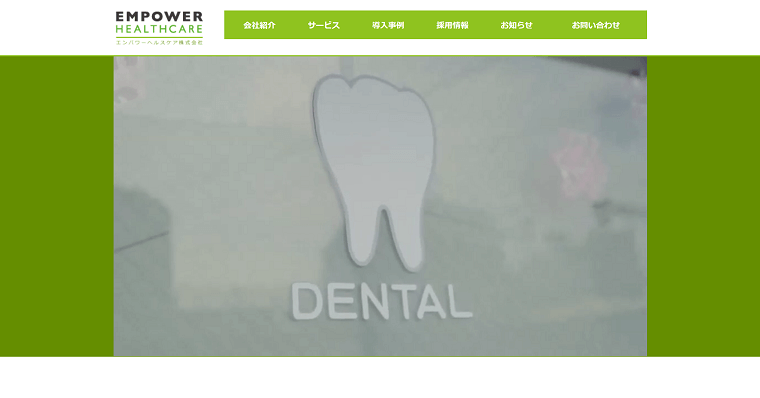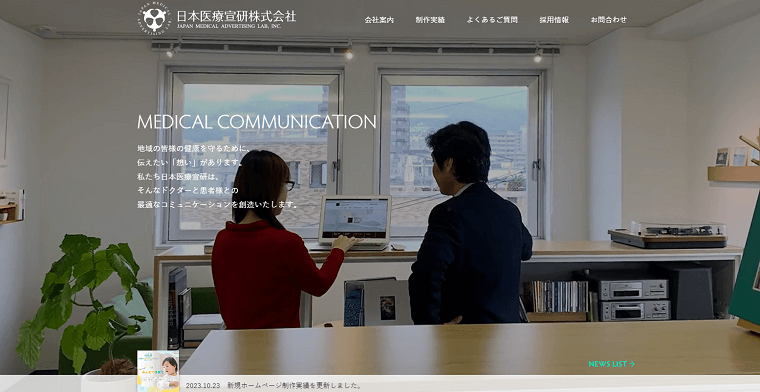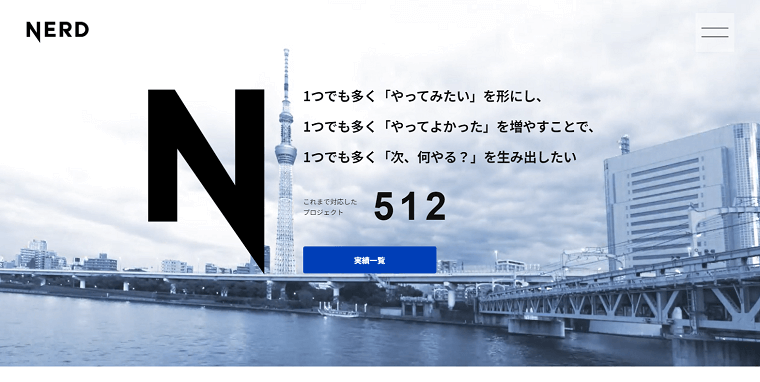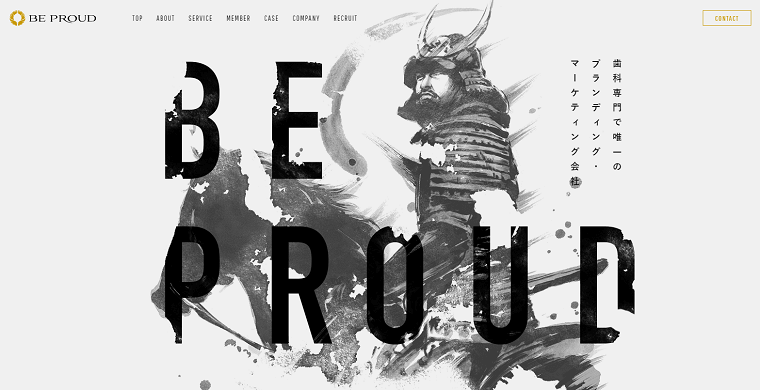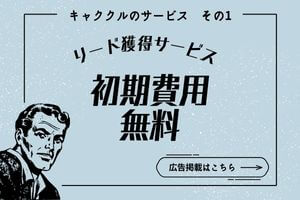医療系コンテンツマーケティングの注意点と成功事例
最終更新日:2024年06月07日
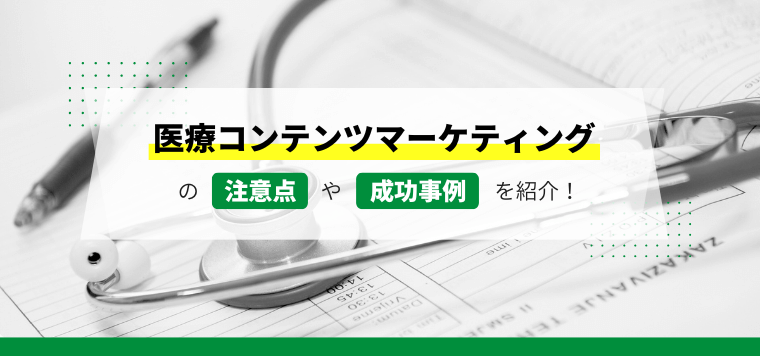
本記事では医療系コンテンツマーケティングを成功させるコツや具体的な施策、さらに制作時の注意点について解説しています。コンテンツマーケティングによる売上につながる集客を検討されているかたは、本記事を参考になさってください。
キャククルを運営しているZenken株式会社には、医療を含む120以上の業界でコンテンツマーケティングを行ってきた実績があります。「記事の作成代行を考えている」「コンテンツマーケティングの外部依頼を検討している」という方は、ぜひ下記の資料を参考にしてみてください。
\ 今すぐ資料を無料ダウンロード! /
医療系コンテンツ制作時に注意しなければいけないこと

キーワード選定
医療や健康系のジャンルでコンテンツマーケティングを展開するのであれば、もっとも重要なのがキーワード選定です。
コンテンツマーケティングにおいて、「どのようなキーワードで検索しているユーザーに対して、どのような情報を発信するか」を考えなければなりません。適切なキーワードで適切な情報を提供できれば、自社サイトへの訪問が問い合せや予約といった具体的な行動につがりやすくなります。
関連法規の順守
他の業界でももちろん、法規を守ったマーケティング活動が求められています。関連法規の順守は、国や規制機関だけが重視していません。Googleも医療など命や生活にかかわるコンテンツの質に関して、厳密なルールで審査をしています。
正しい情報であることはもちろんのこと、生活者に誤解を与えたり、露骨に誘導したりするコンテンツは低品質とみなされ、検索結果の上位に表示されません。
上位表示されないということは、人の目に触れないということ。コンテンツマーケティングはユーザーに記事を読んでもらうことを前提しているので、上位表示されるようにルールを守った制作が必要です。
以下に医療系・健康系コンテンツマーケティングで留意すべきポイントをまとめておきます。
- Googleポリシーや医療広告ガイドラインなどの法令に抵触しない
- クリニック公式サイトやブログは一種の広告であることを認識する
- ユーザーに優良誤認・有利誤認を与える誇大広告を打たない
- 予約などを執拗に求めているだけのページを作らない
こういった制限のため、医療業界のコンテンツマーケティングは難易度が比較的高い点が特徴です。通常の業務を対応しながら質の高いコンテンツの制作が難しそうな場合は、トラブルの未然防止という観点から、コンテンツマーケティングを外部のパートナーに依頼することをおすすめします。
コンテンツマーケティングに求められている本質を理解する

インターネットのユーザーが医療や健康に関する悩みを検索する理由は、抱えている悩みや心配などを解決したいからです。
どんなにユーザーにとってメリットのある治療内容であっても、ユーザーが求めている回答ができていないコンテンツでは、ユーザーは離脱してしまいます。
例えば検索結果に出てきたタイトルと、実際にクリックして開かれたページに書かれている内容が異なっている場合などで、キーワードや目をひくタイトルを気にするあまりに陥りやすいケースです。
コンテンツが非常に充実した良い内容であっても、タイトルと内容の不一致で求めている情報が得られなければ、解決を求めているユーザーの心には刺さりません。
医療系はGoogle広告ポリシーや医療広告ガイドラインに違反しないコンテンツ制作を
インターネットの検索でもっとも多く利用されているGoogleには厳格な広告ポリシーが設定されており、違反をすることで広告や検索の上位から外れてしまいます。
「広告」とつきますが、これは広告枠の宣伝だけに限ったものではありません。オウンドメディアとして制作しているサイトでやホームページ、SNSの公式アカウントやスタッフブログも広告に該当します。
平成29年の通常国会で成立した医療法等の一部を改正する法律(平成29年法律第57号)により医療機関のウェブサイト等についても、他の広告媒体と同様に規制の対象とし、虚偽又は誇大等の表示を禁止し、是正命令や罰則等の対象とすることとした。
(引用元:厚生労働省「医療広告ガイドライン」(https://www.mhlw.go.jp/file/06-Seisakujouhou-10800000-Iseikyoku/0000209841.pdf)
なお、キャククル内で「医療広告ガイドライン」について徹底解説していますので、医療広告の規制や限定解除などについては、下記リンクボタンより別ページをお読みください。
専門性とエビデンスに裏付けられたコンテンツマーケティングを
医療広告のガイドラインやGoogleのポリシーなどを違反しないように制作をすることが大切ですが、それを気にするあまり内容がおろそかになってしまってもいけません。
広告ポリシーや医療ガイドラインに注意をして、かつ専門的な立場からユーザーの役に立つ情報を発信していかなければ他のWebサイトに埋もれてしまうため、ライバルサイトとの差別化ができなくなってしまいます。
関連法規に抵触せず、かつユーザーの心に刺さるコンテンツを制作していくためには、Googleが評価する専門性や権威性、更新性などを盛り込んだコンテンツマーケティングが求められます。
医療系コンテンツマーケティングのオウンドメディア戦略

医療系のメディアを自分たちで制作・運用するのは、通常業務を考えれば不可能に近いものです。できるとしたら、ホームページに少しずつコンテンツを追加していくことくらいだと思います。
そこで多くの医療機関に導入いただいているのが、第三者であるZenkenが制作・運用する戦略的Webメディア「ポジショニングメディア」です。
「ポジショニングメディア」とは
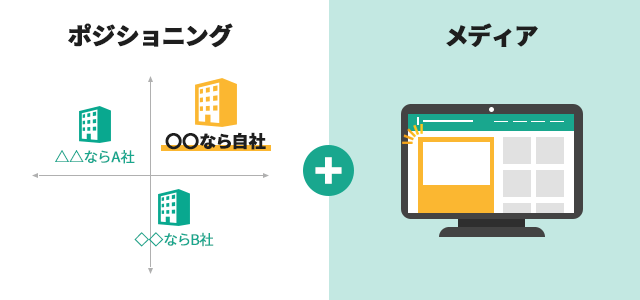
ポジショニングメディアとは、「患者の頭の中にある悩みや要望に応える」情報を提供するコンテンツマーケティングのことです。
医療系比較サイトやポータルサイトとの違いは、徹底的に患者目線でコンテンツマーケティングを実施できる点。医師に医療監修やアドバイザーをおねがいするなどして、エビデンスに基づいた正しい情報を発信します。
なぜ治療を受けたいと思うのか、どのような悩みを抱えているのか、なにに不安を感じているのか。これを解決に導く記事を盛り込みながら、自院の強みや特徴がそのニーズを満たす存在であることを提示します。
そして強引に誘導するのではなく、ユーザーが納得して「この先生に相談してみよう」「このクリニックを受診してみよう」と感じるようなメディアを独自に制作・運用していきます。
ポジショニングメディアには、以下のような利用価値があります。
- 自院の特徴に魅力を感じてもらい、ファンをつくりだす
- 競合他院との差別化とブランディングを同時に実現できる
- ポジショニングメディア内で納得したユーザーを獲得できる
もちろん医療のジャンルによっても違いはありますが、ポジショニングメディアの導入前と後とでは、明らかに問い合わせの質が変わってきた、というお声を非常に多くいただいています。
ポジショニングメディアの資料は下記のページから無料でダウンロードできます。導入企業様の成功事例も多数掲載されています。
コンテンツマーケティング成功事例~ファイザー株式会社~

医療関連の成功事例として、ヘルスケアマーケティングを幅広く展開させている会社があります。その会社とはファイザー株式会社。
健康に関連するサイトを非常に多く制作しており、その数はなんと29サイトにもおよびます。
テーマの一例は以下の通り。
- 男性脱毛症
- うつ病パニック障害
- がん
- 緑内障
- リウマチ
- 禁煙
- 頭痛
命にかかわる病気から、日常的に悩んでいる身近な症状まで幅広く網羅しています。
それぞれ症状について専門家として詳しく解説しているWebサイトではありますが、サイト内でファイザー社製品を宣伝しているわけではありません。ここが大きなポイントです。
あくまで患者や患者の家族の悩みや不安に応えるかたちでコンテンツマーケティングを展開しています。
コンテンツマーケティングの目的は「患者の通院」
ファイザー株式会社は製薬会社なので、会社としては薬が使われることで多くの人の役に立ち収益が増えることになります。
しかし実際に薬を処方するのはクリニックであり、直接患者に対してアプローチできません。製薬メーカーには厳しいプロモーションコードがあり、自社製品の広告が非常に厳しく制限されています。
そこで手段としてとった方法が、患者に対して自社の医薬品が処方される症状側からアプローチ、各症状や疾病についてキーワードごとに解説しています。症状が深刻な場合は医師へ相談をと結んでいます。
コンテンツマーケティング提供によるプロモーション効果は、だいたい下記のようなものです。
- 悩みをもつユーザー(患者)がファイザー株式会社のサイトを見る
- ファイザー株式会社のサイトを見て病院で診察を受けるべきと認識する
- 病院やクリニックにユーザーが診察を受け通院する
- 結果的にファイザー株式会社の薬の処方につながる
日常的な悩みを抱えるユーザーに対し、症状や病気に関する情報を提供することで、クリニックを通じて最終的にファイザー株式会社の薬を使ってもらうという流れです。
生涯でどんな病気にもかかったことのないという方は日本のなかではほとんどいないでしょう。そういう意味では潜在的患者層に向けた情報提供を継続することで、同社の認知度も高まるという仕組みです。
ヘルスケアの啓蒙に徹したマーケティングの展開が成功の秘訣
ファイザー株式会社の事例では、29種類の症状についてをひとつのサイトにまとめているのではなく専門的な内容をジャンルごとに分けて別々のサイトとして制作しています。
別々にするのは労力がかかるところではありますが、それぞれのサイトが症状ごとに特化していることで個々の専門性が高くなっているのです。
さらにコンテンツの内容としてファイザー株式会社の製品を宣伝するのではなく、症状や病気の情報をコンテンツとして予防や症状改善に努めているという点も、ユーザーにとって利便性が高く有益なサイトとなっています。
- ひとつの症状に対して特化し、専門性の高いサイトとなっている
- ユーザー求めている内容がコンテンツ化されている
- ユーザーにとって非常に有益なコンテンツである
という評価をGoogleから受け、さまざまなキーワードで上位表示(一般に1位から5位以内)を実現しています。
医療コンテンツマーケティングには明確な目的が必須
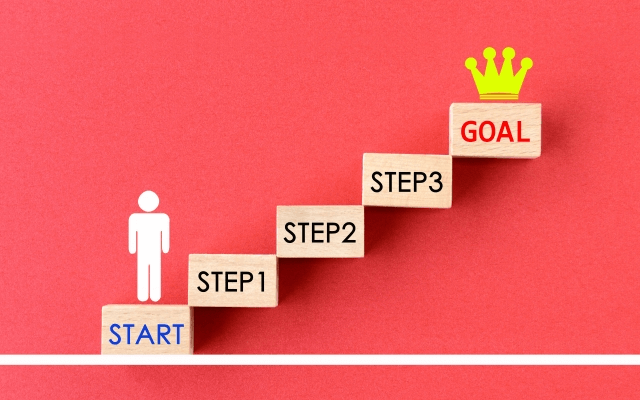
医療のコンテンツマーケティングはWebサイトを制作する前に明確な目的を設定しておくことが不可欠です。ゴールが見えていなければコンテンツ内容もずれ、結果として検索結果からも埋もれてしまい、かけた労力が無駄になってしまいます。
特にコンテンツマーケティングは即効性がある広告の方法ではなく、見込み患者を育てていく長期戦略なので、作業をするリソースも多く用意しなければいけません。
目的が定まっていないままだと、間違った方向へたくさんのリソースをかけて進んでいくことになります。
医療のコンテンツマーケティングはペルソナ別にテーマを絞る
医療のコンテンツマーケティングには、ペルソナの設定が不可欠です。
- 男性or女性
- 年代
- 日頃から抱えている悩み
- 将来への不安
- 経済的事情
- 家族構成
- 仕事・生活環境
などなど、これらの要素を設定したペルソナをつくり、どのようにアプローチをしていくのかを考えてコンテンツを制作します。
病気や症状によっては男女差や年齢による差異がないものもありますが、当事者意識を持ってもらうことがコンテンツマーケティングを成功させるポイントになるため、広く薄くというテーマ設定はおすすめできません。
医療系コンテンツの制作実績が豊富にある会社に依頼する
医療系コンテンツを制作する際のポイントをまとめます。
- ペルソナをつくり、ターゲットを明確にする
- 上位表示を狙うために専門的な立場から求められている情報を提供
- 薬機法や広告ポリシーを違反しないようにコンテンツを作成
医療系の場合、特化している専門情報を提供できる強みをもっています。しかしその情報を医療ガイドラインに注意しすぎて不充分な情報になってしまわないように注意しなければいけません。
医療系コンテンツマーケティングの注意点と成功事例まとめ

医療系コンテンツマーケティングは医療広告ガイドラインや関連法規に沿った制作をする必要があるため、経験が豊富なスタッフがいることが望ましいです。
Zenkenであれば、医療広告ガイドラインのほか各関連法規に関するチェック体制が整っています。
クリニックのエリア集患などの実績もあり、多くのコンテンツを制作してまいりました。そのためさまざまなクリニック様より、日々お問い合わせをいただいています。
医療系のコンテンツマーケティングを検討している方向けに制作した資料を無償で提供していますので、下記よりダウンロードしてください。
自由診療系のポジショニングメディアの事例も豊富にございます。