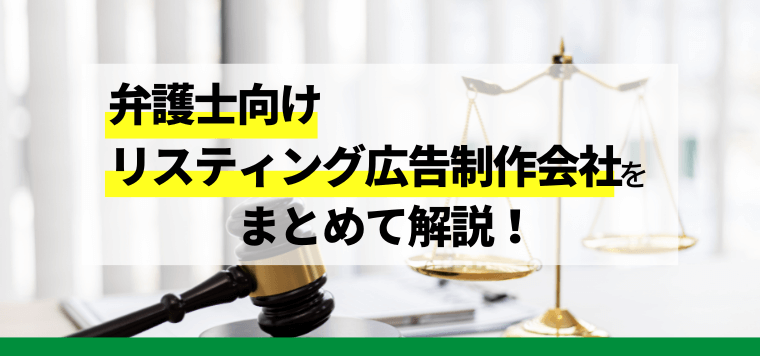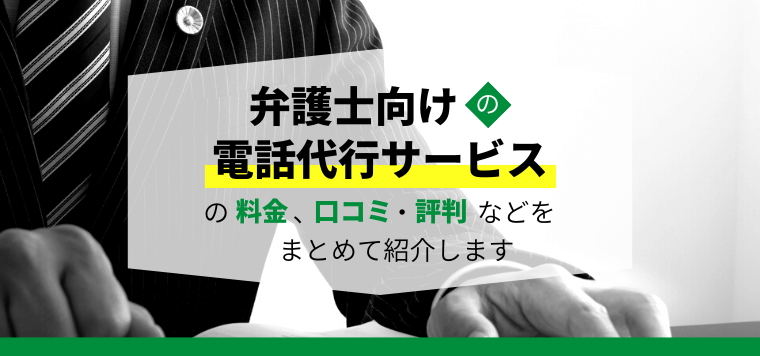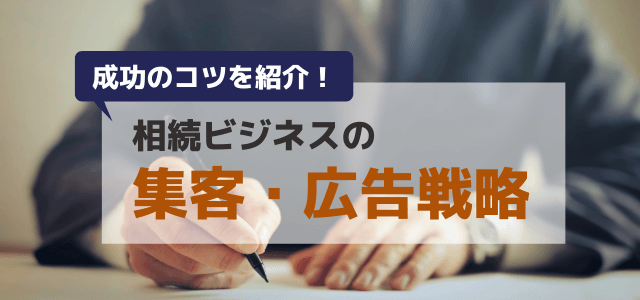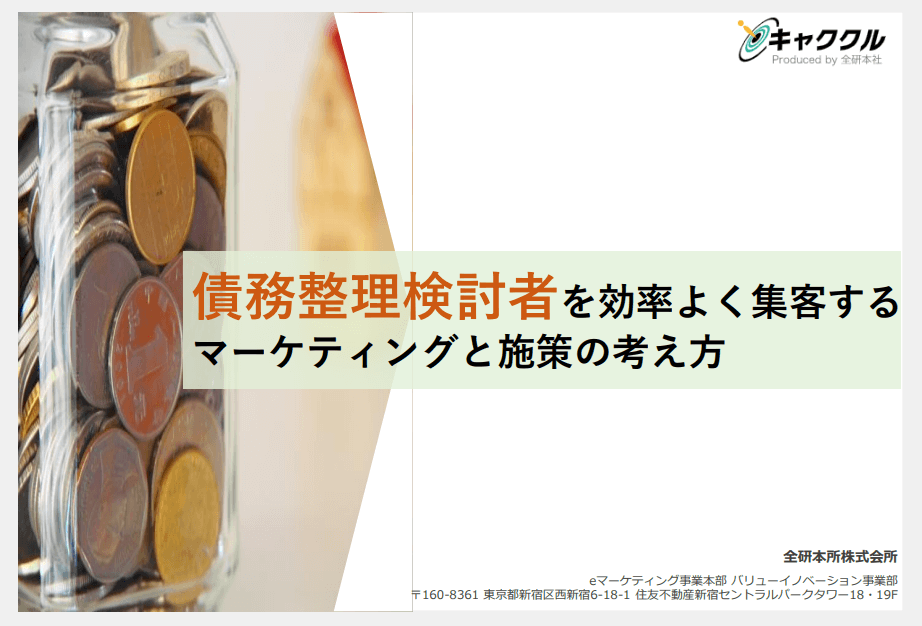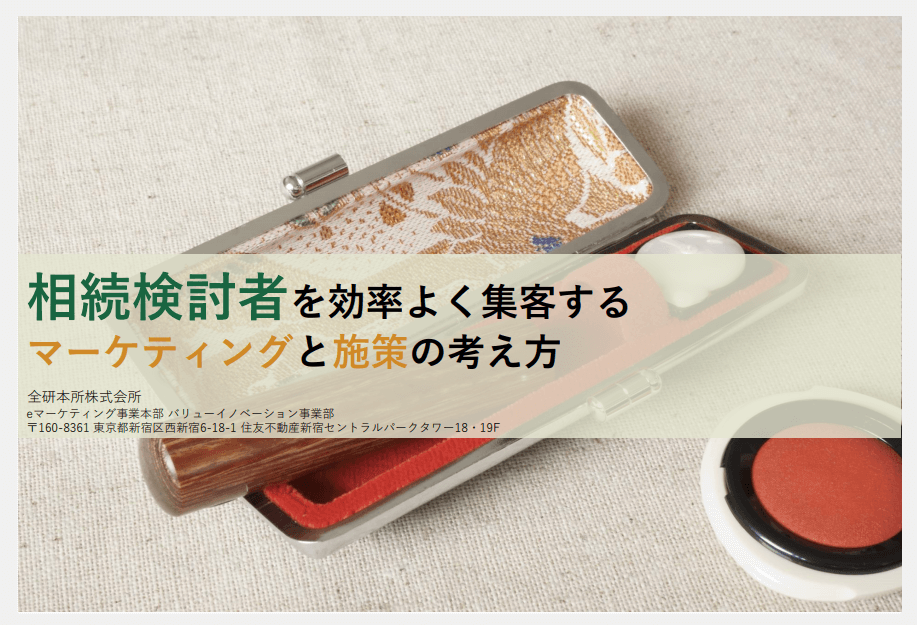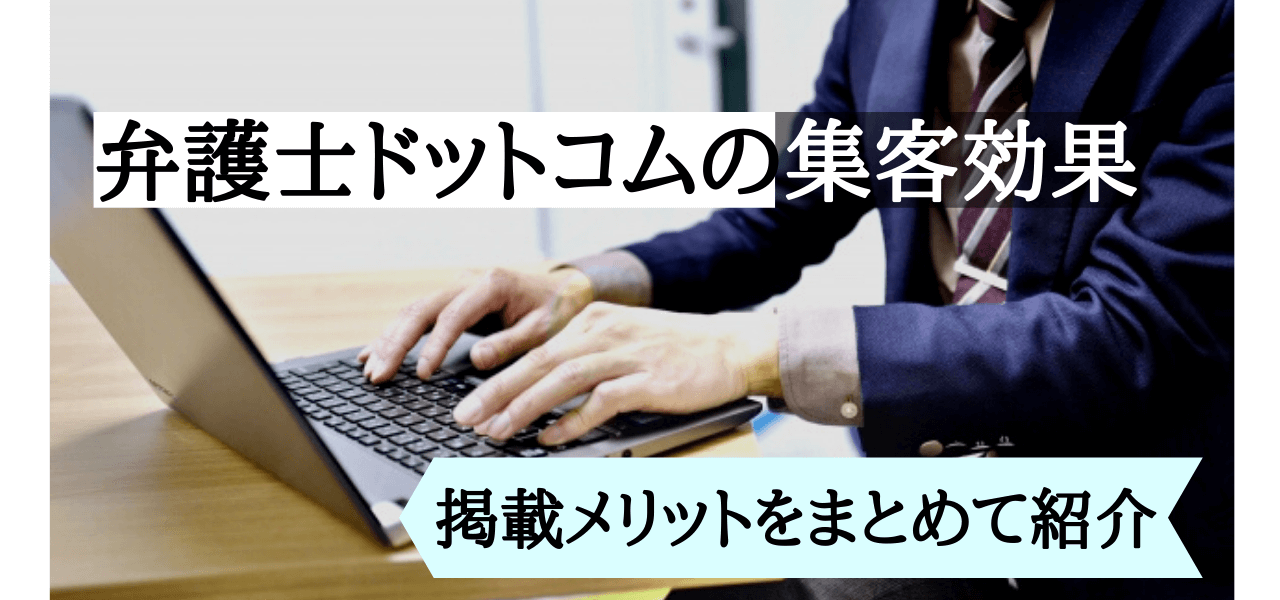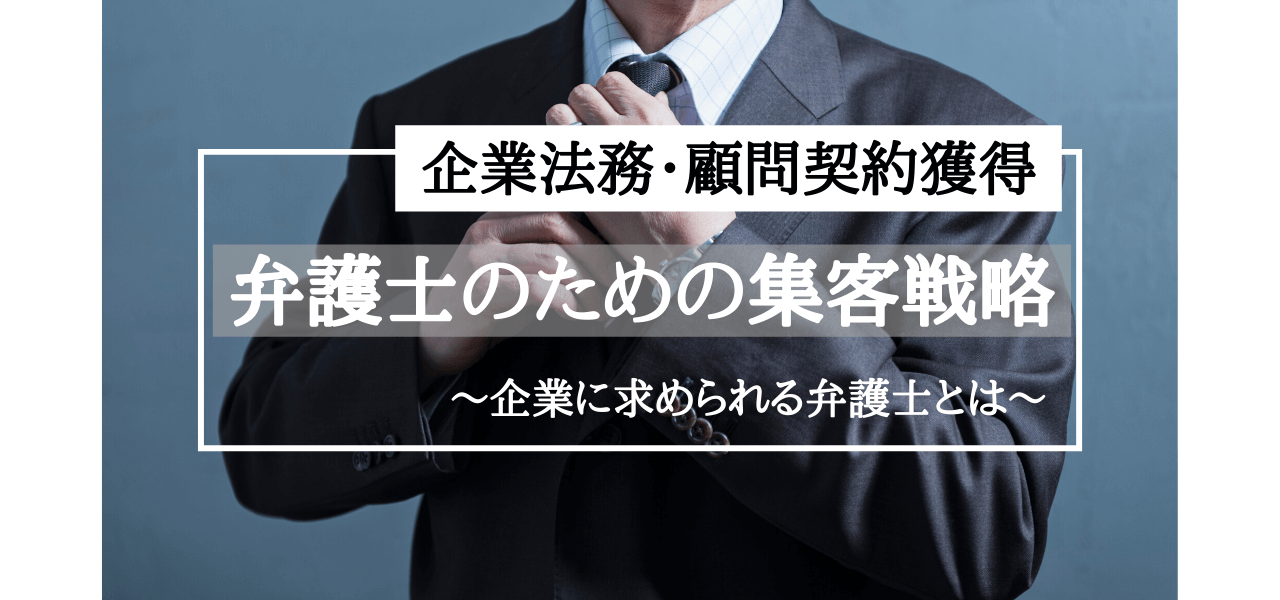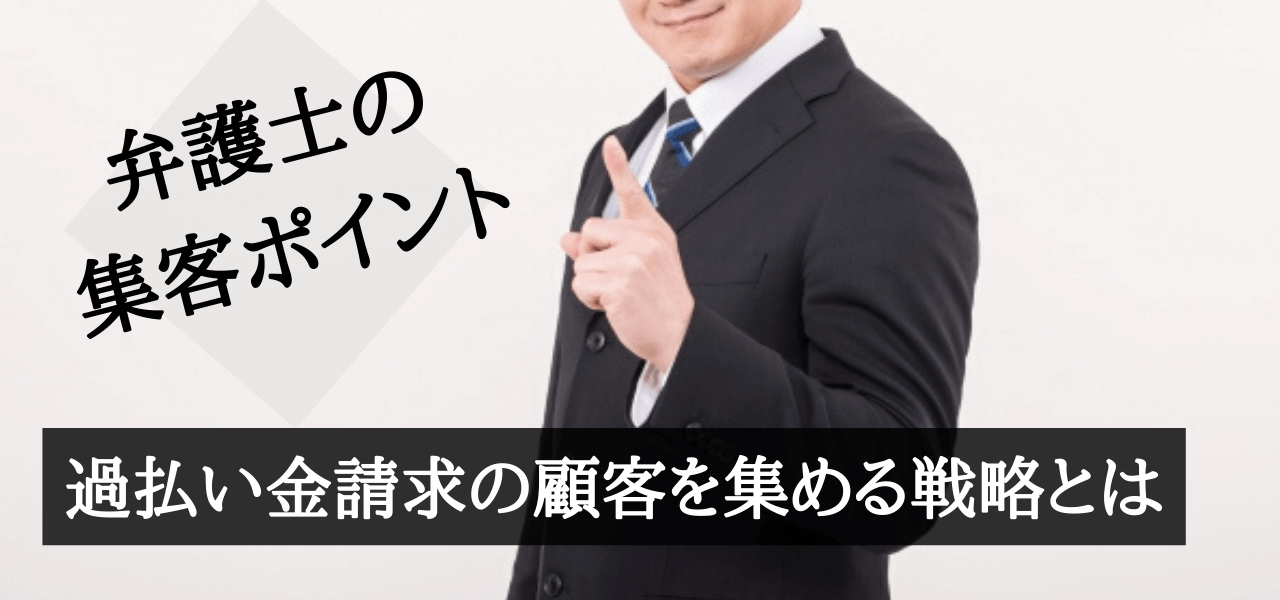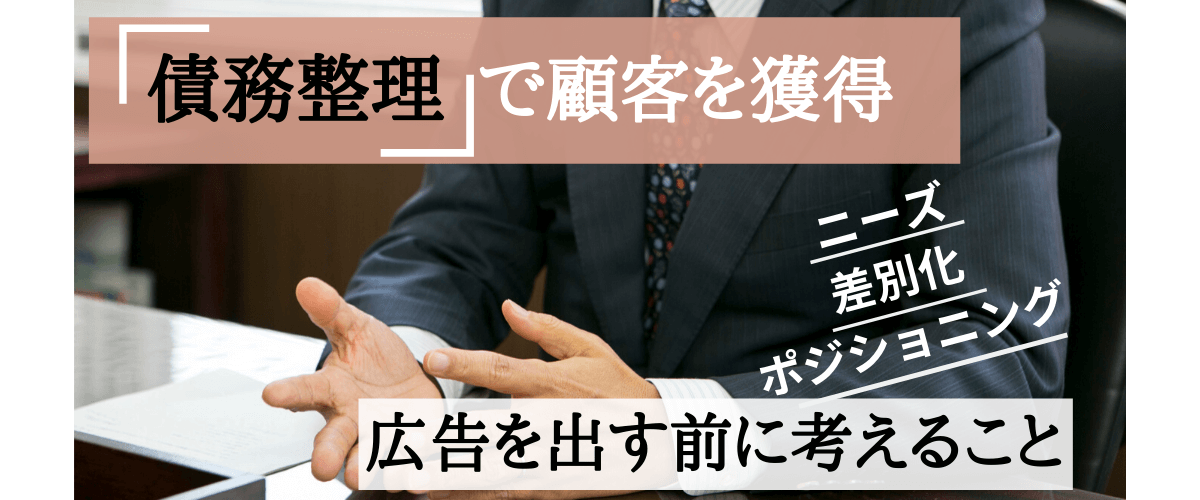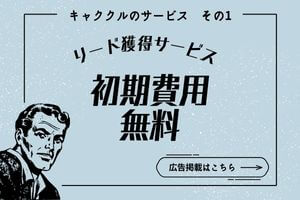弁護士の広告規制を知って正しいマーケティング戦略を取ろう
最終更新日:2024年03月08日
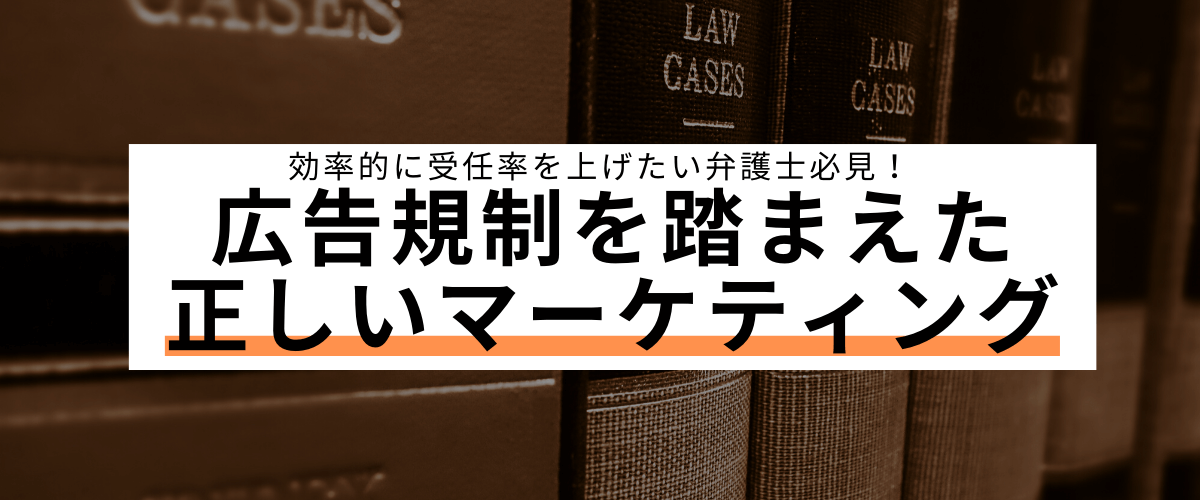
この記事では弁護士事務所が広告やマーケティングをする際に注意しておくべきことをまとめています。
特に重要なポイントである「弁護士の業務広告に関する規定」「その規定の解釈を示した指針」「景品表示法」の3つを詳しく紹介しますので、これから広告やマーケティングをするなら必ずおさえておきましょう!
またキャククルでは弁護士事務所のWeb集客にお役立ていただける「オウンドメディア制作」を提案しています。
離婚、企業法務、過払い金、自己破産、不動産、債務整理、エリアに特化した弁護士事務所の紹介など、様々なテーマでオウンドメディアを制作してきた実績がありますので、ご興味ある方は以下のページよりチェックして見てください。
弁護士・法律事務所の広告規制(ルール)
弁護士業界では、2000年までは広告することができませんでした。
理由としては、広告をすることにより、勝訴見込みがあまりない訴訟を起こし、依頼者の利益が損なわれることがあってはいけないと考えていたから。
また「広告は正義の味方である弁護士がするのははばかられる」という考えもあるでしょう。
弁護士の広告は2000年に自由化(解禁)されました。今では、多くの弁護士事務所がホームページなどで、インターネット広告をしています。
ただし、弁護士がインターネット広告を行う場合には特に厳正なルールがあるので、注意が必要です。
たとえば、
- 弁護士の業務広告に関する規定
- その規定の解釈を示した指針
- 景品表示法
などによる規制があります。
弁護士広告ルール「専門」という言葉は控えたほうがいい
弁護士事務所の広告では、特定の分野の専門という表現が使われていることがあります。たとえば、遺産相続専門や交通事故専門など。
ただ、これは問題で、それは弁護士業務広告の規制の指針上で控えた方がいいとされています。
専門という言葉を使えないとすると「見込み客にアピールすることができない」と考える人もいるでしょう。
自分の得意分野をアピールしたい場合には、「強い」という表現を使えばいいのです。強いという言葉は、弁護士業務広告の規制の指針上で、使っていけないとなっていません。
但し、強いという言葉を利用する場合には、広告規制に違反しないために、その根拠を持つことが必要です。立証責任は弁護士側にあると考えられています。
面識のない人への訪問や電話による広告は禁止
「弁護士の業務広告に関する規程」というのがあり、これは、弁護士が広告を行う場合に知っておかなければいけない規定です。
第5条では「弁護士が面識のない人に対して、訪問したり電話したりして広告をすることはいけない」と記載。面識のない人とは、現在および過去の依頼者友人、親族ならびにこれらに準ずる人以外と定義されています。
第5条は、依頼者が、十分に考量する時間がないまま弁護士に依頼することを防ぐことを目的としています。
また、面識のない弁護士から訪問されたり電話がきたりすると、一般の人は何もやましいことがなくても「おかしな感情になりやすい」「嫌な気持ちを抱きやすい」といったことがあるので、それらを防止するのも目的としています。
特定の事件の勧誘広告も禁止
先にいいました「弁護士の業務広告に関する規程」の第6条も、注意したいです。
第6条では「弁護士が、特定の事件の当事者および利害関係人で、面識のない人に対し、郵便やその他のこれらの人を名宛人として直接届く方法にて、依頼を勧誘する広告を禁止する」としています。
たとえば、交通事故に遭った人に対してDMを送り依頼をすすめ誘うのはアウト。
例外があり、所属弁護士会から許しを得た場合は公益上の必要があるため問題になりません。
第6条は、「弁護士が事件をあさっているという印象を持たれたくない」「勧誘者に不快感を持たれたくない」「弁護士の品位と信用を失われることを防ぎたい」という目的があります。
「弁護士職務基本規程」第10条による禁止
「弁護士職務基本規程」の第10条では、「弁護士が不当な目的のため、または品位を損なう方法にて、事件の依頼を勧誘したり誘発したりするのはいけない」としています。
不当な目的とはたとえば、
- 訴えても負けると分かった上、自分が儲けるためだけの目的で勧誘・誘発する場合
- 依頼を受けて依頼者を経済的に困らせる目的で勧誘・誘発する場合
品位を損なう方法とはたとえば、
- 依頼者に不安や恐怖を与えるような言葉を執拗に使う
- 法律知識のなさにつけこみ法的に嘘なことを依頼者にいう
などがあります。弁護士は昔より増加しているので、仕事を取りにくくなっているのは間違いないでしょう。
適切な広告を出稿するために、他の業界以上に正しく広告活動を行い、ユーザーから依頼してもらえる流れに向けたマーケティングが出来ているかどうかこまめに確認することが、重要になってきます。
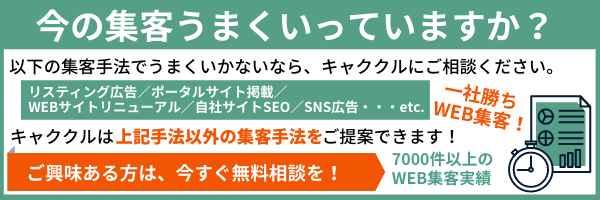
弁護士が広告・マーケティング施策をするときに知っておくべきこと

昔は、法律問題に困った人は紹介により弁護士と出会っていました。しかし最近はベテラン・新人を問わず、また年代も問わず、広告で仕事を獲得する弁護士が増えています。
特にインターネット社会の今日ではネット集客が効果的なので、有効なマーケティング施策として導入する人が多いです。
弁護士業界には、広告規制があります。ここでは、広告でのアピール時に注意したいことを説明します。
注意事項を守れば、余計なトラブルに巻き込まれることが減り、安定した事務所経営ができるようになるでしょう。経営が安定できれば、顧客のために全力を尽くせるようになります。
「弁護士の業務広告に関する規程」の7つの禁止規定
「弁護士の業務広告に関する規程」には、広告の禁止規定も設定されています。具体的には次のような広告が規定に抵触します。
- 1.事実に合わない広告
- 2.誘導または誤認のおそれのある広告
- 3.誇大または過度な期待を持たせる広告
- 4.困惑させまたは過度な不安をあおるような広告
- 5.特定の弁護士・外国法事務弁護士・法律事務所または外国法事務弁護士事務所と比較をおこなった広告
- 6.法令に違反する広告または日弁連もしくは所属している弁護士会の会則や会規に違反する広告
- 7.弁護士の品位または信用をそこなうおそれがある広告
上記の規定は、市民への弊害が起きないようにと考えられたものです。
禁止規定を守れば広告時のトラブルに巻き込まれにくくなるといえますが、抽象的文言もあるので、注意が必要です
弁護士の広告時に訴訟の勝訴率を表示するのは注意した方がいい
日弁連の「弁護士の業務広告に関する規程」4条1号では、訴訟の勝訴率を、表示できない広告事項としています。
依頼者が一番知りたいことは、裁判で勝てるかどうかなので、別にいいのでは思う先生もいるかもしれません。
しかし、訴訟で勝訴を得るには証拠が必要です。主張を確実に通すことができるような証拠を相手方が持っていて、それを覆すような証拠を持っていない場合には、どんなに優秀な弁護士でも負けてしまうものです。
依頼者から「勝訴率をみて先生に依頼したいのに、この結果はなんだ」というクレームが入るのを防ぐことが狙いなのでしょう。
弁護士の広告は特殊性がある
少々乱暴なデータになりますが、裁判所のデータによれば、平成30年には3百62万2,502件もの事件が起きています。しかし、そのすべての被害者が弁護士に相談したわけではありません。
法律サービスは、依頼者の抱えている法律問題に合わせたオーダーメイドにする必要があるため、事前にどのような対応を行うか説明するのが難しいものです。
依頼者は、弁護士に事件処理の依頼した場合にどんなことをしてくれるのか分からないまま、委任することが多いもの。結果がよければ問題ありませんが、悪ければクレームになりやすいです。他の業界以上に大げさな表現は控えた方がいいでしょう。
不当な実績の表示をするのは広告ルール的に禁止
弁護士は、今までの実績を広告で表現するのはルールとして問題ありません。
依頼者の希望は概ね以下のようなものです。
- 全面勝訴判決を得たい
- 相手方との交渉との際に自分の主張を何がなんでも認めさせたい
弁護士の実績が確認できれば、自分が依頼したあとの結果がイメージしやすくなるので、仕事の依頼につながりやすくなります。
その一方、実績を過剰にアピールすると問題になることも念頭に置いてください。誤導または誤認のおそれのある広告に該当するかもしれないからです。
実績を広告する場合には、事実を装飾せずにそのまま記載するようにしましょう。
顧問先・依頼者・受任中の事件も表示できない
弁護士の広告のガイドラインとなる「弁護士の業務広告に関する規程」では、顧問先または依頼者の情報を広告事項とすることを禁止しています。個人情報の流出に繋がるほか、弁護士に相談していることが公になれば「法的問題を抱えている」というイメージを世間が持ってしまうからです。
受任中の事件については、細かい情報を出してしまうと依頼先が露呈してしまう可能性も上がります。個人情報と依頼内容の守秘義務を順守しましょう。
過去に取り扱いした事件や関与した事件も広告に利用してはいけいない
たとえば「何年何月何日にどの地域で暴行事件が起こった」などの情報はNGです。デジタルタトゥーが問題になっている昨今、実際に発生し弁護を取り扱った事件でも、広告への利用は慎重になる必要があります。
「弁護士の業務広告に関する規程」の広告禁止には例外がある
顧問先・依頼者・受任中の事件・過去に取扱した(関与した)事件は、原則的に広告に利用することは禁止されています。しかし、依頼者の書面による同意がある場合には問題となりません。口頭での確認では後々「言った・言わない」の騒動に発展する可能性があるため、やはり書面で同意を得ておきましょう。
また、依頼者が特定されない場合で、かつ、依頼者の利益が損なわれるようなことがない場合には、同意がなくても広告に表示できますが、この場合は本当に特定できないか、また利益が損なわれないのか、検証してから広告するのがいいでしょう。
弁護士はSNSを利用する際も注意が必要
SNSを利用する弁護士は増えています。弁護士ならではの話を聞いてみたいと一般市民がフォローするため、見込み客との接触回数が増え、仕事の依頼にもつながるからです。
しかし、弁護士がSNSを利用する際には注意すべきことがあります。それは法律相談を促す、つまり顧客の誘因を目的とした投稿の場合は弁護士広告となるため、ここまでに説明した規制が適用されるということです。
規制のため、次の表示を行う義務が生じます。
- 氏名
- 所属弁護士会
顧客の誘引を目的としていなければ、匿名投稿時でも、弁護士であることの証明は不要です。
有価物等供与をして広告することも禁止
「弁護士の業務広告に関する規程」第7条により、弁護士は社会的儀礼の範囲をこえた有価物などの利益の供与を行い広告することはできません。品位的な問題もありますし、お金を渡して仕事を受けようとすると不必要な争いが起きるからでしょう。
「社会的儀礼の範囲をこえた有価物」とは解釈の余地がある表現ですが、実際に弁護士たちの間で行われた議論では、テッシュでも該当するのではないかといわれています。今後、規定第12条により調査されるかもしれません。
広告ガイドラインとしてテレホンカードは明確にアウトとされているので、これは配らない方がいいです。
弁護士がネット広告・マーケティング施策をするときに注意しておきたいこと
ネット広告により、想定以上に依頼が増えすぎてしまう場合もあります。案件が増えすぎて処理が遅くなれば、依頼者との間でトラブルが起きることも。
適切な広告出稿と運用を行うためには、ネット広告・マーケティング施策のプロに相談することをおすすめします。
弁護士広告を正しく使い、効率的にマーケティング・集客をしよう

弁護士は社会から大変信頼されているので、品位を保ち、顧客に不利益がないように配慮することが求められます。そのため広告に関するさまざまな規制・規定・指針が設定されているのです。
業務を遂行しつつ、広告出稿時のルールを完璧に把握し、適切に運用し続けるのは困難です。
キャククルでは離婚、企業法務、過払い金、自己破産、不動産、債務整理、エリアに特化した弁護士事務所の紹介など、その弁護士事務所が得意としているジャンルでWeb集客のお手伝いをしてきました。
弁護士法や景表法をクリアした施策をご提案できますので、一度キャククルにご相談ください。
キャククルのWeb集客の
ご相談はこちら