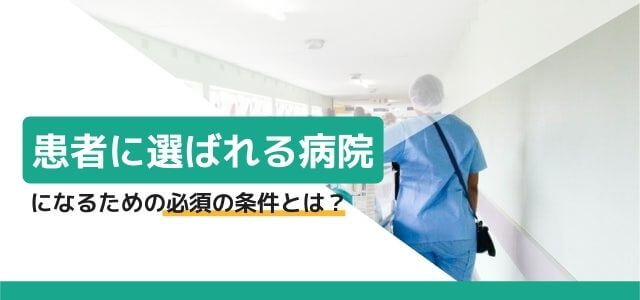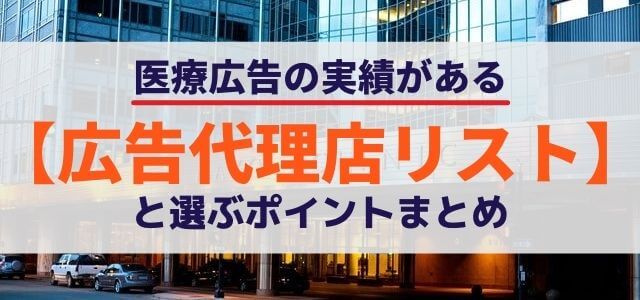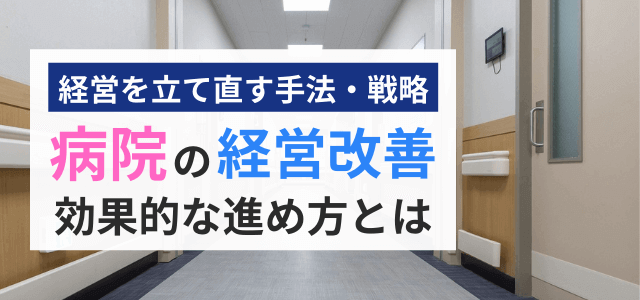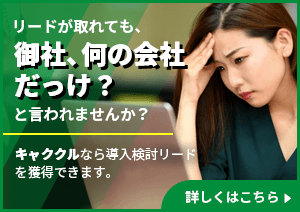中小病院向けの電子カルテおすすめ19選を徹底比較!導入事例や費用・口コミ・評判を紹介
最終更新日:2024年05月28日

従来の手書きのカルテでは、患者の待ち時間が増えたり、看護師の業務負担も大きくなりがちです。また、補助金申請や診療報酬加算は電子カルテの導入が前提になっている場合もあるので、電子カルテの導入を検討している中小病院が増えています。
この記事では、中小病院向けに電子カルテを提供する企業を紹介します。サービスの特徴や費用、導入事例などもご覧いただけますので、自院への電子カルテ導入の参考にしてみてください。
中小病院向けの電子カルテシステム一覧表
ここでは、各社が提供する中小病院向けの電子カルテシステムを一覧で紹介しています。電子カルテは自院に合ったシステムのほうが高い効果が得られるため、機能性やサービス特徴を比較して、自院に合ったシステムを見つけましょう。画像をクリックすると資料ダウンロードページに移動します。
| システム名 | サービスの特徴 |
|---|---|
 【PR】ウェブカルテⅡ 【PR】ウェブカルテⅡ |
追加費用なしでユーザーを増やせるライセンスフリーの電子カルテ! 更新費も不要で低コストを実現 ・コンパクトに始められる電子カルテ!ユーザーを増やしても料金そのまま ・視認性を重視した使いやすいカルテ画面で業務効率化 ・スムーズな連携と運用しやすいメンテンナンス性を実現 資料ダウンロードはこちら >> |
| 電子カルテシステムER | 自由度の高いシステム構成とユーザーニーズへのスピーディ対応で業務効率化をサポート |
| メディコム | 必要な機能をパッケージ化!直感的な使いやすさで業務効率アップをサポート |
| ミナリス | 価格&機能がちょうどいい!電子化を今すぐ実現できる情報システムを提供 |
| HOPE Cloud Chart II | 病院経営の未来に向けた多彩なソリューションを提供!柔軟な導入オプションが魅力 |
| AHIS | 必要な機能をワンパッケージ化!システムが苦手な方にも安心の使いやすさを提供 |
| モバカル | 電子カルテ × クラウド × モバイル端末が実現する院内DX化への第一歩! |
| Henry | 外来・入院・退院まで全業務の効率化をサポート!経営レポートの自動作成も可能 |
| OCS Cube-Smart | リアルタイムでの情報共有でチーム医療を支援!迅速な意思決定をサポート |
| HAYATE/NEO | 20年以上の導入ノウハウでシステム運用コストの削減をサポート |
| ヘルス×ライフ カルテ | 定額制×初期費用無料!初めてもシステム導入に最適なソリューションを提供 |
| セコム・ユビキタス電子カルテ | ウェブベースで場所を選ばずアクセス可能!システム維持作業やコストの心配は不要 |
| MI・RA・Is/AZ | 医療の未来を担う機能を搭載!医療サービスの向上に貢献し患者満足度アップをサポート |
| blanc | 『いつでも・どこでも・だれでも』をコンセプトとした使いやすさが魅力 |
| MALL | 導入医療施設数200件!柔軟性と拡張性に優れたシステムをリーズナブル価格で提供 |
| A-CHART | 万全のセキュリティ体制に加えICカードでログインできる使い勝手の良さが魅力 |
| 医次元 | 導入コストを削減し、必要な機能を厳選!UIを重視した使い勝手優先のシステム |
| メディカルフォース | 導入クリニック400院突破の話題システム!自由診療の業務と経営をワンストップで管理 |
| RACCO | 科目別・病床数別に使い分けが可能!カスタマイズOKで使い勝手抜群 |
【PR】追加費用なしでユーザーを増やせるライセンスフリーの電子カルテ!更新費も不要で低コストを実現
ライセンスフリーで小さくコンパクトに電子カルテを導入できるウェブカルテⅡは、Webアプリで専用ソフトが不要のため、端末を何台増やしてもパッケージ費⽤は変わりません。複数のスタッフが同時に一人のカルテを見ることも可能なので、低コストで使いやすい電子カルテです。
また、システム更新によるソフトウェアの買い換えも不要なので、無料で最新の機能を使うことが可能。長期的な運用を考えている病院はランニングコストを大幅に抑えられることができます。
中小病院向け電子カルテ「ウェブカルテⅡ」
 画像引用元:ウェブカルテⅡ公式サイト(https://webkarte.iryojoho.jp/)
画像引用元:ウェブカルテⅡ公式サイト(https://webkarte.iryojoho.jp/)中小病院向け電子カルテ「ウェブカルテⅡ」の特徴
医療現場の業務効率化に貢献するウェブカルテⅡは、パソコンが苦手な方でも操作しやすく、過去のカルテを参照しながらカルテの入力が可能なDo機能や、視認性を重視した画面でスピーディにカルテ作成ができるシステムです。
同一法人内での介護システムや各部門システムとの連携や、障害発生時でも診療業務を継続できるバックアップサーバの標準構成など、「使いやすく、繋げやすく、運用しやすい」電子カルテを実現します。
また、診療業務をサポートする利便性の高い機能も豊富。全体的な状況の把握をしやすくする外来指示状況機能や看護支援機能、メッセンジャー機能、一括指示機能、褥瘡管理機能、一括実施入力機能などがあり、業務効率化や患者サービス向上にも貢献します。
中小病院向け電子カルテ「ウェブカルテⅡ」はこんな病院におすすめ
- 最初はコンパクトにシステム導入して、少しづつ端末数を増やしていきたい
- システム導入や更新費用を考えると電子カルテへシフトチェンジできない
- パソコンが苦手なので、操作ができるか不安
\ライセンスフリーで低コスト実現/
中小病院向け電子カルテ「ウェブカルテⅡ」が選ばれる理由
【理由1】コンパクトに始められる電子カルテ!ユーザーを増やしても料金そのまま
ウェブカルテⅡは、ライセンスフリーで提供されるため、何台使用してもパッケージ費用は同じで、導入と運用にかかるコストの大幅な削減が可能です。WindowsOSがあれば専用ソフトも不要で、運用開始後もクライアントを自由に追加することができ、端末の追加や配置なども柔軟に行うことができます。
また、システム更新時のソフトウェアのパッケージ費用も不要のため、低コストで常に最新機能を利用でき、長期的な経費削減が見込めます。
【理由2】視認性を重視した使いやすいカルテ画面で業務効率化
ウェブカルテⅡはインターネット感覚で操作可能で、パソコンが苦手な方でも簡単に入力・閲覧することができます。視認性と操作性を重視した見やすい画面は、過去のカルテを確認しながら新規のカルテ入力が可能で、医者が行う記録の確認や記事・オーダ入力、文書作成などがカルテ画面からスピーディに行うことができます。
また、複数スタッフが一人のカルテを同時に参照することができ、入力時は排他制限により記録の整合性を担保します。カルテの部門間の搬送作業やアリバイ管理が不要なので業務効率化に貢献します。
【理由3】スムーズな連携と運用しやすいメンテンナンス性を実現
ウェブカルテⅡは柔軟に接続を行うマルチベンダー方式を採用することで、医事システムは富士通HOPE・ナイスMLA・ORCAとの接続を可能にし、繋げやすさを実現。また、介護システムや各部門システムと情報をシームレスに共有することで、それぞれのスタッフ間で、よりスムーズな連携と業務効率化を実現します。
さらに、ウェブカルテⅡはバックアップサーバを標準構成としており、サーバー二重化により障害時でも業務を止めることなく、安定して稼働させることができる高いメンテンナンス性と運用しやすい体制を実現します。
\簡単な操作で使いやすい/
中小病院向け電子カルテ「ウェブカルテⅡ」の料金プラン
公式サイトに料金プランの掲載はありませんでした。サービス資料をダウンロードすると担当者から連絡がありますので、その際にお問い合わせください。
中小病院向け電子カルテ「ウェブカルテⅡ」の導入事例
リハビリ部門連携と紙文書データ化で運用効率改善
診療科:内科、リハビリテーション科
病床数:約160床(回復期リハ)
- リハビリ部門システムとの連携
- 院内紙文書を一括スキャナ取込みでデータ化し運用効率改善
引用元:ウェブカルテⅡ公式HP(https://webkarte.iryojoho.jp/#case/)
複数の部門システム連携とバイタル自動取込み運用
診療科:脳神経外科
病床数:約120床(一般)
- 複数の部門システムと連携(調剤、RIS、PACS、リハビリ、給食、検体検査)
- ベッドサイドモニタからのバイタル自動取込みを運用
引用元:ウェブカルテⅡ公式HP(https://webkarte.iryojoho.jp/#case/)
\充実の便利機能で業務効率化をサポート/
ウェブカルテⅡの運営会社概要
| 企業名 | 株式会社医療情報システム |
|---|---|
| 所在地 | 大阪市中央区平野町1丁目4番8号 IJSビル |
| 創立年 | 1996年4月11日 |
| URL | https://www.iryojoho.jp/ |
\ライセンスフリーで低コスト実現/
他にもまだある!業務を効率化する文書電子化サービス
電子カルテシステムER
 画像引用元: 電子カルテシステムER公式サイト(https://www.wiseman.co.jp/products/medical/er-about/)
画像引用元: 電子カルテシステムER公式サイト(https://www.wiseman.co.jp/products/medical/er-about/)電子カルテシステムERの特徴
自由度の高いシステム構成とユーザーニーズへのスピーディ対応で業務効率化をサポート
電子カルテシステムERは、クリアなレイアウトと直感的なユーザーインターフェイスを提供しているサービスです。画面はERガイドエリア・カルテエリア・オーダーエリアの3つに区分されており、それぞれのエリアが特定のタスクに最適化されています。医療スタッフは、過去の診療記録やオーダー履歴を参照しつつ、新たなカルテの入力やオーダーの発行がスムーズに行える点が魅力です。
また、システムは、患者の診断分類や訪問記録の管理も支援。患者情報を効率的に集計し、出力する機能を搭載しています。さらに、他の部門システムと無縫に連携し、院内の情報通信技術(ICT)の整備を全面的にバックアップ。診療の効率が大幅に向上し、管理業務が簡略化されると考えられます。
電子カルテシステムERの料金プラン
公式サイトに料金プランの掲載はありませんでした。
電子カルテシステムERの導入事例
電子カルテシステムERで患者情報のトータル管理が可能に!
退院調整業務では、入院時の診療情報だけでなく、食事内容がどうだったか、日常生活動作の状況はどうかなど、さまざまな部門の情報を総括的に収集する必要があります。従来は、それぞれの部門に出向いて担当者から情報を得て文書にまとめる作業が大変でした。今では食事療養科による詳細な情報、リハビリ部門の実施内容や総合評価など、患者さんに関わるすべての情報が電子カルテを介して収集でき、提供資料の作成も効率的に行えます。業務合理化が推進され、退院調整もスムーズに進むようになりました。
引用元:電子カルテシステムER公式HP(https://www.wiseman.co.jp/case/medical/14739/)
電子カルテシステムERの運営会社概要
| 企業名 | 株式会社ワイズマン |
|---|---|
| 所在地 | 岩手県盛岡市盛岡駅西通2丁目11番1号 |
| URL | https://www.wiseman.co.jp/ |
※中小病院向け電子カルテシステムの比較表をもう一度チェックする
メディコム
 画像引用元: メディコム公式サイト(https://www.phchd.com/jp/medicom/hospitals/mcck2)
画像引用元: メディコム公式サイト(https://www.phchd.com/jp/medicom/hospitals/mcck2)メディコムの特徴
必要な機能をパッケージ化!直感的な使いやすさで業務効率アップをサポート
メディコムは、直感的な操作が可能で、各種カルテやオーダー入力を簡単に行えるようサポートしてくれるシステムです。治療情報を年表形式で表示し、詳細確認も可能。特に、中小規模病院向けに、必要な機能を厳選して標準パッケージ化し、業務負担を軽減してくれます。
また、複数端末での利用が可能で、医療情報システムとの連携をサポートしつつ、効率的なチーム医療を推進。ライセンスフリーで低コスト、短納期での導入が期待できます。
メディコムの料金プラン
公式サイトに料金プランの掲載はありませんでした。
メディコムの導入事例
統一された操作性や一括入力などの機能が好評
『Medicom-CK』はブラウザを使用し、だれもがとっつきやすい統一された操作性や一括入力などの機能が職員からも好評です。さらに端末を自由に増やせるフリーライセンスも大きな特長の一つ。丸川院長も「導入前にスマートフォンでも閲覧できるという説明があり、これは『面白そうだな』と思いました」と振り返ります。
引用元:メディコム公式HP(https://www.phchd.com/jp/medicom/case-studies/ck056)
メディコムの運営会社概要
| 企業名 | ウィーメックス株式会社 |
|---|---|
| 所在地 | 東京都渋谷区渋谷3-25-18 NBF渋谷ガーデンフロント14F |
| URL | https://www.phchd.com/jp/medicom/hospitals/mcck2 |
※中小病院向け電子カルテシステムの比較表をもう一度チェックする
ミナリス
 画像引用元: ミナリス公式サイト(https://www.minaris.co.jp/)
画像引用元: ミナリス公式サイト(https://www.minaris.co.jp/)ミナリスの特徴
価格&機能がちょうどいい!電子化を今すぐ実現できる情報システムを提供
ミナリスは、中小病院向けに特化したハイブリッドクラウド情報システムです。高性能なIBM Cloudシステムを採用し、「3省4ガイドライ」に準拠した安心・安全な環境を実現。クラウドとオンプレミスのハイブリッド構成により、高パフォーマンスを維持しつつ、柔軟なシステム運用が可能です。
さらに、オールインワンの電子カルテ機能により、必要な機能を一つのパッケージに集約。追加のオプション購入は不要で、中小病院の電子化を効率的にサポートします。
ミナリスの料金プラン
公式サイトに料金プランの掲載はありませんでした。
ミナリスの導入事例
公式サイトに導入事例の掲載はありませんでした。
ミナリスの運営会社概要
| 企業名 | 株式会社ミナリス |
|---|---|
| 所在地 | 東京都渋谷区渋谷3-6-20 第5矢木ビル3F |
| URL | https://www.minaris.co.jp/ |
※中小病院向け電子カルテシステムの比較表をもう一度チェックする
HOPE Cloud Chart II
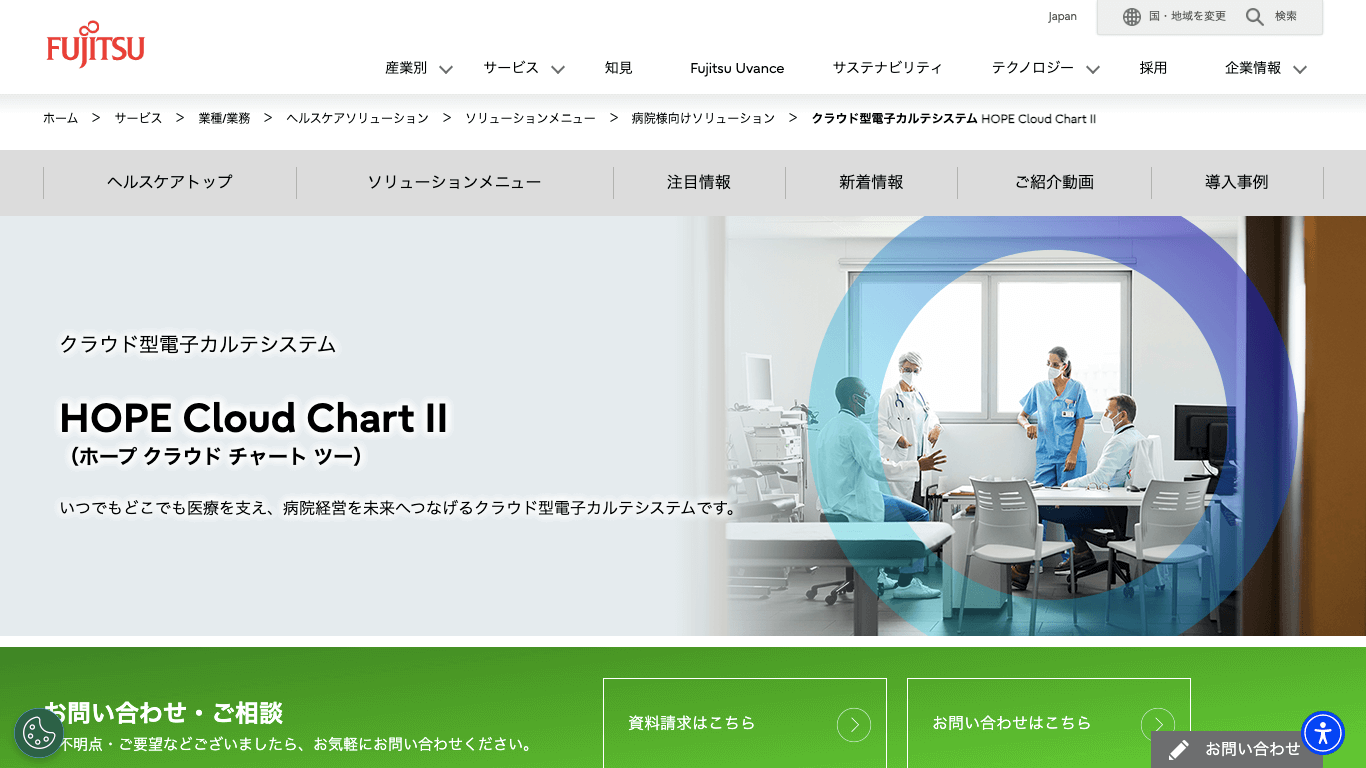 画像引用元: HOPE Cloud Chart II公式サイト(https://www.fujitsu.com/jp/solutions/industry/healthcare/products/cloudchart2/)
画像引用元: HOPE Cloud Chart II公式サイト(https://www.fujitsu.com/jp/solutions/industry/healthcare/products/cloudchart2/)HOPE Cloud Chart IIの特徴
病院経営の未来に向けた多彩なソリューションを提供!柔軟な導入オプションが魅力
HOPE Cloud Chart IIは、いつでもどこでも利用可能なクラウド型電子カルテシステムです。導入が容易で、クラウドならではの充実したアフターサービスを提供し、医療機関の手間を軽減してくれます。
また、病院の形態に応じて必要なサービスを柔軟に提供し、利用者ポータルを通じて院内ニーズに迅速に対応。さらに、業務の継続性を確保し、最新機能と教育動画の定期更新も魅力です。経営ダッシュボードを活用した管理の見える化と、クラウド技術を駆使した診療スタイルの変革を支援し、病院経営の未来へとつながるサポートが期待できます。
HOPE Cloud Chart IIの料金プラン
公式サイトに料金プランの掲載はありませんでした。
HOPE Cloud Chart IIの導入事例
看護師をはじめとした病院スタッフの方が働きやすくなりました
電子カルテの導入効果について、「医師の引き継ぎが容易になったということに加えて、業務の標準化により、看護師をはじめとした病院スタッフの方が働きやすくなりました」と語る。従来は手書きで作成していた帳票作成の手間が省けるなど、業務の効率化も進んでいるという。
引用元:HOPE Cloud Chart II公式HP(https://www.fujitsu.com/jp/group/fip/about/resources/case-studies/2019/1216/)
HOPE Cloud Chart IIの運営会社概要
| 企業名 | 富士通株式会社 |
|---|---|
| 所在地 | 神奈川県川崎市中原区上小田中4-1-1 |
| URL | https://www.fujitsu.com/ |
※中小病院向け電子カルテシステムの比較表をもう一度チェックする
AHIS
 画像引用元: AHIS公式サイト(https://ahis.aits.jp/)
画像引用元: AHIS公式サイト(https://ahis.aits.jp/)AHISの特徴
必要な機能をワンパッケージ化!システムが苦手な方にも安心の使いやすさを提供
AHISは、直感操作が可能なwebベースの電子カルテシステムです。ドラッグ&ドロップ機能により、カルテの入力がスムーズに行える使いやすいUI設計を採用。どなたでも簡単に操作しやすい点が魅力です。
中小規模病院向けに必要な全機能を統合したパッケージを提供し、医療クラウドサービスの効率の大幅な向上が期待できます
また、さまざまな標準オプションが利用可能で、日医標準レセプトORCAと連携した医事会計処理も支援。月額定額で利用でき、院内にサーバーの設置が不要なため、初期導入コストを心配する必要がありません。
AHISの料金プラン
- クリニックプラン:123,750円〜(/月)
- スタンダードプラン:233,750円〜(/月)
※すべて税込価格です
AHISの導入事例
使いやすさとコスト削減が導入の決め手!
他社製の電子カルテと比較して低コストで導入できることが魅力であり、分かりやすいインターフェースで使い勝手がよく医師の要望にもある程度柔軟に対応していただけることが選択の理由です。AHISでは外来受付のステータスを可視化する機能があり、診察室やリハビリ室や窓口など患者さんごとにステータス(診察待ち・リハビリ・会計待ちなど)を設定することで患者さんの今の状況をリアルタイムで把握することができます。
引用元:AHIS公式HP(https://ahis.aits.jp/work/case_hyogo/)
AHISの運営会社概要
| 企業名 | 株式会社エイトス |
|---|---|
| 所在地 | 香川県高松市勅使町604-4 |
| URL | https://aits.jp/ |
※中小病院向け電子カルテシステムの比較表をもう一度チェックする
モバカル
 画像引用元: モバカル公式サイト(https://movacal.net/hospital/)
画像引用元: モバカル公式サイト(https://movacal.net/hospital/)モバカルの特徴
電子カルテ × クラウド × モバイル端末が実現する院内DX化への第一歩!
モバカルは、200床未満の中小規模医療機関向けに設計されたモバイルファーストな電子カルテシステムです。高機能かつ低コストで地域医療のDX推進をサポート。直感的なUIとモバイル最適化により、スタッフの作業効率が向上が期待できます。
注射3点確認機能では、バーコードを利用して自動照合を行い、ミスリスクを低減。また、音声入力サポート機能により、ハンズフリーでの記録入力が可能です。加えて、内蔵のチャットアプリとWEB会議機能により、連絡漏れのリスクを軽減し、遠隔診療もスムーズに行える点が注目ポイントです。
モバカルの料金プラン
公式サイトに料金プランの掲載はありませんでした。
モバカルの導入事例
公式サイトに導入事例の掲載はありませんでした。
モバカルの運営会社概要
| 企業名 | NTTデバイステクノ株式会社 |
|---|---|
| 所在地 | 神奈川県横浜市神奈川区新浦島町1-1-32 アクアリアタワー横浜14階 |
| URL | https://movacal.net/hospital/ |
※中小病院向け電子カルテシステムの比較表をもう一度チェックする
Henry
 画像引用元: Henry公式サイト(https://lp.henry-app.jp/)
画像引用元: Henry公式サイト(https://lp.henry-app.jp/)Henryの特徴
外来・入院・退院まで全業務の効率化をサポート!経営レポートの自動作成も可能
Henryは、クラウド型の一体電子カルテです。外来から入院、退院までの業務を効率化が期待できる上、クラウド型なので、専用機器やサーバーの設置も必要ありません。また、病床ごとの料金が他社の半額で、追加のオプション料金や保守運用料金が不要。継続的な経費が抑えられる分、他の設備やサービスへの投資が可能です。
直感的な入力支援、タブレット対応や音声入力も可能で、どなたにも使いやすい設計を採用。自動で経営レポートも作成してくれるので、病床の稼働率や必要な報告業務を容易になるはずです。
Henryの料金プラン
公式サイトに料金プランの掲載はありませんでした。
Henryの導入事例
会計業務の効率化を実現
Henryは入力しやすい設計になっているため、診察が終了してワンクリックで会計に反映できるなど入力作業が簡素化され、会計業務の効率化につながっています。感覚値ですが、患者さん1人あたり5分くらいの短縮になっています。
引用元:Henry公式HP(https://lp.henry-app.jp/case/taiyokodomo)
Henryの運営会社概要
| 企業名 | 株式会社ヘンリー |
|---|---|
| 所在地 | 東京都品川区東五反田2-9-5 サウスウィング東五反田 3階 |
| URL | https://henry.jp/ |
※中小病院向け電子カルテシステムの比較表をもう一度チェックする
OCS Cube-Smart
 画像引用元: OCS Cube-Smart公式サイト(https://service.ryobi.co.jp/healthcare_solution/hc-cube-smart/)
画像引用元: OCS Cube-Smart公式サイト(https://service.ryobi.co.jp/healthcare_solution/hc-cube-smart/)OCS Cube-Smartの特徴
リアルタイムでの情報共有でチーム医療を支援!迅速な意思決定をサポート
OCS Cube-Smartは、クラウド型の高度な電子カルテシステムで、職種を越えた情報共有を促進し、患者の状態を迅速に把握するための4列並列の表記を採用しています。
個別の画面設定では、複数種類のオーダ入力に対応。直感的な操作へのサポートはもちろん、業務スタイルや好みに応じたカスタマイズが可能です。
また、ベッドサイドでの看護支援を提供し、効率化と残業時間の削済を実現。レセプトチェックの連動や病床利用率の可視化により、経営改善と医療の質向上を支援してくれます。
OCS Cube-Smartの料金プラン
公式サイトに料金プランの掲載はありませんでした。
OCS Cube-Smartの導入事例
複施設の患者ID番号が統合でき、利便性がアップ!
ラウド版システムの利点を生かして複数施設連携を実現。また患者ID番号を統一し、患者様にとっても1枚の共通診察券があれば上記施設どこへでも受診でき、過去の複数施設の受診履歴(カルテ、検査結果等)もその場ですぐに確認できますので、職員様にとっても業務軽減や患者サービス向上へ注力できる仕組みになっています。
引用元:OCS Cube-Smart公式HP(https://service.ryobi.co.jp/healthcare_solution/hc-cube-smart/)
OCS Cube-Smartの運営会社概要
| 企業名 | 株式会社両備システムズ |
|---|---|
| 所在地 | 記載なし |
| URL | https://service.ryobi.co.jp/healthcare_solution/hc-cube-smart/ |
※中小病院向け電子カルテシステムの比較表をもう一度チェックする
HAYATE/NEO
 画像引用元: HAYATE/NEO公式サイト(https://www.hayate-neo.jp/)
画像引用元: HAYATE/NEO公式サイト(https://www.hayate-neo.jp/)HAYATE/NEOの特徴
20年以上の導入ノウハウでシステム運用コストの削減をサポート
HAYATE/NEOは、199床以下の中小規模病院向けに特化したクラウド型電子カルテシステムです。20年以上の導入ノウハウを活かし、コストの面で躊躇していた病院にも手が届くよう設計。システムは、直感的で使いやすく、見やすい画面構成なので、診察内容をスムーズに把握できる点が利点です。
また、クラウドサービスを採用しているため、導入と運用コストの大幅削減が期待できます。さらに、定期的なバージョンアップにより最新機能の提供と安心・安全なクラウド環境の整備で、セキュリティの心配もありません。
HAYATE/NEOの料金プラン
公式サイトに料金プランの掲載はありませんでした。
HAYATE/NEOの導入事例
情報共有と交換がスムーズに!コスト面にも満足
導入し1年ほど経過すると、多くの職員から「導入して良かった」と声が上がっています。医師は紙カルテを見に行かなくても指示が出せるようになり、医療関係者の中でも間違いなく情報共有、情報交換ができるようになりました。また必要なコストもきっちりと取れるようになりましたので、コスト漏れ防止の管理ができるようになったと思います。
引用元:HAYATE/NEO公式HP(https://www.hayate-neo.jp/case/takaishikamo-hp/)
HAYATE/NEOの運営会社概要
| 企業名 | 株式会社メディサージュ |
|---|---|
| 所在地 | 大阪市中央区内平野町1丁目3番7号 |
| URL | https://www.hayate-neo.jp/ |
※中小病院向け電子カルテシステムの比較表をもう一度チェックする
ヘルス×ライフ カルテ
 画像引用元: ヘルス×ライフ カルテ公式サイト(https://karte.kinjiro-e.com/)
画像引用元: ヘルス×ライフ カルテ公式サイト(https://karte.kinjiro-e.com/)ヘルス×ライフ カルテの特徴
定額制×初期費用無料!初めてもシステム導入に最適なソリューションを提供
ヘルス×ライフ カルテは、診療所から300床までの病院向けに設計されたクラウド型電子カルテシステムです。初期導入費用は無料で、定額制により全機能が利用可能。予算が限られている中小規模の医療機関でも導入のハードルが低くなるよう設定されています。
シンプルな画面構成と早いレスポンスで直感的な操作で、カルテ情報の検索と閲覧が瞬時に行えるのも注目ポイント。院内の情報共有を容易にし、テンプレート化された文書作成機能で業務効率向上が期待できます。
また、高いセキュリティ性を確保し、アクセス制限や通信データの暗号化・ファイアウォール設置・ランサムウェア対策も実施しています。
ヘルス×ライフ カルテの料金プラン
- 初期費用:0円
- 病院向けプラン:535,000円〜(/月)
- 診療所向けプラン:19,000円〜(/月)
※税不明
ヘルス×ライフ カルテの導入事例
公式サイトに導入事例の掲載はありませんでした。
ヘルス×ライフ カルテの運営会社概要
| 企業名 | 勤次郎株式会社 |
|---|---|
| 所在地 | 東京都千代田区外神田4丁目14番1号秋葉原UDXビル南18階 |
| URL | https://karte.kinjiro-e.com/ |
※中小病院向け電子カルテシステムの比較表をもう一度チェックする
セコム・ユビキタス電子カルテ
 画像引用元: セコム・ユビキタス電子カルテ公式サイト(https://www.secom.co.jp/business/medical/ubiquitous.html)
画像引用元: セコム・ユビキタス電子カルテ公式サイト(https://www.secom.co.jp/business/medical/ubiquitous.html)セコム・ユビキタス電子カルテの特徴
ウェブベースで場所を選ばずアクセス可能!システム維持作業やコストの心配は不要
セコム・ユビキタス電子カルテは、安全性・経済性・利便性を兼ね備えたクラウド型電子カルテシステムです。PCやモバイルデバイスなどインターネット環境があれば、どこからでもアクセスでき、スムーズな診療情報の作成・保管・閲覧が可能。診療科別の収入分析など経営支援機能も備えており、医療経営の強化が期待できます。
また、通信を保証する専用ネットワークと堅牢なデータセンターを使用し、高度なセキュリティを提供。低コストでの導入が可能な上に、煩雑なシステム構築も不要です。
セコム・ユビキタス電子カルテの料金プラン
公式サイトに料金プランの掲載はありませんでした。
セコム・ユビキタス電子カルテの導入事例
公式サイトに導入事例の掲載はありませんでした。
セコム・ユビキタス電子カルテの運営会社概要
| 企業名 | セコム株式会社 |
|---|---|
| 所在地 | 東京都渋谷区神宮前1丁目5番1号 |
| URL | https://www.secom.co.jp/ |
※中小病院向け電子カルテシステムの比較表をもう一度チェックする
MI・RA・Is/AZ
 画像引用元: MI・RA・Is/AZ公式サイト(https://www.csiinc.co.jp/solution/mirais/)
画像引用元: MI・RA・Is/AZ公式サイト(https://www.csiinc.co.jp/solution/mirais/)MI・RA・Is/AZの特徴
医療の未来を担う機能を搭載!医療サービスの向上に貢献し患者満足度アップをサポート
MI・RA・Is/AZは、次世代の医療ニーズに対応したクラウドベースの電子カルテシステムです。マルチベンダー方式と標準インターフェースを採用し、さまざまな施設との接続を可能にします。また、MI・RA・Is/AZは、患者満足度と医療サービスの質を向上させ、業務効率化を図ることを目的として設計されており、医療従事者と患者の双方にとって価値ある支援の提供が期待できます。
全国900以上の医療機関からのノウハウが統合されており、医療安全と経営改善をサポートします。また、健康情報基盤への情報連携機能を備え、地域包括ケアシステムの実現を効果的に支援してくれます。
MI・RA・Is/AZの料金プラン
公式サイトに料金プランの掲載はありませんでした。
MI・RA・Is/AZの導入事例
各部署ネットワークを繋ぎ、最適な医療の提供を実現
ベンダを選定する際に3~4社程ベンダのデモを見て、その中から札幌で実績があり、サポートもしっかりしているシーエスアイ社を選定しました。「各システムとの連携がしやすい電子カルテ」という点でも、MI・RA・Isが一番優れていました。また、担当営業が足しげく当院に通ってくれたことも大きかったです。
引用元:MI・RA・Is/AZ公式HP(https://www.csiinc.co.jp/case/doto/)
MI・RA・Is/AZの運営会社概要
| 企業名 | 株式会社シーエスアイ |
|---|---|
| 所在地 | 北海道札幌市白石区平和通15丁目北1番21号 |
| URL | https://www.csiinc.co.jp/ |
※中小病院向け電子カルテシステムの比較表をもう一度チェックする
blanc
 画像引用元: blanc公式サイト(https://healthcare.jbcc.co.jp/product/blanc.html)
画像引用元: blanc公式サイト(https://healthcare.jbcc.co.jp/product/blanc.html)blancの特徴
『いつでも・どこでも・だれでも』をコンセプトとした使いやすさが魅力
blancは、一般病院や精神科病院向けに特化したクラウド型電子カルテシステムです。「いつでも・どこでも・だれでも」をコンセプトに設計されており、従来の「Ecru」と「Psyche」の機能を継承しつつ、より使いやすいレイアウトで遠隔診療や訪問医療にも対応しています。
クラウド利用により、院内サーバーの管理が不要で、システムのアップデートも自動化。サーバーの購入やIT専門スタッフの雇用といった必要がありません。また、災害に強い設計で、東西日本にデータを分散保管しているため、高い安全性と可用性が期待できます。
blancの料金プラン
公式サイトに料金プランの掲載はありませんでした。
blancの導入事例
業務効率化が実現し、より患者と向き合う時間ができた!
医師が手書きした処方箋を事務員が入力し直すというプロセスがなくなったので、業務効率が大幅に向上しました。またクラウドサービスを選択したことで※外出先や自宅でもカルテを参照できるようになり、医師の負担が軽くなっただけではなく、対応もスピードアップできています。今までは看護師が申し送りをするために紙のカルテを持ったままになっているために、医師が指示を出せないということが多々あったのですが、今ではその問題も解消されています。
引用元:blanc公式HP(https://healthcare.jbcc.co.jp/casestudy/sarufutsumura.html)
blancの運営会社概要
| 企業名 | JBCC株式会社 |
|---|---|
| 所在地 | 東京都中央区八重洲2丁目2番1号 東京ミッドタウン八重洲 八重洲セントラルタワー13階 |
| URL | https://healthcare.jbcc.co.jp/ |
※中小病院向け電子カルテシステムの比較表をもう一度チェックする
MALL
 画像引用元: MALL公式サイト(https://pcmed.jp/product-mall/)
画像引用元: MALL公式サイト(https://pcmed.jp/product-mall/)MALLの特徴
導入医療施設数200件!柔軟性と拡張性に優れたシステムをリーズナブル価格で提供
MALLは、病院専用に開発された電子カルテシステムです。20年以上で約200件の導入実績と99%の継続率を誇り、信頼性の高さが伺えます。薬剤・栄養・検査・透析などの多岐にわたる自社部門システムとの高度な連動性を持ち、150社以上の機器・システムとの互換性が特徴です。
年2回の大型アップデートを通じて、約3,000の設定項目をカスタマイズ可能で、各職種・ユーザーに合わせた柔軟な運用を支援。リーズナブルな料金設定と、導入から保守まで一貫して手厚いサポートを提供しています。
MALLの料金プラン
公式サイトに料金プランの掲載はありませんでした。
MALLの導入事例
さまざまな情報が一目瞭然に!煩雑な書類作成が楽になった
とにかく書類の作成が楽です。書類を作る際、その情報は電子カルテのあちこちに点在していますが、「MALL」は書類作成画面と同時に、これまで書いた病名やカルテの内容、SOAPを全て参照し、引用ができます。 その他、私個人では、入院セット・検査結果テスト・文書管理セットなどをタブで作って、自分の使いやすいような形で基本画面のレイアウトを変更しています。
引用元:MALL公式HP(https://pcmed.jp/cases/adachi/)
MALLの運営会社概要
| 企業名 | 株式会社パシフィックメディカル |
|---|---|
| 所在地 | 高知県宿毛市幸町5番12号 |
| URL | https://pcmed.jp/ |
※中小病院向け電子カルテシステムの比較表をもう一度チェックする
A-CHART
 画像引用元: A-CHART公式サイト(https://www.act-s.co.jp/a-chart/)
画像引用元: A-CHART公式サイト(https://www.act-s.co.jp/a-chart/)A-CHARTの特徴
万全のセキュリティ体制に加えICカードでログインできる使い勝手の良さが魅力
A-CHARTは、高度なセキュリティとユーザビリティを兼ね備えた医療用電子カルテシステムです。ICカードとパスワードの二重認証を採用しており、個々の利用者認証を強化。なりすましや不正利用の防止が期待できます。
全利用情報は、サーバーに一括保存され、必要時に詳細な利用状況の追跡が可能。院内の任意の端末からログインして作業の再開ができ、複数の端末でカルテを同時に閲覧・編集できる利便性の高さが魅力です。
また、直感的な操作が可能なユーザーインターフェースは、タブレットにも対応し、診療効率の向上をサポートしてくれます。
A-CHARTの料金プラン
公式サイトに料金プランの掲載はありませんでした。
A-CHARTの導入事例
公式サイトに導入事例の掲載はありませんでした。
A-CHARTの運営会社概要
| 企業名 | 株式会社アクトシステムズ |
|---|---|
| 所在地 | 北海道札幌市中央区北1条西20丁目1番27号 井門札幌N120ビル7F |
| URL | https://www.act-s.co.jp/ |
※中小病院向け電子カルテシステムの比較表をもう一度チェックする
医次元
 画像引用元: 医次元公式サイト(https://ijigen.jp/carte/)
画像引用元: 医次元公式サイト(https://ijigen.jp/carte/)医次元の特徴
導入コストを削減し、必要な機能を厳選!UIを重視した使い勝手優先のシステム
医次元は、医療機関の効率化と柔軟性を目指した先進的な電子カルテシステムです。一画面に患者の診療録やステータスを表示し、短時間で詳細な情報を把握が可能。全スタッフが同じ画面をリアルタイムで閲覧・更新し、迅速な情報共有を実現してくれます。
直観的な操作性により、ユーザーフレンドリーなインターフェースを提供。カスタマイズ可能なテンプレートと豊富な部門システムで、病院の個別ニーズへの対応も可能です。その他にも、カレンダー機能やさまざまな部門とのシステム連携サポートも嬉しいポイントといえます。
医次元の料金プラン
公式サイトに料金プランの掲載はありませんでした。
医次元の導入事例
公式サイトに導入事例の掲載はありませんでした。
医次元の運営会社概要
| 企業名 | 株式会社イジゲン |
|---|---|
| 所在地 | 東京都豊島区南池袋1-27-10 油木第一ビル9F |
| URL | https://ijigen.jp/carte/ |
※中小病院向け電子カルテシステムの比較表をもう一度チェックする
メディカルフォース
 画像引用元: メディカルフォース公式サイト(https://corp.medical-force.com/)
画像引用元: メディカルフォース公式サイト(https://corp.medical-force.com/)メディカルフォースの特徴
導入クリニック400院突破の話題システム!自由診療の業務と経営をワンストップで管理
メディカルフォースは、クリニックの効率化と経営の可視化を目指す統合型システムです。予約カレンダー・電子カルテ・在庫管理をシームレスに連携させ、業務の自動化と効率化を実現。患者は、直接カレンダーから予約の完結が可能で、診療情報へのアクセスも容易にできるよう導いてくれます。
また、会計時には、在庫が自動で更新され、日々の業務がシンプルかつ迅速に進行。スマホやタブレットにも対応しているので、直感的な操作性とクリアなデザインでどこからでもアクセスできる利便性の高さが魅力です。さらに、自動集計やCRM機能を備え、経営の洞察と改善への貢献が期待できます。
メディカルフォースの料金プラン
公式サイトに料金プランの掲載はありませんでした。
メディカルフォースの導入事例
予約が簡単になり患者の利便性がアップ!リピート率向上にも寄与
まず、課題だった予約が取りづらい状況が大幅に改善され、予約数が増えました。体感ですが、私以外のドクターを指名する予約が3~4割、私の指名予約が2割程度増えたと思います。受けたい施術メニューを選ぶとすぐにドクターごとの空き状況が表示されるので、「この日に施術を受けられるならこのドクターにしよう」と予約が分散して、私以外のドクターにも指名が入りやすくなったのだと感じます。
引用元:メディカルフォース公式HP(https://service.medical-force.com/case/757-2/)
メディカルフォースの運営会社概要
| 企業名 | 株式会社メディカルフォース |
|---|---|
| 所在地 | 東京都品川区東五反田1-21-13 ファーストスクエア五反田2F |
| URL | https://corp.medical-force.com/ |
※中小病院向け電子カルテシステムの比較表をもう一度チェックする
RACCO
 画像引用元: RACCO公式サイト(https://www.road.co.jp/product/racco/)
画像引用元: RACCO公式サイト(https://www.road.co.jp/product/racco/)RACCOの特徴
科目別・病床数別に使い分けが可能!カスタマイズOKで使い勝手抜群
RACCO電子カルテシリーズは、不妊治療向け・産婦人科向け・全科目向けと、対象を設定した多機能な電子カルテシステムです。無床診療所・有床診療所・中小規模病院に適応し、日医標準レセプトソフトとの連携機能を装備。Web問診・予約システム・内視鏡記録システムなどの診療支援ツールを提供し、効率的な医療業務をサポートしてくれます。
また、カスタマイズ可能なアクセサリ機能を通じて、専門的な記録や参照ニーズに応じた柔軟な画面表示が可能。コストパフォーマンスに優れた健診システム「HOTATE」も提供し、幅広い医療ニーズに対応しています。
RACCOの料金プラン
公式サイトに料金プランの掲載はありませんでした。
RACCOの導入事例
公式サイトに導入事例の掲載はありませんでした。
RACCOの運営会社概要
| 企業名 | システムロード株式会社 |
|---|---|
| 所在地 | 東京都中央区新川1-3-3 グリーンオーク茅場町 |
| URL | https://www.road.co.jp/product/racco/ |
※中小病院向け電子カルテシステムの比較表をもう一度チェックする
電子カルテとは?
電子カルテは、医療情報をデジタル化し、管理するシステムです。従来の紙のカルテを電子的に置き換え、患者の診療情報をコンピューターに記録。医療機関内で共有し、診療情報の入力・閲覧・更新が迅速に行われるようサポートしてくれます。
電子カルテの三原則
厚生労働省は、電子カルテの使用において、「真正性」「見読性」「保存性」の三つの基本原則遵守を要求しており、医療現場で効果的に機能するためには不可欠としています。 電子カルテの導入によって、患者情報の整合性・アクセス管理・データの永続性を保証し、診療情報を正確に更新・維持・管理ができると考えられます。
電子カルテの連携性
電子カルテシステムは、異なる医療機関や関連する健康管理システムとデータを共有する能力を持っています。電子カルテの使用により、患者の一貫したケアを可能にし、医療提供者間で情報が効率的に流通できるはずです。
電子カルテの基本機能と高度な機能
基本機能には、患者の病歴・診療記録・薬剤情報の記録が含まれます。高度な機能としては、臨床決定支援ツール・カスタマイズ可能なレポート生成・リアルタイムでのデータ分析ツールがあり、医療の質と効率向上が期待できます。
カスタマイズ性とユーザーインターフェース
電子カルテは、利用環境に応じてカスタマイズが可能です。各医療機関のニーズに合わせたフォーマットや、特定の専門分野に特化した設定ができ、ユーザーインターフェースも直観的に操作できるものが多く採用されています。高い利便性により、医療従事者は患者ケアに集中できる環境を実現できると考えられます。
中小病院向けに電子カルテを導入するメリット
電子カルテは、導入によって中小規模病院の業務にさまざまなメリットをもたらすと考えられます。ここでは、それぞれのメリットについて紹介します。
情報管理の最適化
電子カルテにより、患者の医療記録や診療情報がデジタル化され、検索やアクセスが容易になります。紙カルテを物理的に探す手間が省け、情報管理の効率化が期待できます。
診療プロセスの効率化
電子カルテシステムは、テンプレートや補助機能の活用により、カルテの入力や処方箋、紹介状の作成が迅速に行えるようサポートしてくれます。転記ミスの防止や異常値の早期発見に役立つアラート機能も組み込まれているものもあります。
スペースとコストの削減
ペーパーレス化により、従来の紙カルテを保管していたスペースが不要になります。さらに、クラウド型電子カルテを採用すれば、高額な初期投資や継続的なサーバー保守のコストの大幅削減が可能です。
アクセスと連携の強化
クラウド型電子カルテは、医療スタッフが院外からも診療情報にアクセスが可能。在宅医療や往診時の利便性が高められるはずです。また、他の医療システムや診療支援ツールとの連携が容易で、チーム医療や地域医療の促進に寄与すると考えられます。
データの安全性と復旧
外部サーバーに保管できると、火災や自然災害からデータを保護し、緊急時にも迅速な復元が可能になります。医療機関は、どのような事態にも迅速に対応ができ、患者情報の漏洩や損失のリスクを心配する必要がありません。
中小病院向けに電子カルテを導入するデメリット
電子カルテ導入には、メリットだけでなくデメリットについても理解しておく必要があります。ここでは、電子カルテ導入のデメリットについて紹介します。
初期設定とトレーニングの負担
電子カルテシステムの導入には、初期設定やスタッフトレーニングに時間と労力が必要です。特に、中小規模の病院では、リソースが限られているため、日常業務に影響を与える場合があります。
技術的な障壁
システムに不慣れなスタッフが多い場合、電子カルテシステムへの適応が困難である可能性が考えられます。また、システムの不具合やダウンタイムが発生した際の対応が、病院運営にストレスをもたらすケースも少なくありません。
継続的な費用
電子カルテの維持には、定期的なソフトウェア更新やサポートサービスのための継続的な費用が伴います。特に予算が限られている中小規模病院にとって、経済的な負担となるため、システム選びは、慎重にしたいものです。
中小病院向けに電子カルテの相場費用
電子カルテの費用は、オンプレミス型とクラウド型では異なります。ここでは、それぞれの費用相場を紹介します。
オンプレミス型電子カルテの費用
オンプレミス型電子カルテの導入には、サーバー設置のための初期費用として約200万円から500万円が必要です。さらに、システムの維持や更新に必要な保守費用は、月額約2万円が目安。耐用年数はおおよそ5年で、その後は新しいシステムの再購入が必要です。
クラウド型電子カルテの費用
クラウド型電子カルテでは、初期費用が大幅に削減され、約10万円から数十万円程度です。月額料金は、1万円から数万円で、システム使用料やサーバーのレンタル料が含まれます。クラウド型は、ユーザーの追加や外部機器の連携によって費用が変動する場合があります。
電子カルテの補助金について
IT導入補助金は、中小企業や小規模事業者が生産性向上のためにITツールを導入する際、経費の一部を支援する制度です。対象となるソフトウェアやサービスは、事務局の審査を経て公式サイトに登録されたもののみが補助対象。サポート費用やクラウドサービスもカバーします。
通常枠(A・B類型)
電子カルテの導入には、通常枠の補助金が活用できます。A類型とB類型に分かれており、A類型では補助率1/2以内で、補助金額は5万円以上150万円未満です。
B類型は、補助率は同じく1/2以内で、補助金額が150万円以上450万円以下に設定されています。電子カルテのソフトウェア・導入関連費用・クラウドサービス利用料(最大2年分)に適用可能ですが、ハードウェア購入費は対象外です。
デジタル化基盤導入枠
デジタル化基盤導入枠では、補助対象として会計ソフトや受発注ソフトなどがあり、電子カルテシステムに関連する機能が含まれる場合に利用できます。ソフトウェアの補助率は最高で3/4。補助上限額は50万円超で350万円以下です。また、ハードウェアに関しては、補助率1/2以内で、補助金額はPCやタブレットが10万円以下、その他機器が20万円以下に設定されています。
セキュリティ対策推進枠
サイバーセキュリティの強化を目的としたセキュリティ対策推進枠は、電子カルテシステムのセキュリティ対策を含むITツール導入に利用できます。補助率は1/2以内で、補助金額は5万円以上100万円以下です。医療機関におけるデータ保護と効率化のためにもセキュリティ対策推進枠の活用が推奨されています。
中小病院向け電子カルテシステム導入に関するよくある質問
Q1.中小病院の電子カルテの主な機能は?
中小病院向けの電子カルテシステムには、効率的な患者管理と診療支援を実現する多様な機能が組み込まれています。患者管理機能では、患者の病名・既往歴・感染症・薬品や食物アレルギー情報を詳細にプロファイリングし、アクセスを簡単にしてくれます。
外来機能
受付時にカルテを呼び出し、問診内容を記録。次回診察のスケジュール管理や他部門への予約手続きを行う機能が必要です。一部システムでは、患者自身による予約やオンライン診療機能も提供されています。
電子カルテ機能
カルテ作成のテンプレート利用、薬歴や検査結果の参照が可能。高頻度で使用する薬剤のデータを保存し、必要に応じて家族カルテも確認できるよう設計されているものがあれば利便性が高まると考えられます。
オーダー機能
薬の処方や各種医療処置、入退院管理をはじめ、リハビリや手術などのオーダーを効率的に管理します。カレンダー機能や薬品の名称検索も利用できます。
病棟機能
入院管理・看護記録・患者ケアの管理を一元化。部門機能では、検査予約の管理や実施状況を追跡し、記録や治療文書の作成が可能です。また、文書管理機能では、患者同意書やリストバンド作成などがスムーズに行え、院内の情報共有や他システムとの連携を強化。中小病院でも大規模な施設と同等のサービスを提供が可能になると考えられます。
Q2.中小病院の電子カルテの選び方とは?
中小病院の電子カルテ選定は、医療サービスの効率化と品質向上を目指す重要なプロセスです。適切なシステム選びは、医療従事者の作業負担を軽減し、患者ケアの質を向上させるために不可欠です。
選定の流れ
電子カルテを選ぶ際は、まずプロジェクトチームを組織し、医師・看護師・医療事務など各部門から意見を集めます。チームは、現場の課題を洗い出し、解決のための優先順位を決定。必要な機能を明確にできれば、適合する電子カルテの選出が可能になると考えられます。
重要な選定ポイント
効果的な運用を実現するためには、以下のポイントに着目してみるといいかもしれません。
- 操作性:直感的で使いやすいインターフェースを採用している電子カルテは、機会が苦手な方にも安心感を与えられるはずです。まずは、デモンストレーションを通じて操作性を確認し、実際の現場のニーズに合っているかを判断する必要があります。
- 標準化:地域で広く利用されている電子カルテを選ぶと、他の医療機関や薬局との情報共有がスムーズに行えると考えられます。患者の一貫したケアが可能になり、患者満足度の向上につながるはずです。
- 安定性:システムの安定性は、日常的な運用において重要です。導入前には、他の医療機関のレビューや評価を参考にし、信頼性の高い製品を選びましょう。
- 連携性:電子カルテは、効率的な医療業務の実施のためにも、他の医療システムや機器とスムーズに連携が必要であると考えられます。
電子カルテを選ぶ際は、医療機関の特定のニーズを満たしているかどうかがポイントになります。トライアル期間を利用して、実際の使用感を試すのも一つの方法で、最終的な判断材料として具体的なフィードバックが得られるかもしれません。
中小病院向け電子カルテシステムの導入を考えている方は、本ページに掲載している中小病院向け電子カルテシステムの早見表をご覧ください。
中小病院向け電子カルテシステムのまとめ
中小病院向け電子カルテは、効率的な患者管理・シームレスな情報共有・診療プロセスの最適化を実現してくれるシステムです。医師や看護師の業務負担が軽減され、患者ケアの質の向上が期待できます。また、カルテのデジタル化により、データの迅速なアクセスと正確な情報管理が可能になります。自院にあった電子カルテシステムを選んで、業務効率化と診療の質向上を目指してみませんか。
本記事は、2024年5月時点の情報をもとに作成しています。掲載各社の情報・事例をはじめコンテンツ内容は、現時点で削除および変更されている可能性があります。あらかじめご了承ください。