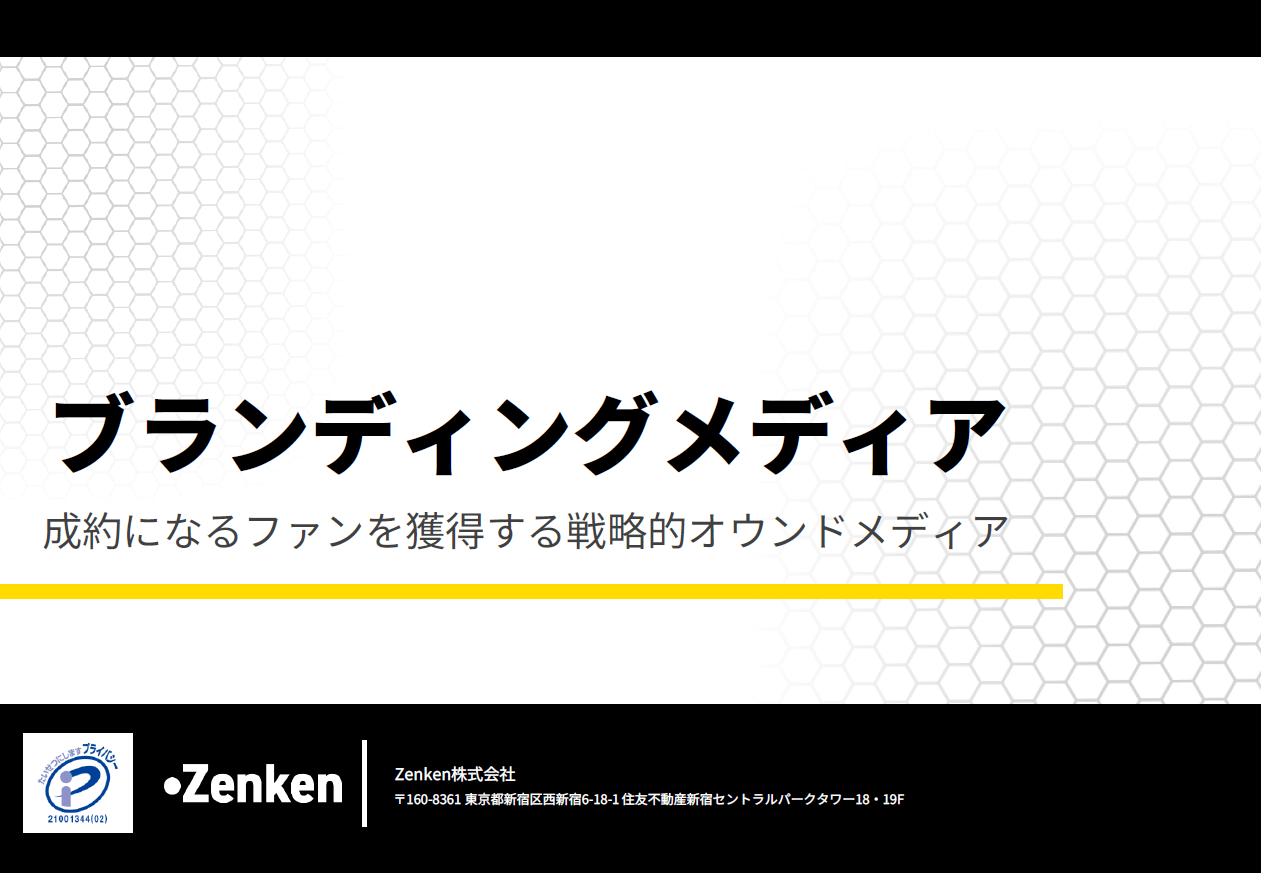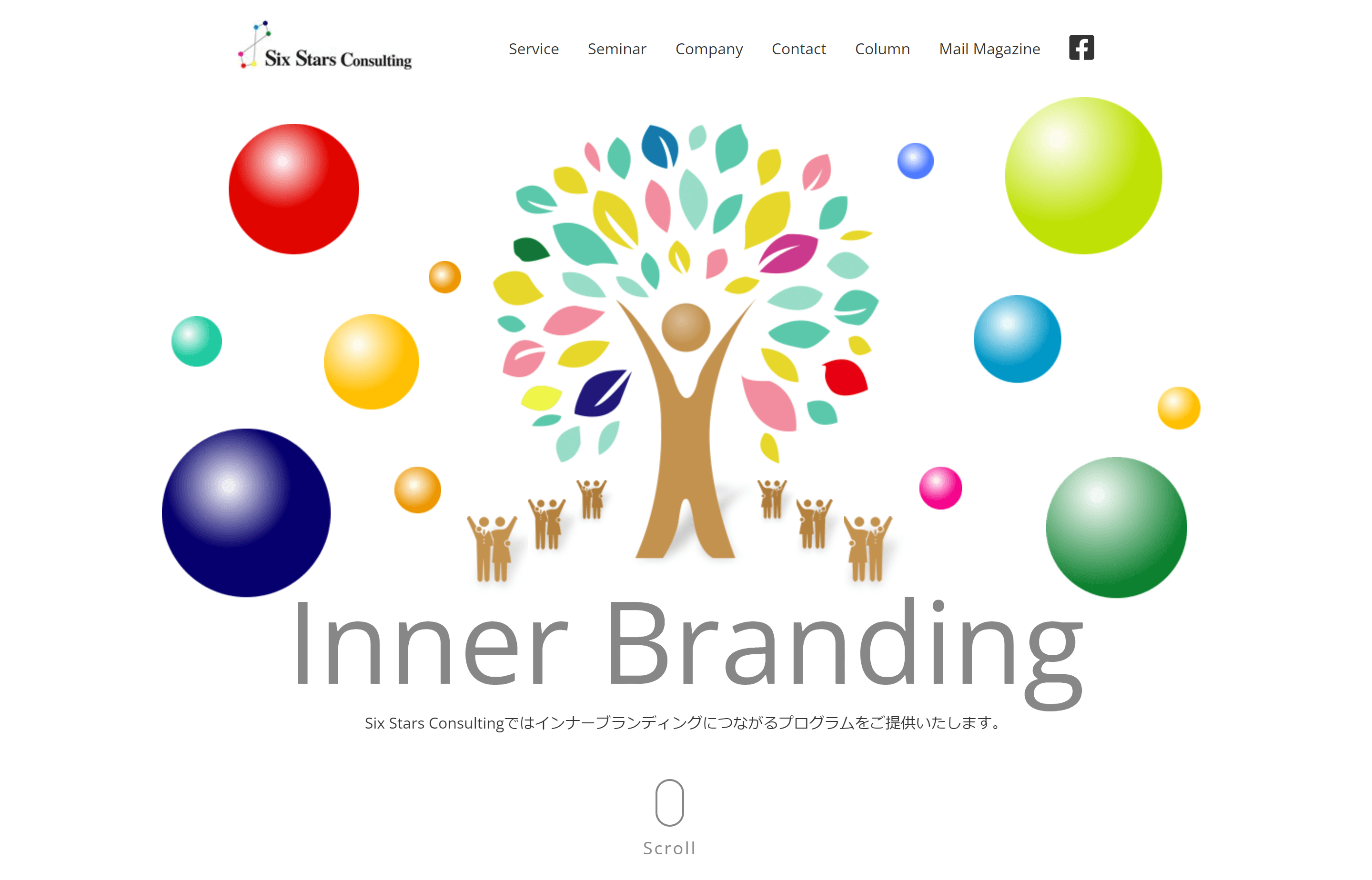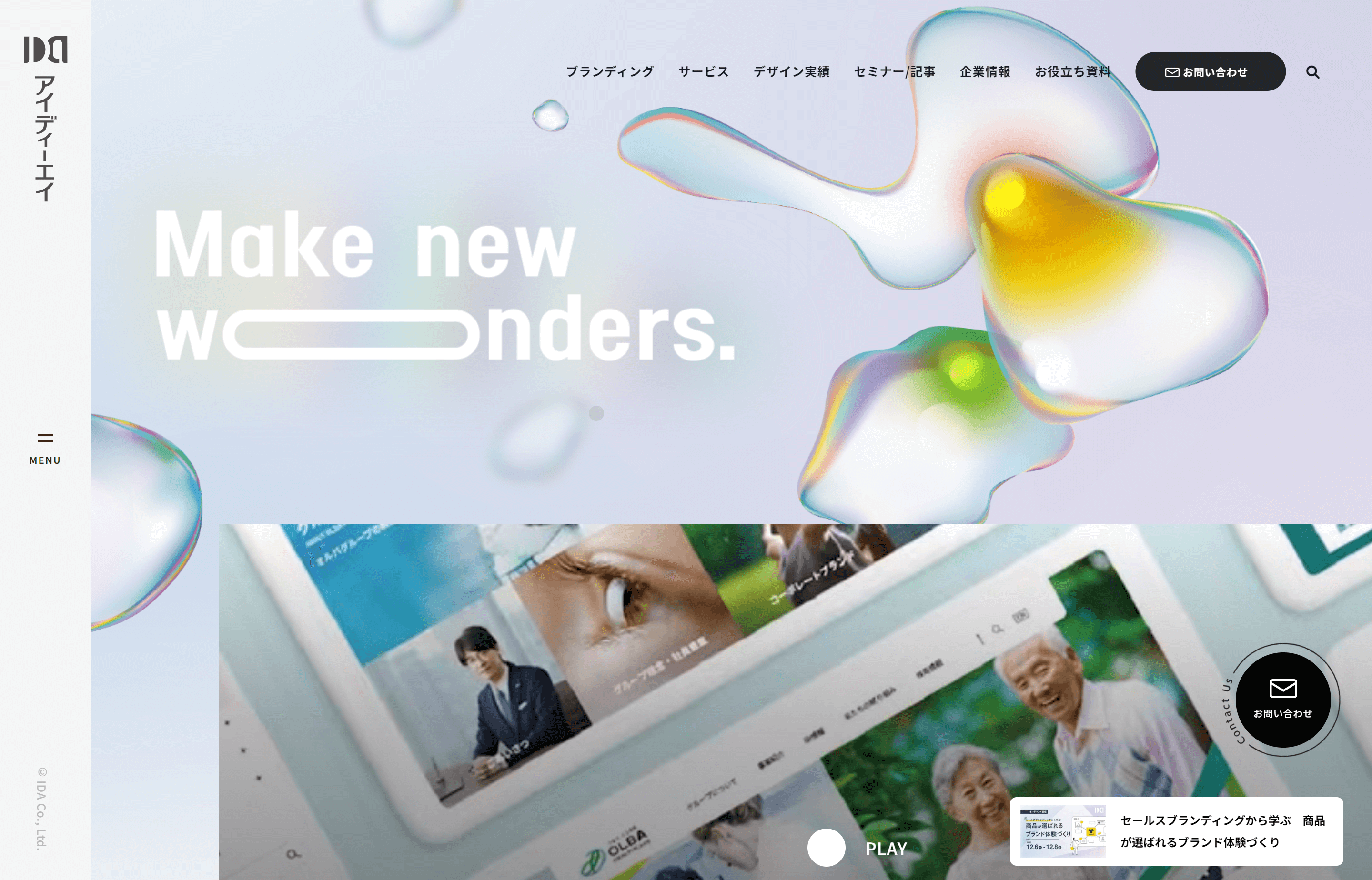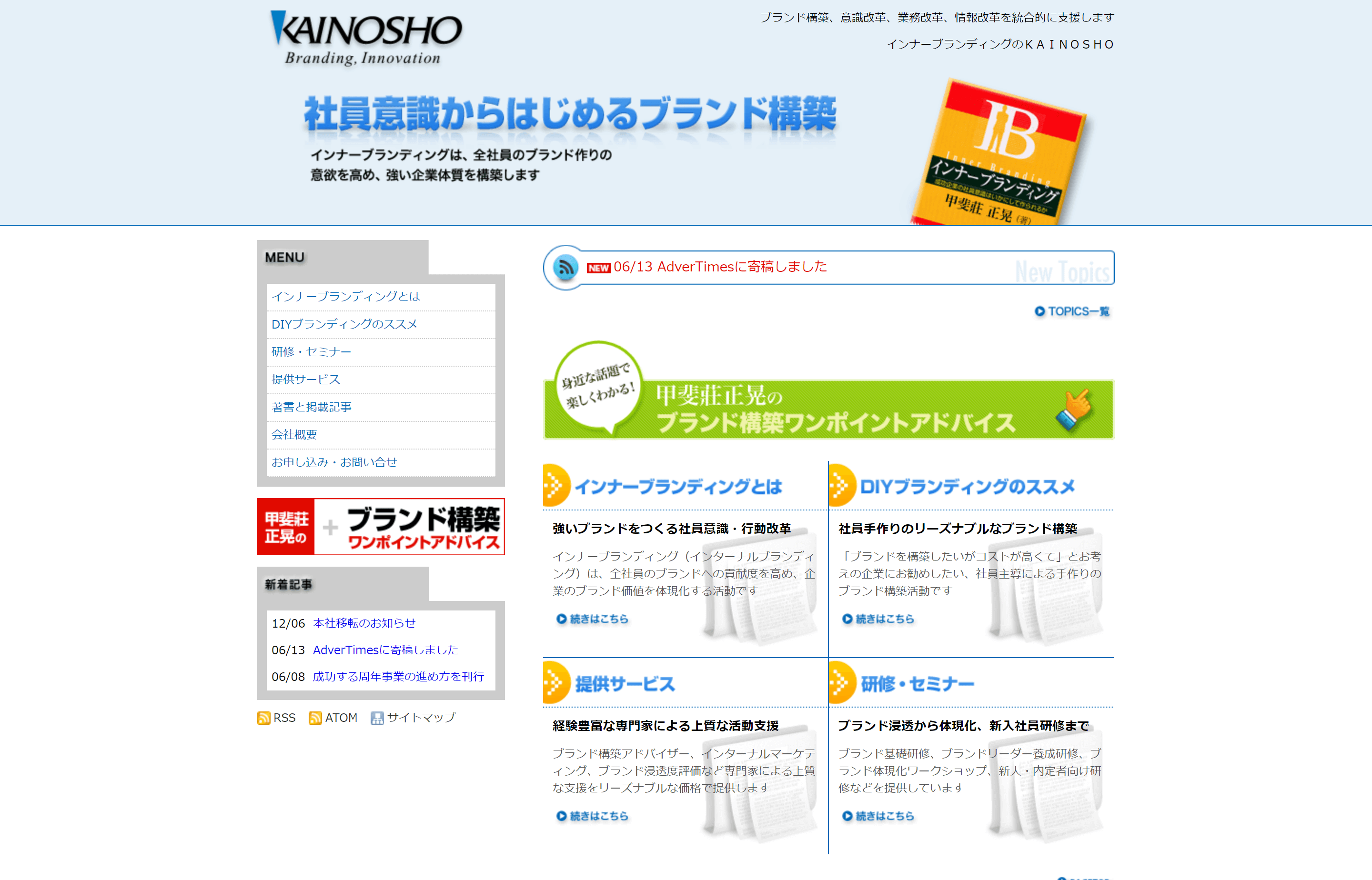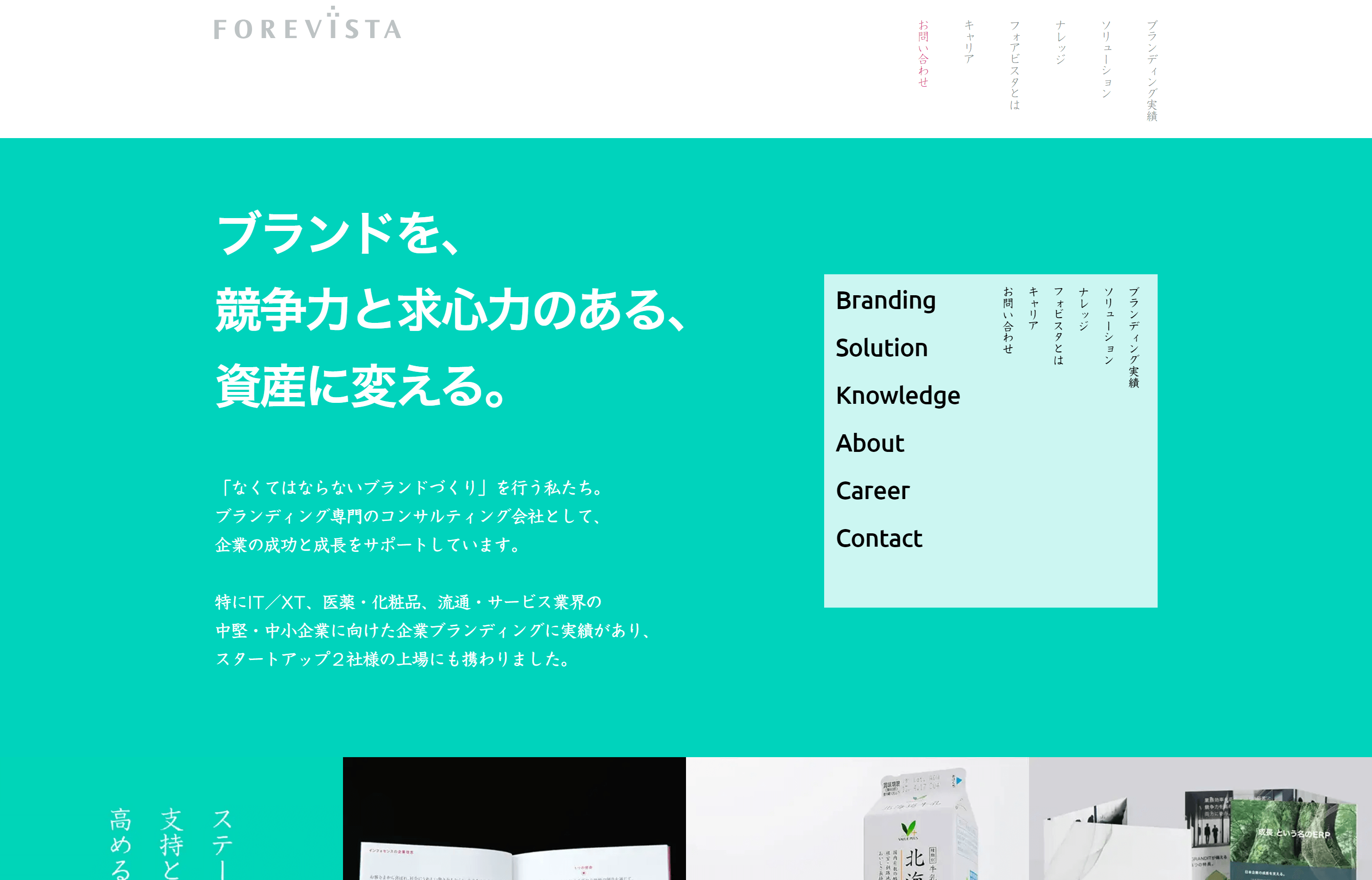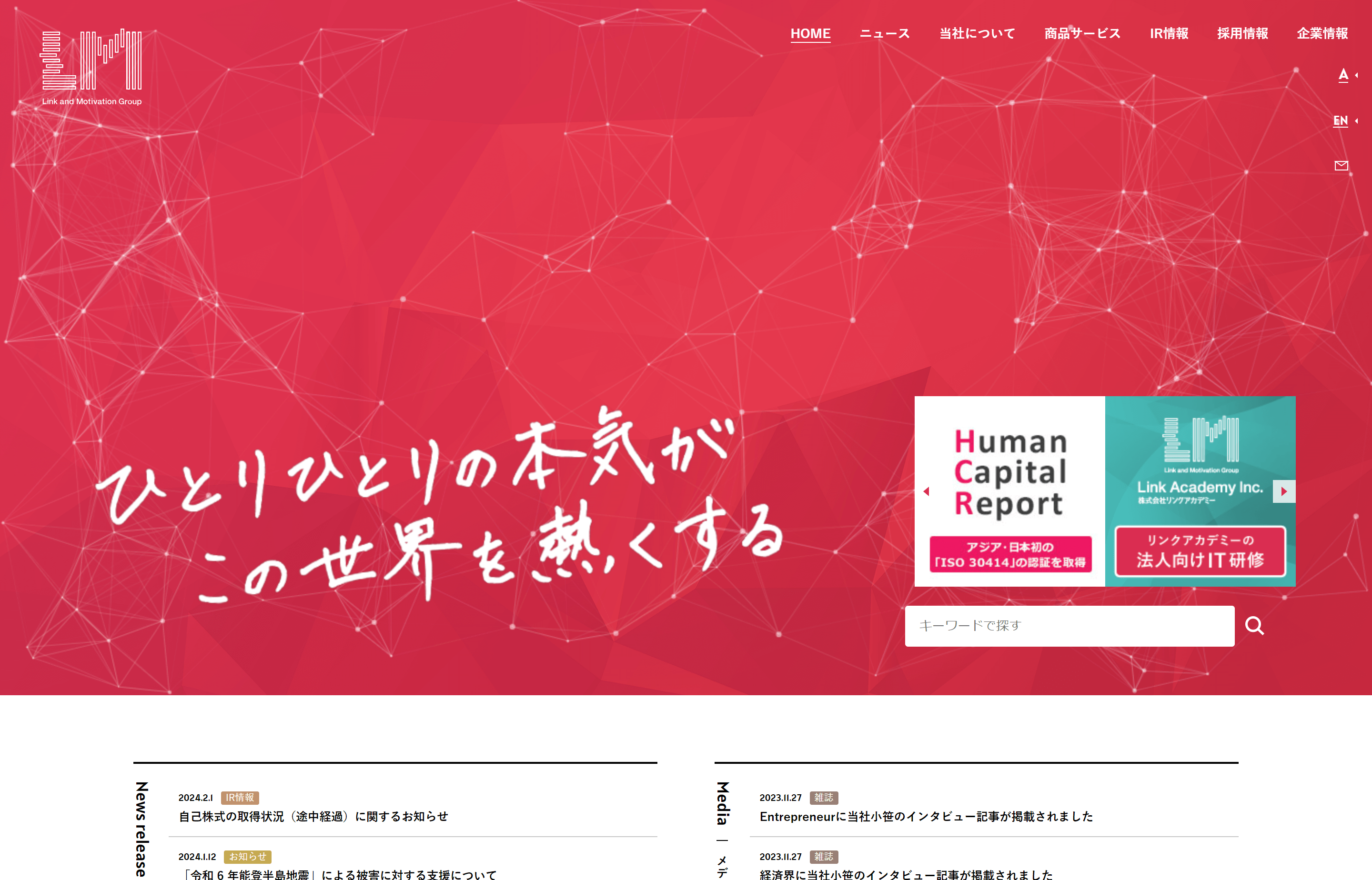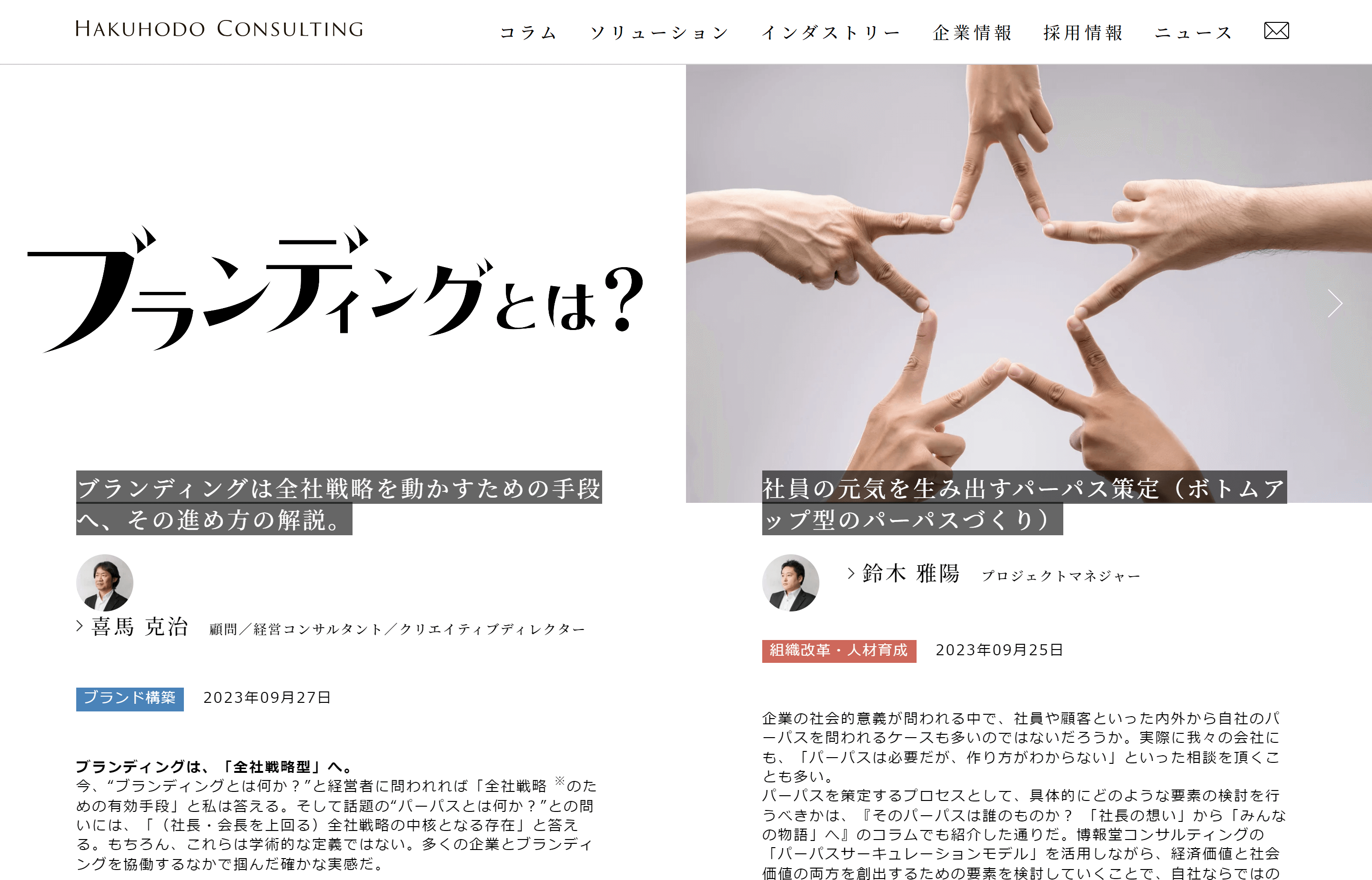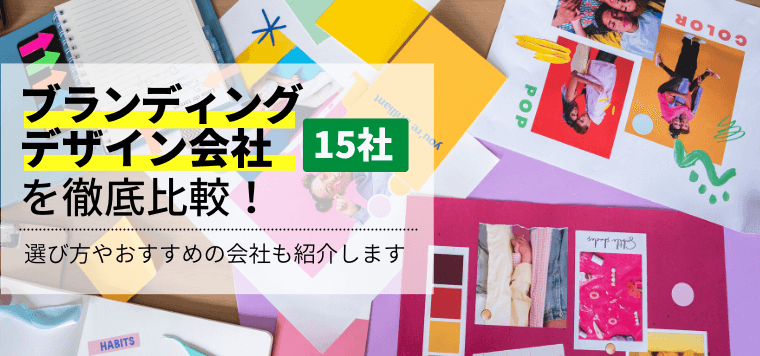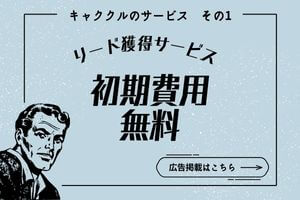ブランディングツールとは?ブランドを可視化するメディア解説
最終更新日:2024年03月19日
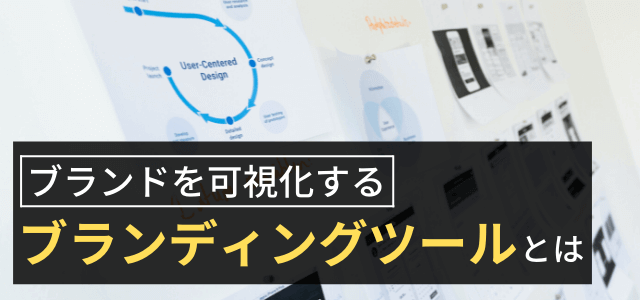
企業がブランディングを行うために活用される「ブランディングツール」。しかし、実際にどんなツールがあるか、知らない方も多いはず。
そこで本記事では、自社のブランディングを構築したい・強化したい方に向けて、ブランディングツールの種類やメリットについて解説しています。
また、ブランディングツールに加えて認知度の向上と、単価の高い成約につながるWebブランディング施策である「ブランディングメディア」についても紹介しています。
ブランディングツールとは

ブランディングツールとは、企業やお店が持つ独自の世界観や「らしさ」をブランドとして目に見える形で表現し、ユーザーに届けるための手段です。
具体的には、自社の持ち味・企業らしさ・お店らしさ・製品らしさといった価値を可視化する、メディアや広告などのを指します。
ブランディングは、企業側が提案したい価値観やアイデンティティと、ユーザーが抱くイメージをできるだけ近づけ、共感を持ってもらうために非常に大切です。また、競合他社との差別化にも欠かせない戦略ともいえるでしょう。
ブランディングを行うメリット
ブランディングを行うことで、ファンを増やすことができるなど、以下のメリットがあります。
- リピーターの増加による一定顧客数の維持
- 付加価値による増益
ブランディングすることで、「スーツを買うなら〇〇」とリピーターを増やし、新作を出しても一定の顧客数が維持できる安心感につながります。
また、たとえばスーツに撥水加工や防臭加工を施すといった、ブランディングに基づいた付加価値などをつければ、単価が上がることによる増益が期待できるでしょう。
ブランディングツールの種類

企業やお店が発信する手段として利用できる主要なブランディングツールは、以下のようなものがあります。
- マス広告
- Webサイト(オウンドメディア)
- SNS
- デジタル音声広告
- パンフレット(会社案内・ブランドブック)
- 紙袋、封筒など
それぞれ、どのようなツールでどんな効果が期待できるのかご紹介します。
マス広告
マス広告とは、マスメディアを利用した広告です。具体的には、テレビ、新聞、雑誌、ラジオといったものがこれにあたります。
ウェブ上で配信する広告に比べて、大衆にリーチしやすく、広告接触あたりの単価が抑えられるのが特徴。
また、メディア自体の知名度を利用し、「そのメディアが宣伝しているのだから信用できる情報」だと感じてもらいやすいのがメリットでしょう。
テレビ

「タイムCM」と「スポットCM」という選択肢があります。
「タイムCM」とは、放送広告とも呼ばれ、放送番組中に挟まれるCMや番組枠と一体として扱うCM、枠内で流されるCMを指します。「この番組の提供は~」というアナウンスがなされるスポンサー放送もその一つです。
その番組の視聴者層とマッチしているターゲット層に対して、CMを打つことで、より高い宣伝効果が期待できるでしょう。
「スポットCM」は、番組の間に差し込まれるCMで、最小15秒から設定できます。
「タイムCM」が、最小単位30秒で、1クール(3ヶ月)が基本の配信期間であるのに対し、短い反面、配信期間や予算配分がしやすいという特徴が「スポットCM」にはあります。
新聞

全面を使った枠や、記事下の小さい枠までさまざまなサイズを選ぶことができます。モノクロ広告だけでなく、カラー広告にして目立たせたり、モノクロでも飾りや袋文字を使用して目立たせたりといった工夫が可能。
文字、イラスト、写真などを駆使しインパクトを与える方法も、様々考えられます。
雑誌
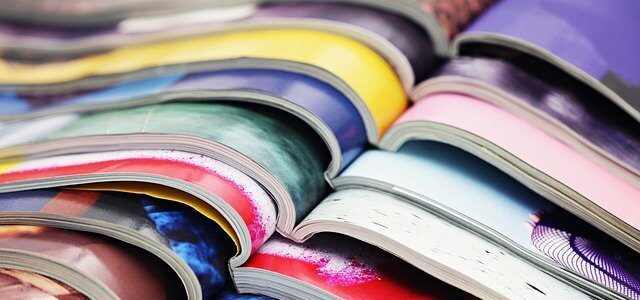
雑誌に掲載する広告は、タイアップ広告と純広告があります。タイアップ広告は、雑誌内の記事にインタビュー記事や商品を紹介するレポートを入れてもらう方法。純広告は、広告枠を買い取り、自由にデザインした広告を打っていきます。
その雑誌を読むターゲット層に応じた広告が打てるので、価値観やニーズに合致すれば興味をもってもらいやすいでしょう。
ラジオ

テレビCMと同様に、番組の合間にはさまれるコマーシャルタイプの広告です。「タイムCM」と「スポットCM」の2つがあり、地方に合わせた広告を打ち出すことで、ターゲットが絞られ、より高い効果が期待できるでしょう。
一定期間流すことで、繰り返し同じ広告を耳にするので、記憶に残りやすいというメリットもあります。
Webサイト

インターネットでの情報収集が当たり前のいま、Web上のサイト・メディアもブランディングを広めるツールとして非常に有効です。
効果を出すためには専門的なスキルやノウハウが必要になってきますが、デザインやコンテンツなどを自社の思い通りにできるため、自社のブランディングイメージを伝えやすいでしょう。
ホームページ
企業規模や業態に関わらず、自社のホームページを持つことはマーケティングや集客において必須レベル。
ホームページはいわばWeb上のパンフレットともいえますが、基本的な会社情報や製品情報を載せているだけではもったいないです。
自社の名前を知ってもらうだけではなく、提供している価値や、商品づくりで大切にしていることなどを認知してもらえるようにしましょう。
ホームページは、顧客やユーザーが自社の名前を知ったときに一度は検索して閲覧するものです。定めたブランドイメージが伝わるものになっているかチェックしてみましょう。
情報が散在してわかりにくくなっている場合は、1ページに伝えたい情報やメリットを集約したLP(ランディングページ)をつくることも有効です。
オウンドメディア
オウンドメディアとは広い意味では自社で運用しているメディアすべてを指します。ここでは狭義として、ホームページ以外に運用しているWebサイトのこととして紹介をします。
オウンドメディアはホームページとは違い、自社の社名や商品を前面には出しません。あくまでユーザーにとって有益な情報を発信することを最優先し、その上でユーザーの悩みを解決する手段として自社商品を知ってもらうという流れになります。
ユーザーニーズの解決を起点とすることで、オウンドメディアを通じ自社の信頼性が高まることはもちろん、自社の存在を知らない見込み顧客にまで知ってもらう機会をつくりだすことができます。
そしてオウンドメディアはサイト全体に統一のテーマを設定するため、企業のブランディングにも効果があるのです。
キャククルが手がけるオウンドメディアとは?
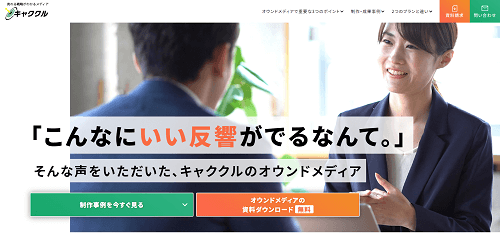
120業界・8,000サイト以上の実績があるキャククルのオウンドメディア。
認知度向上、他社との差別化、従来と異なるターゲットにアプローチしたいなど、様々な目的で制作することができます。詳しくは以下のページでご確認ください。
ポジショニングメディア
差別化をより意識したブランディングを行いたい場合は、ポジショニングメディアの制作もおすすめします。
ポジショニングメディアでは、自社がおかれている市場や業界内で、自社がどういった価値提供をしているかを競合と比較しながら見せることで、立ち位置を明確に示すことが可能です。
「△△といえば自社」というブランディングができるだけでなく、ユーザー自身がニーズにあった会社や商品を納得して選ぶことができるため、購入や申し込みへの温度感が高い状態でのお問い合わせが期待できます。
- 自社コンセプトにマッチした見込み顧客が増え、契約単価が1000万円向上した
- 商材の強みや特徴を理解した上で反響に至るため、価格競争から脱却し受注単価が2.5倍になった
- 数ある競合から自社に興味を持ってもらえるようになり、反響獲得後から契約までの期間を3分の1に短縮できた
といった成果があるWeb施策についてご興味のある方は、以下で詳しく解説しております。ぜひご確認ください。
ブランディングメディア


ブランディングメディアとは、キャククルを運営するZenkenが制作する、ブランド認知の向上と売上につながりやすい親和性のあるリード(見込み顧客)が集客ができるオウンドメディアです。
通常、ブランディングをする場合は何千万単位の制作費や広告費、そして時間を掛ける必要があります。しかしブランディングに失敗してしまえば、効果が出ず莫大な費用を失うだけでなく、間違った印象がついてしまう可能性も。
ブランディングメディアとは、親和性の高いユーザーに絞った認知度の向上を行い、ニーズが顕在化した際の第一想起されるブランドとして広めていきます。
自社のブランドを確立し
売上アップも叶える
ブランディングメディアとは?
また、購買意欲や利用意欲のあるユーザーにも同時にアプローチができます。その顕在的なユーザーにはなぜそのブランドや企業を使うべきかを解説し、さらに成約や購入につながるよう温度感を上げた集客が可能です。
ブランディングメディアを導入した結果、
- 1ケタ分受注単価が増える売上を獲得できた
- 求人広告に依存することなく、自社サイトから今までの10倍採用応募が来るようになった
というようなブランディング効果も発揮できております。下記で詳しく紹介していますので、ぜひ一度ご確認ください。
SNS
FacebookやTwitter、InstagramといったSNS(ソーシャルメディアサービス)も、ブランディングツールとして有効です。
当然のことながら、SNSのアイコンやカバー画像などは、ブランディングイメージを統一させ、タイムラインで見逃されず、目に留まりやすくすることが大切でしょう。
また、SNSごとに利用者の年齢層が異なるため、ターゲティングを変えることも欠かせません。
SNSマーケティングを専門に行う株式会社コムニコによると、Twitter利用者は20代が多いものの平均年齢は35歳、Instagramは10代、20代が半数以上、Facebookの登録者数は20代、30代が多数というデータがあります。
参照元:人気ソーシャルメディアのユーザー数(https://www.comnico.jp/we-love-social/sns-users)
Twitterは短文でリアルタイムに情報を拡散することに優れており、Instagramはビジュアル訴求を得意としています。Facebookは実名性があり、ビジネスシーンでの利用が高い点が特徴です。
それぞれのSNSのエンゲージメント率に着目し、分析することも有効です。エンゲージメント率を高めることで、より多くの人に知ってもらうきっかけにもなります。コストを抑えて行えるブランディング戦略として、SNSはぜひ活用したいものです。
ブランディングを高めるには、サービスを提供してくれる「人」が見えることも大切になってきます。文章や画像を通して、人間味を感じてもらうことやコミュニケーションを取ることも欠かせません。
SNSの投稿者=会社の代表としてコメントを返すアクションを起こすことで、よりブランドイメージを高めることができるでしょう。
デジタル音声広告


インターネット広告を使った宣伝手段として「デジタル音声広告」も注目が高まっています。
Webサイトやスマホアプリ、タブレットなどで楽しめるインターネットラジオや音楽配信サービスなどで配信される音声広告で、聴覚への訴求により認知拡大やブランディングへの効果が期待できます。
また、動画広告とは異なりスキップされにくいため、最初から最後まで聞いてもらえる完全聴取率が高いのも魅力。さらに、ユーザー情報を取得していることから、広告出稿のターゲティングを、年齢、性別、視聴コンテンツによって設定できるのも利点でしょう。
具体的なものとして、Spotify音声広告、ラジコオーディオアド、ポッドキャストオーディオアドなどがあります。
Spotify音声広告
定額音声サービスでユーザー数は世界で3.2億人。リスナーデータを利用し、年齢、性別、気分、習慣、季節的なイベントにあわせた「プレイリストカテゴリー」、音楽ジャンルを組み合わせたシーンに合わせたターゲティングができるのが魅力です。
音声広告を配信している間は、コンパニオンバナーが表示されているため、ホームページへ遷移させたり、動画配信もできたりします。
ブレイクタイムに最大30秒の音声広告を配信でき、ターゲティングできる年齢も13歳から1歳刻みと細かな設定が可能です。
ラジコオーディオアド
スマホやパソコンで無料でラジオが聴けるradiko(ラジコ)が提供する音声広告です。民放全99局が参加しており、地上波ラジオで一律広告配信する枠を利用する方法とユーザーに合わせた個別配信ができる方法があります。
ユーザーが過去に聞いた番組履歴や登録情報、位置情報などを用いて、ターゲティングを絞った配信ができるのがメリットでしょう。より高いレスポンスが期待できます。
ポッドキャストオーディオアド
ニッポン放送が配信するポッドキャスト番組に、ターゲティングした音声広告を配信できるサービスです。配信日時や位置情報、使用デバイスといったものから細かにターゲティングを行い、該当するユーザーにダイレクトにアプローチが可能。
「Apple Podcasts」「Googleポッドキャスト」「Spotify」「Amazon Music」「Castbox」など、さまざまなポッドキャストアプリで聴くことができます。
ほかにも、ニッポン放送と同様のシステムで文化放送がポッドキャストオーディオアドを配信しているものや、株式会社エフエム東京提供のラジオアプリと、パイオニアが開発した「ドライブ行動特化型デジタル音声広告」を融合させたサービスなどもあります。
パンフレット(会社案内・ブランドブック)
社会的な信用と企業が持つ魅力を十分に伝えるものとして、パンフレットも有効です。新規取引先への営業や、人材採用の場でも使用できますが、問い合わせのあったユーザーへの資料送付としてもおすすめです。
起業した想いやポリシー、社会に対する取り組みといったものを、写真なども盛り込みながら分かりやすくストーリー仕立てで伝えることで、共感してもらいやすくなるため、ブランディングツールとして役立つでしょう。
実際に、パンフレットを作り替えただけで、お客さんからの問い合わせが増えた、営業活動が楽になったといった声も多いものです。
また、ブランドブックや製品を紹介するパンフレットなども同様です。誕生秘話や製品開発の苦労話なども盛り込みながら、ブランドコンセプトや製品を通じて提供する価値観などについてユーザーに訴えかけることができます。
紙袋、封筒など
企業やお店のロゴマークなどが入った紙袋、ショッパーなども、ブランディングツールとして外せません。
スマホを購入すればキャリア名が印刷された紙袋に入れて商品を渡されます。また、洋服や靴などを購入すればその店の名前が入ったショッパーなどに入れてくれるでしょう。
これらの袋の多くはシンプルでありながら、スタイリッシュなデザインになっていることが多く、ファッションアイテムとして汎用性に優れたものも少なくありません。そのため、ユーザーは購入後も、別のものを入れる袋として利用しています。
ショッパーを普段使いすることで、ユーザーとしてはロイヤルティ向上につながることはもちろん、それを目にした人に、ブランド名や企業名などを知ってもらう機会にもつながります。
おしゃれなデザインだなと、ブランドイメージを高めた上で、何のお店なんだろうと検索してもらうことにもつながるでしょう。
ショッパーを見た見込み客にアクションを起こさせることができる意味では、コストメリットも高く宣伝効果も高いブランディングツールだと言えます。
ブランディングツールまとめ
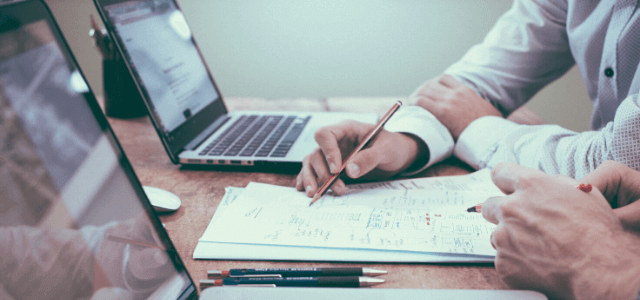
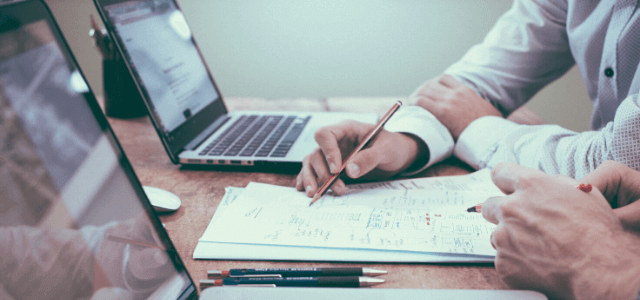
ご紹介してきたように、自社のブランドイメージをユーザーに伝える方法は様々。業種によっても、どのブランディングツールを利用するのがいいのか変わってくるでしょう。
広告宣伝に割くことができる予算なども考えながら、自社のイメージを伝えるのに最も適しているのはどの媒体なのか、はたまたどのメディアと相性がいいのかを考えながら、活用していきましょう。
複数のブランディングツールを導入する場合、大切なのはブランドイメージにブレを起こさないことです。特に、複数の会社にそれぞれ別のブランディングツールの作成を依頼した場合、統一性が取れないリスクも起こりがちです。
ブランディングや差別化にお悩みなら
キャククル運営元であるZenkenは、これまで120業種以上のWeb集客支援をしてまいりました。
特にクライアント企業の独自の強み・価値であるバリュープロポジションを軸とした、市場内でのブランディング・差別化を実現できるマーケティング戦略のご提案を得意としています。
自社だからこそできるマーケティング戦略、自社らしさを表現するブランディング戦略を進めていきたいというご要望がありましたら、ぜひお気軽にご相談ください。