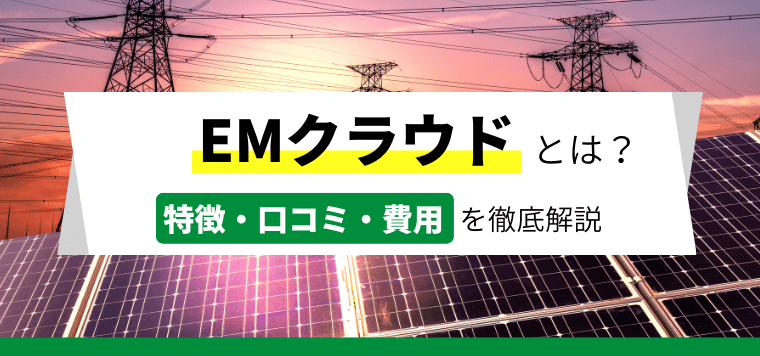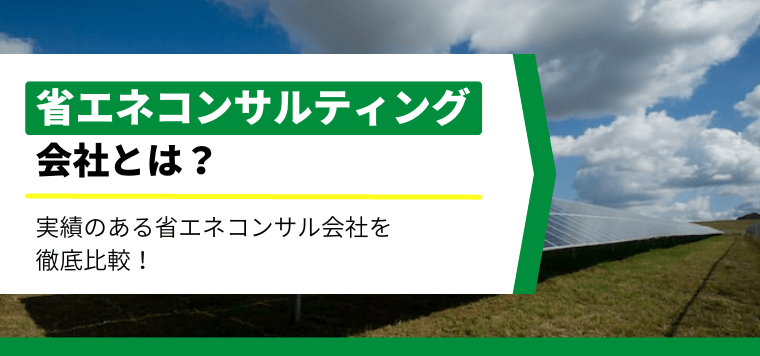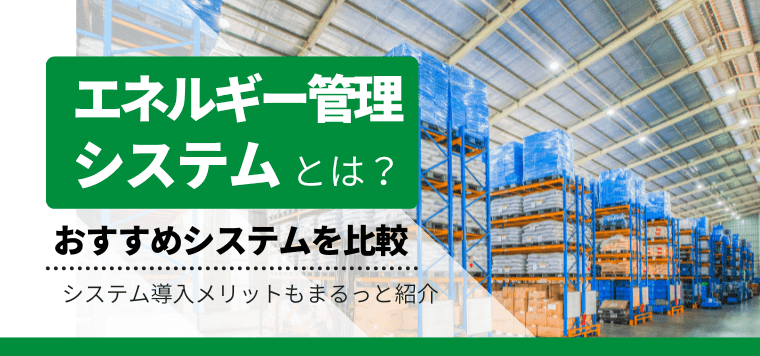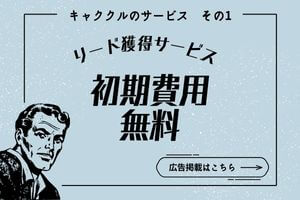CO2排出量管理ツール(システム)13選比較!見える化でコスト削減を実現
最終更新日:2024年01月22日
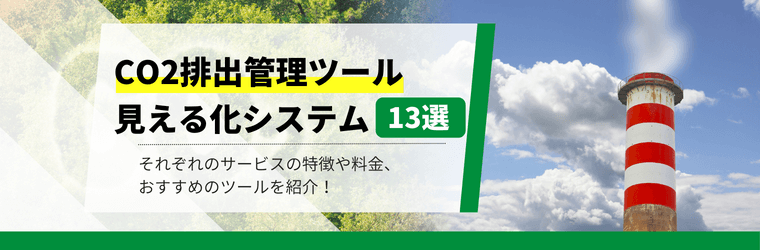
CO2排出量管理・見える化するツールの特徴を比較解説
近年、温室効果ガス(GHG)排出量の削減に向けて、日本国内でも取り組みを強化する企業が増えています。
2022年の東京証券取引所の市場区分再編においても、「プライム市場」に上場する企業には、気候変動によるリスク情報の開示が実質的に義務付けられました。「スタンダード市場」と「グロース市場」にも開示が推奨されています。
しかし、「環境データの収集から算出プロセスまで管理できる⼈材がいない…」という現状もあり、企業活動におけるGHG排出量が一元管理できるツールが求められています。
そこでこの記事では、CO2排出量管理ツール・見える化ツールを紹介します。企業のCO2排出削減の取り組みにお役立てください。
CO2排出量管理見える化ツール早見表
「CO2排出量の見える化ツール」導入をご検討中の方のために、導入可能なツールをはじめに紹介します。一口に「CO2排出量の見える化ツール」と言っても、各サプライヤーのCO2排出量まで可視化させるツールや、カーボンオフセットまで対応できるツールなど様々です。自社やサプライヤーに合ったCO2排出量見える化ツールを導入しましょう。
| ツール名 | ツールの特徴 |
|---|---|
| ScopeX(スコープエックス) | ・GHG数値算出と併せて排出量の削減施策まで提案 |
| アスゼロ | ・温室効果ガス排出量の算出ができ、レポートを自動で生成 |
| 商品炭素簿 PRODUCT EMISSIONS | ・「原材料調達」「生産」「物流/販売」など5つのフェーズで算出 |
| ReNomシリーズ | ・CO2排出量をシミュレーションが可能 |
| Ond(オンド) | ・データを自動収集しCO2排出量を自動で算定 |
| zeroboard(ゼロボード) | ・国際的な基準に沿った企業活動全体のGHG排出量を見える化 |
| C-Turtle(シータートル) | ・CO2の計測から可視化、管理や報告レポートの出力まで提供 |
| booost GX | ・プライム上場企業が選ぶ、ESG情報開示・GHG排出量算定ソリューション |
| ClassNK ZETA | ・船舶毎・航海毎のCO2排出量・CII格付けが確認できる |
| Net Zero Cloud(ネットゼロクラウド) | ・GHGプロトコルに基づいてSCOPE1~3を算出しグラフィカル表示 |
| グローバルSCMシミュレーションサービス | ・製品や部品あたりのCO2排出量まで試算 |
| EcoNiPass(エコニパス) | ・CO2排出量を自動で集計し可視化 |
| カーボンオフセットクラウド | ・商品・サービスの販売に伴う温室効果ガスの排出量を算定 |
CO2排出量見える化ツールまとめ
ScopeX(スコープエックス)

ScopeXの特徴
環境関連データの収集から算出までをワンストップで管理。社内の作業工数を減らすことができます。情報管理も内製化できるため、外部へ委託する費用をカットすることも可能です。また、CO2排出量の算出だけでなく、CO2排出量の削減施策まで提案してくれます。
ScopeXを通じて環境関連情報を可視化することで、投資家をはじめステークホルダーの信頼を勝ち取ることができ、企業価値の向上につながります。
ScopeXの料金プラン
温室効果ガス排出量算定・削減範囲に沿ってプランをお選びいただけます。
- スタータープラン…初期費用(30万円)/月額費用(5,000円)
- ベーシックブラン…初期費用(60万円)/月額費用(20,000円)
- エンタープライズプラン…初期費用(ご相談)/月額費用(ヒアリングを元にカスタマイズ)
ScopeXの導入事例
投資家に対する取り組み開示に役立っています(IT関連・CSR部⾨)
毎年投資家からの環境配慮に関する取り組み開⽰のプレッシャーはかなり上がっています。⾃社より契約しているサプライヤーに環境データの開⽰を求めた時に対応できない企業が多いため、このようなツールがあることで⾮常に助かっています。引用元:お客様の声(https://tb-m.com/scopex/casestudy.html)
ScopeXの運営会社概要
| 運営会社 | 株式会社TBM |
|---|---|
| 会社所在地 | 東京都千代田区有楽町1-2-2 東宝日比谷ビル15F |
| 資本金 | 234億2,993万円(資本準備金含む ) |
| 会社設立 | 2011年8月 | 事業内容 | 環境配慮型の素材開発及び製品の製造・販売・資源循環を促進する事業等 |
| 公式HPのURL | https://tb-m.com/ |
アスゼロ

画像引用元:アスエネ株式会社公式サイト(https://earthene.com/asuzero)
アスゼロの特徴
アスエネ株式会社では、CO2排出量の削減に向けたクラウド型ツール「アスゼロ」を提供しています。SCOPE1~3の温室効果ガス排出量の算出ができ、レポートを自動で生成します。
操作性の高いUIにより、知見がない従業員も登録から報告業務まで簡単に行えるのが特徴です。削減目標を設定し、削減手法を設定するだけでCO2排出量の算出をお任せできます。
また、ツールにはサプライチェーンデータ連携機能・API連携機能も搭載しており、企業活動の温室効果ガスの排出量を自動で見える化できます。
国際規格「Pathfinder Framework」への対応で、国際相互流通にまで活用できます。導入に向けてコンサルタントが勉強会を実施するので、操作に自信がない方も導入ハードルを下げられます。運営会社のアスエネ株式会社は初期設定・CO2排出量の見える化まで伴走でサポートします。
アスゼロのサービスの料金
公式サイト上に情報は見つかりませんでした。
アスゼロサービスの口コミ
面倒なエクセル管理から解放され、データ信頼性を向上。業務効率が圧倒的にあがりました。(導入したお客さまの声 農業より抜粋)
引用元:アスエネ株式会社公式サイト(https://earthene.com/asuzero)
アスゼロの運営会社概要
| 運営会社 | アスエネ株式会社 |
|---|---|
| 会社所在地 | 東京都港区虎ノ門1-17-1 虎ノ門ヒルズビジネスタワー15F CIC TOKYO |
| 公式HP | https://earthene.com/asuzero |
商品炭素簿 PRODUCT EMISSIONS
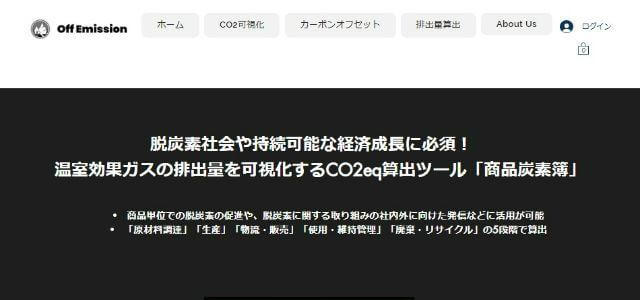
画像引用元:株式会社テックシンカー公式サイト(https://www.offemission.com/productemissions)
商品炭素簿 PRODUCT EMISSIONSの特徴
株式会社テックシンカーは、CO2eq算出ツール「商品炭素簿 PRODUCT EMISSIONS」を提供しています。「商品炭素簿 PRODUCT EMISSIONS」では、5段階に分けてCO2排出量を算出できます。
「原材料調達」「生産」「物流/販売」「使用/維持管理」「廃棄/リサイクル」の5つのフェーズで算出し、CO2排出量を見える化。領域ごとの担当者が利用できるツールで、かつ社内外への発信にも有効活用できます。
商品単位で脱炭素化に向けた取り組みができ、メタンガスなど他の温室効果ガスの排出量も含めて算出します。現場の声を拾い上げるために、カスタマイズでツールの開発が可能です。
インターフェースや操作性など、企業に合わせた仕様を提案しています。開発に際して、環境省が公表している排出原単位データベースと、海外の排出原単位データベースを採用しています。
商品炭素簿 PRODUCT EMISSIONSのサービスの料金
公式サイト上に情報は見つかりませんでした。
商品炭素簿 PRODUCT EMISSIONSの口コミ
公式サイト上に情報は見つかりませんでした。
商品炭素簿 PRODUCT EMISSIONSの運営会社概要
| 運営会社 | 株式会社テックシンカー |
|---|---|
| 会社所在地 | 東京都品川区東五反田5-25-18 7F |
| 公式HP | https://www.offemission.com/ |
ReNomシリーズ
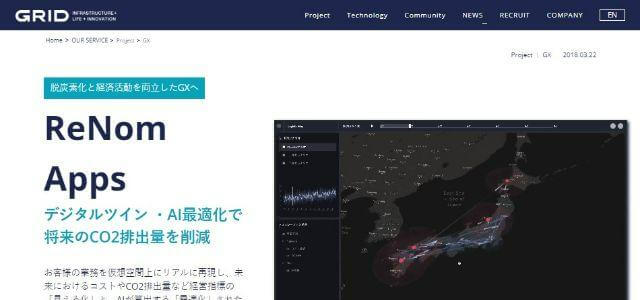
画像引用元:株式会社グリッド公式サイト(https://gridpredict.jp/our_service/gx/)
ReNomシリーズの特徴
株式会社グリッドは、CO2排出量の削減に向けたツール「ReNomシリーズ」を提供しています。ReNomSIMはシミュレーター開発フレームワークで、CO2排出量をシミュレーションが可能です。日々の業務からCO2排出量をシミュレーションでき、適した計画を立てられるようになります。
ReNom ALGOはAIがCO2削減最適化を行うアプリケーションで、燃料・消費エネルギー・原材料の最適化を目指します。AIが計画を策定するため、自動でCO2削減に向けた計画を策定できます。
他にも業務システムと連携を図るためのアプリケーションを提供しており、知見がなくとも簡単に利用できるのが特長です。ReNom GXでは、Scope1・2・3の排出量と生産コストを同時に可視化させます。
ReNomシリーズのサービスの料金
公式サイト上に情報は見つかりませんでした。
ReNomシリーズの口コミ
公式サイト上に情報は見つかりませんでした。
ReNomシリーズの運営会社概要
| 運営会社 | 株式会社グリッド |
|---|---|
| 会社所在地 | 東京都港区北⻘山3-11-7 Aoビル6F |
| 公式HP | https://gridpredict.jp/ |
Ond(オンド)

画像引用元:オンド株式会社公式サイト(https://ond.earth/)
Ondの特徴
オンド株式会社は、サプライチェーンCO2排出量自動算定ツール「Ond(オンド)」を提供しています。Scope1・2・3の算定を支援しており、TCFDのフレームワークに沿った開示も可能です。
活動量となるデータを自動で収集し、排出原単位をマッチングさせて、CO2排出量を自動で算定。GHGプロトコル準拠の算定システムで、操作が不慣れな方も算定結果を理解しやすくなっています。結果はダッシュボード化され、算出量を一目で把握できるのがポイント。
リアルタイムの排出量を算出できるほか、サプライチェーン排出量算定のコンサルティングもあわせた提供が可能です。気候変動リスクに関する相談から、経営目線でのアドバイスまで対応しています。コンサルティングでは、TCFD開示・CDP回答・SBT・RE100・LCAへの対応を支援します。
Ondのサービスの料金
公式サイト上に情報は見つかりませんでした。
Ondの口コミ
公式サイト上に情報は見つかりませんでした。
Ondの運営会社概要
| 運営会社 | オンド株式会社 |
|---|---|
| 会社所在地 | 東京都港区南青山2-2-15 |
| 公式HP | https://ond.earth/ |
zeroboard(ゼロボード)
 画像引用元:zeroboard公式サイト(https://zeroboard.jp/)
画像引用元:zeroboard公式サイト(https://zeroboard.jp/)zeroboardの特徴
zeroboardは、サプライチェーン全体のGHG排出量を算出し、製品別・サービス別に可視化。国内外のグループ会社および製造拠点の排出データを一元管理する「GHG排出量算定クラウドサービス」です。企業活動全体のGHG排出量を見える化します。
温室効果ガスの排出量算定に国際規格「ISO14064-3」に準拠しており、国際的な認証機関の算定ロジックを採用。これにより、信頼性の高いサステナビリティ情報を開示することが可能です。
また、zeroboardは2000社以上の導入実績があり、大手の金融機関、エネルギー会社、商社、地方自治体など、さまざまな業界で活用されています。膨大なGHGデータを集積し、社会の削減対策とカーボンニュートラル実現に貢献しています。
zeroboardの料金プラン
zeroboardの料金は、クライアントのニーズや拠点数に基づき決定されます。
zeroboardの導入事例
導入実績の豊富さに安心感、コミュニティによる横のつながりでの社会課題解決にも期待
システムが軽く直感的に操作できる点、カスタマーサポートがしっかりしている点は、日々操作をするうえで重要なポイントでした。
また導入実績が多く、弊社のお客様の業界にも浸透してきており調査機能を活用できそうな点、更には自社製品(エネルギーマネジメントシステム)との連携に期待ができる点も良かったです。引用元:zeroboard公式HP(https://zeroboard.jp/user/macnica)
zeroboardの運営会社概要
| 運営会社 | 株式会社ゼロボード |
|---|---|
| 会社所在地 | 東京都港区三田三丁目5-27 住友不動産三田ツインビル西館10階 |
| 公式HPのURL | https://zeroboard.jp/ |
C-Turtle(シータートル)

画像引用元:株式会社エヌ・ティ・ティ・データ公式サイト(https://www.nttdata.com/jp/ja/lineup/c-turtle/)
株式会社エヌ・ティ・ティ・データの特徴
株式会社エヌ・ティ・ティ・データは、温室効果ガス排出量可視化プラットフォーム「C-Turtle™(シータートル)」を提供している会社です。総排出量配分方式を用いて温室効果ガス排出量を算出します。
サプライヤーの排出量を、売上高に占める企業との取引額で配分する方式を採用。従来の排出量の算定方法では掴みにくかった各社の排出量の実態を把握でき、整合的な算定ができるようになりました。
Scope1・2・3のGHG排出量を可視化でき、他社の削減努力を自社の排出量へ反映できるため、削減アクションを算定しやすくなっています。サプライヤー別排出原単位はNTTデータにて算出し、プラットフォーム上で管理しています。
クラウドサービスなので取り入れやすく、誰でも利用しやすい操作画面により、スピード感を持って導入が可能です。
C-Turtleの料金
公式サイト上に情報は見つかりませんでした。
C-Turtleの口コミ
公式サイト上に情報は見つかりませんでした。
C-Turtleの運営会社概要
| 運営会社 | 株式会社エヌ・ティ・ティ・データ |
|---|---|
| 会社所在地 | 東京都江東区豊洲3-3-3 豊洲センタービル |
| 公式HP | https://www.nttdata.com/jp/ja/ |
booost GX

画像引用元:booost technologies株式会社公式サイト(https://booost-tech.com/solutions/bsc/gx/)
booost GXの特徴
booost technologies株式会社は、CO2排出量管理・炭素会計プラットフォーム「booost GX」を展開している会社です。CO2の計測から可視化、管理や報告レポートの出力までまとめて提供しており、算出工程を簡略化できます。
国際規格である「ISO27001(ISMS)認証」を取得しているので、セキュリティ対策が万全です。IPアドレスによるアクセス制限も可能で、アクセス可能な機能を絞り込めるようになっています。
また、クラウド型のシステムのため、自社サーバーが不要で導入の手間を省けるのも特長。スマホからのアクセスにも対応しており、どこからでもCO2排出量を管理できます。
企業の要望や予算に応じて、エンタープライズ・スタンダードプレミアム・スタンダード・ライトの4つのプランから提案。エンタープライズプランでは、RE100報告書・TCFD報告書・SBT報告書の作成を支援する機能も搭載しています。
booost GXの料金
公式サイト上に情報は見つかりませんでした。
booost GXの口コミ
公式サイト上に情報は見つかりませんでした。
booost GXの運営会社概要
| 運営会社 | booost technologies株式会社 |
|---|---|
| 会社所在地 | 東京都品川区大崎1-6-4 新大崎勧業ビルディング10F |
| 公式HP | https://booost-tech.com/ |
ClassNK ZETA

画像引用元:一般財団法人 日本海事協会公式サイト(https://www.classnk.or.jp/hp/ja/info_service/ghg/nk-zeta.html)
ClassNK ZETAの特徴
一般財団法人 日本海事協会は、CO2排出量把握のためのGHG排出マネジメントツール「ClassNK ZETA」を提供しています。4つの機能を搭載しており、「Vessel Monitoring」では船舶毎・航海毎のCO2排出量・CII格付けを確認できます。
「Fleet Monitoring」は、担当フリートごとのCO2排出量・CII格付けを把握できる機能。「Simulation」は、減速運航・使用燃料の変更・省エネ付加物を設置した際のCO2排出量やCII格付けの変化をシミュレーションできる機能です。
最後に、「Periodical Report機能」では、CO2排出量のレポート出力が行えるので、ステークホルダーへの説明資料としても役立ちます。船舶管理会社などによるデータ利用許諾により、船主・オペレーターの利用も可能になります。船舶からのGHG排出をマネジメントに向いているツールです。
ClassNK ZETAの料金
公式サイト上に情報は見つかりませんでした。
ClassNK ZETAの口コミ
公式サイト上に情報は見つかりませんでした。
ClassNK ZETAの運営団体概要
| 運営団体 | 一般財団法人 日本海事協会 |
|---|---|
| 会社所在地 | 東京都千代田区紀尾井町4-7 |
| 公式HP | https://www.classnk.or.jp/hp/ja/index.html |
Net Zero Cloud(ネットゼロクラウド)
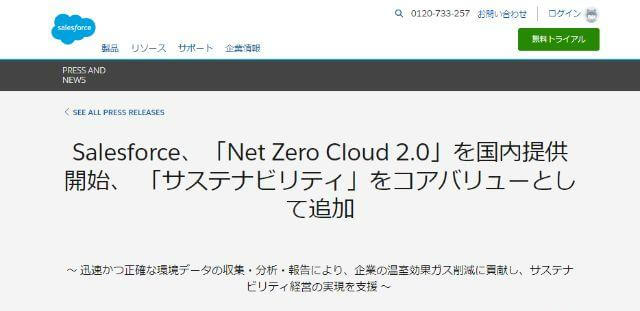
画像引用元:株式会社セールスフォース・ジャパン公式サイト(https://www.salesforce.com/jp/company/news-press/press-releases/2022/03/220309/)
Net Zero Cloudの特徴
株式会社セールスフォース・ジャパンは、温室効果ガス排出量削減に向けたツール「Net Zero Cloud」を展開しています。
国際基準のGHGプロトコルに基づいてSCOPE1~3を算出し、グラフィカル表示。温室効果ガスの排出量から再生可能エネルギー利用率、サプライチェーン排出量にいたるまでダッシュボードで確認を行えます。
また、What-if分析と科学的根拠に基づき、温室効果ガス排出量を予測分析し、目標達成へのシミュレーションを行います。科学的根拠に基づき排出量削減目標を策定し、進捗を測定することが可能です。
サプライチェーン排出量の管理にとどまらず、廃棄物データもまとめて管理できるようになっています。価格は組織単位で設定されており、従業員の炭素コストへの理解を深めるきっかけになるでしょう。
Net Zero Cloudの料金
年間633.6万円(税込)、Growthは組織単位で年間2,772万円(税込)
Net Zero Cloudの口コミ
公式サイト上に情報は見つかりませんでした。
Net Zero Cloudの運営会社概要
| 運営会社 | 株式会社セールスフォース・ジャパン |
|---|---|
| 会社所在地 | 東京都千代田区丸の内1-1-3 日本生命丸の内ガーデンタワー |
| 公式HP | https://www.salesforce.com/jp/ |
グローバルSCMシミュレーションサービス

画像引用元:株式会社日立ソリューションズ公式サイト(https://www.hitachi-solutions.co.jp/)
グローバルSCMシミュレーションサービスの特徴
株式会社日立ソリューションズは、CO2排出量を試算できるクラウド型ツール「グローバルSCMシミュレーションサービス」を提供しています。利益やコストを提供できるサービスの機能の一つにCO2排出量のシミュレーションが付いており、製品や部品あたりのCO2排出量まで試算できます。
事前入力したサプライチェーンのマスター情報から数理最適化により算出し、サプライチェーン全体のCO2排出量を可視化。マスター項目として設定できるのは、原料生産にかかるCO2排出量と炭素税、輸送時のCO2排出量・製造時の排出量・サプライチェーンの制約条件のCO2排出量です。
将来計画のCO2排出量をシミュレーションできるため、取り組み前に評価できる体制が整います。カーボンフットプリントの試算にも対応しており、工場単位から製品単位のCO2排出量の把握に役立ちます。消費者向けの資料としても活用できるので、事業継続に向けて支援も行えるのが魅力です。
グローバルSCMシミュレーションサービスの料金
公式サイト上に情報は見つかりませんでした。
グローバルSCMシミュレーションサービスの口コミ
公式サイト上に情報は見つかりませんでした。
グローバルSCMシミュレーションサービスの運営会社概要
| 運営会社 | 株式会社日立ソリューションズ |
|---|---|
| 会社所在地 | 東京都品川区東品川4-12-7 |
| 公式HP | https://www.hitachi-solutions.co.jp/ |
EcoNiPass(エコニパス)

画像引用元:ウイングアーク1st株式会社公式サイト(https://www.wingarc.com/index.html)
EcoNiPassの特徴
CO2排出量可視化プラットフォームサービス「EcoNiPass(エコニパス)」を提供するウイングアーク1st株式会社。CO2排出量を自動で集計し可視化します。現状把握に繋げて、CO2削減の施策の検討を支援。1次~3次サプライヤーで共通して使用すると、各社のCO2排出量を自動で連携するので、報告・集計の手間を省けます。
また、EcoNiPassは、初期費用ゼロで利用できる点も魅力。月額料金のみで安く導入できるので、各社サプライヤーを含めて導入しやすくなっています。
EcoNiPassの料金
サプライヤー月額1,650円相当(税込)
メーカー月額5,280円相当(税込)
※利用料金は利用開始月翌月末の一括支払いです。上記は月額換算の費用を表記しているのでご注意ください。
EcoNiPassの口コミ
公式サイト上に情報は見つかりませんでした。
企業概要
| EcoNiPassの運営会社 | ウイングアーク1st株式会社 |
|---|---|
| 会社所在地 | 東京都港区六本木3-2-1 六本木グランドタワー |
| 公式HP | https://www.wingarc.com/index.html |
カーボンオフセットクラウド

画像引用元:Sustineri株式会社公式サイト(https://sustineri.co.jp/service/ghgcalcuration/)
カーボンオフセットクラウドの特徴
Sustineri株式会社は、商品・サービスの販売に伴う温室効果ガスの排出量を算定できるツール「カーボンオフセットクラウド」を提供している会社です。
また、商品・サービスの販売に伴う温室効果ガスの排出量を、クラウド上で算定できる「GHG算定クラウド」もあわせてサービスを展開しています。
カーボンオフセットクラウドは、商品・サービスを販売するWebサイトに数行コードを書くだけでGHGを算定。同量のGHG削減クレジット・再生可能エネルギー証書を購入して、GHG排出を相殺します。リアルタイムで実行ができ、排出した温室効果ガスの埋め合わせができます。
対して、GHG算定クラウドでは、商品・サービスを販売するWebサイトにコードを書き、GHGを算出と表示に特化したサービスを提供。販売する商品が環境へ与える影響を可視化させることで、サスティナビリティの観点で差別化が図れます。
カーボンオフセットクラウドの料金
公式サイト上に情報は見つかりませんでした。
カーボンオフセットクラウドの口コミ
公式サイト上に情報は見つかりませんでした。
カーボンオフセットクラウドの運営会社概要
| 運営会社 | Sustineri株式会社 |
|---|---|
| 会社所在地 | 東京都渋谷区神宮前6-23-4 桑野ビル2F |
| 公式HP | https://sustineri.co.jp/ |
e-dash

画像引用元:e-dash公式サイト(https://e-dash.io/)
e-dashの特徴
e-dashはCO2排出量削減する企業をトータルサポートするCO2排出量管理ツール。
エネルギーの最適化、CO2削減、コスト削減、電気やガスの請求書の集約など、ツールで脱炭素化を支援しています。
カーボンニュートラルは企業の目標や取り組み内容を、対外的に報告するケースがしばしばありますが、e-dashはそこもフォロー。
目標設定やロードマップ作成、報告対応、対外公表を手厚くサポートしてくれます。
CO2排出量管理ツールのプランについては、拠点数に応じて月額1万円~(税抜)。
まずは1拠点から始めたいと考えている企業におすすめです。
e-dashの料金
拠点数に応じて月額1万円〜(税抜)スタートできます。
その他にもオプションが様々ありますので、詳しくは問い合わせてみてください。
e-dashの口コミ
公式サイト上に情報は見つかりませんでした。
e-dashの運営会社概要
| 運営会社 | e-dash株式会社 |
|---|---|
| 会社所在地 | 東京都千代田区大手町1-2-1 Otemachi Oneタワー6階 WORK STYLING内 |
| 公式HP | https://e-dash.io/ |
CO2排出量管理システムのメリット
業務効率化による時間短縮
CO2排出量管理システムを利用することで、数値をExcel入力するなどの煩雑な作業から解放され、CO2排出量を自動計算することができます。また、データを自動収集し、活動量と排出単位をマッチングしてCO2排出量をリアルタイムで自動算定するシステムもあります。これにより、業務効率を改善することができます。
サプライチェーン全体の可視化による効果的な削減
CO2排出量管理システムによって、企業のサプライチェーン全体のCO2排出量を可視化できるようになります。そのため、企業は自社だけでなく、サプライチェーン全体を通したCO2削減に取り組むことができ、より効果的な削減が可能となります。
全員参加型の脱炭素活動による社会的貢献
CO2排出量管理システムの導入によって、企業は従業員や関連企業、顧客など、広範なステークホルダーを巻き込んだ脱炭素活動の展開が可能になります。
このような全員参加型のアプローチは、単なる経済合理性だけではなく、企業が社会的責任を果たすことにつながるでしょう。また、顧客にもCO2削減の取り組みをPRすることで、企業イメージ向上につながることも期待できます。
削減目標設定・進捗管理による施策実行の支援
CO2排出量管理システムで算出したデータをもとに、システム上で削減目標を設定し、進捗管理ができるようになります。CO2排出量と生産指標を分析することで、より効率的にCO2の削減につながる施策を打ち出すことも可能です。
また、削減目標の設定や、削減に向けた具体的なアクションプランを提案してもらえるサービスもあります。これにより、CO2削減に向けた取り組みを具体化することができるでしょう。
専門的なコンサルティングによる現実的な目標設定
CO2排出量管理システムの中には、専門的なコンサルタントが、現実的で実現可能な削減目標設定を支援してくれるサービスもあります。業界トレンドや最新技術を把握し、組織の状況に合わせた最適な戦略提供から目標設定のプロセス、実行までのサポートが期待できます。
CO2排出管理・見える化が注目されている背景

近年、多くの企業でCO2削減、脱炭素経営が注目されています。温室効果ガスの排出を抑えるために、企業は石油・石炭といった化石燃料への依存を防ぐ取り組みが世界各国で行われています。
温室効果ガスが増えると地球表面の温度が上がり、多くの生物にとって住みにくい環境となり、持続可能な企業を目指すことが難しくなる恐れも。持続的な経営を目指すためにも、世界各国が一丸となって取り組む必要があるのです。
脱炭素の取り組みが活発化した背景には、2015年12月に採択されたパリ協定が挙げられます。パリ協定では、産業革命前からの平均気温上昇を1.5~2℃未満への抑制が目標として掲げられました。
日本も例外ではなく、政府は2050年までに温室効果ガスの排出量と吸収量を均衡させる「カーボンニュートラル」の達成を目標に掲げています。
2015に国連に採択され、近年ビジネス界隈で注目されているSDGsにも「脱炭素化」も含まれていることから、今後もCO2排出削減に取り組む企業は増えると予想されます。
CO2排出量見える化
ツールを提供する会社の
早見表をチェックする
CO2排出量管理ツールの開発や導入が進んでいる
脱炭素に向けた取り組みが活発になり、CO2排出量管理ツールの開発や導入が急ピッチで進められています。CO2排出量の削減と一口に言っても、削減した量を数値化しないと取り組みの是非がハッキリと分かりません。
そこで、具体的な削減量・削減率を設定できる「CO2排出量管理ツール」に注目が集まっています。
企業でCO2排出量を算出するには手間も時間もかかるため、知見がなくとも直ぐに算出できるCO2排出量管理ツールを導入したいところです。
CO2排出削減に注目した経営のメリット

ここからは、企業がCO2排出削減に取り組むメリットとを紹介します。導入後のイメージを掴んだうえで、「CO2排出量管理ツール」を比較検討してみてください。
企業がCO2排出削減に取り組むメリット
CO2排出削減に企業が取り組むメリットは、大きく分けて3つあります。
- 取り組みを通して、企業の認知度や好感度が上げられる
- エネルギーコストが削減できる
- 補助金などの支援を受けやすくなる
脱炭素を含むSDGsに取り組むことで、社会への責任を果たす企業として好意的に受け止めてもらえます。また、CO2排出量を削減する取り組みは、エネルギー消費を抑えられるのでコスト削減にも繋がります。
さらに、脱炭素経営を促進するために、日本政府が毎年様々な施策を実施しているため、タイミングによっては補助金が受けられる可能性があります。
エネルギーコスト削減に繋がる機器の購入費用・設置費用の一部を補助してもらえるので、脱炭素経営に取り組む際のハードルを下げられます。
2022年度は「エネルギー対策特別会計予算 補助金・委託費等事業」が実施されており、設備費用の一部を補助しています。CO2排出量削減に取り組む企業は、ぜひ各種補助金をご活用ください。
※参照元:環境省|令和4年度(2022年度)エネルギー対策特別会計予算 補助金・委託費等事業(事業概要)(https://www.env.go.jp/earth/42021.html)
CO2排出量管理ツール導入でよくある質問

Q1.CO2排出量管理するにはどのようなツールがありますか?
CO2排出量管理ツールは、基本的に企業活動における排出量を見える化(数値化)しますが、中にはどのように削減すべきか施策も提案してくれるツールもあります。
どのようなツールがあるのか早く知りたい方は「CO2排出量管理見える化ツール早見表」をご一読ください。
Q2.CO2排出量管理ツールの導入メリットは何ですか?
脱炭素を含むSDGsに取り組むことで、社会への責任を果たす企業として好意的に受け止めてもらえます。また、CO2排出量を削減する取り組みは、エネルギー消費を抑えられるのでコスト削減にも繋がります。
さらに、脱炭素経営を促進するために、日本政府が毎年様々な施策を実施しているため、タイミングによっては補助金が受けられる可能性があります。さらに詳しく知りたい方は、「企業がCO2排出削減に取り組むメリット」をご覧ください。
本記事のまとめ
脱炭素で、会社のエネルギーコスト削減のほか、「SDGsを推進する企業」として自社のブランディングも図れます。
その近道として、CO2排出量の算出や管理があるのですが、知識や技術ゼロの状態からスタートするのはなかなか現実的とは言えません。ツールを開発し、カーボンオフセットについてのノウハウをもっている企業に頼るのも有効な手段です。
本記事でピックアップした企業を参考にいただき、ツール導入にお役立てください。
本記事は、2023年7月時点の情報をもとに作成しています。掲載各社の情報・事例をはじめコンテンツ内容は、現時点で削除および変更されている可能性があります。あらかじめご了承ください。