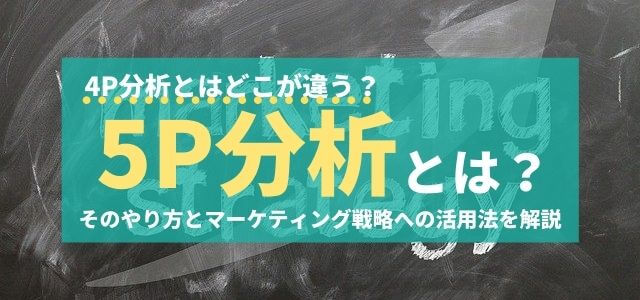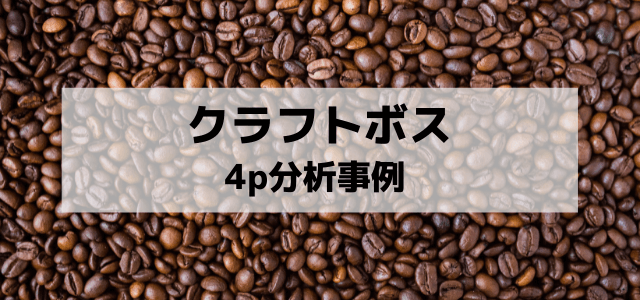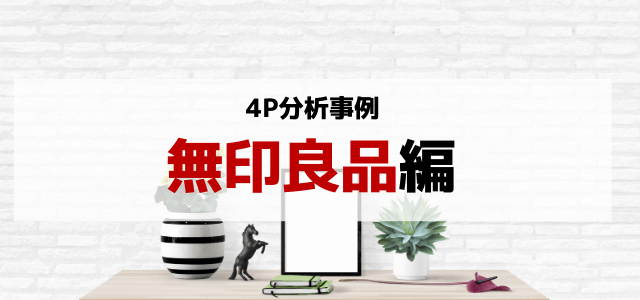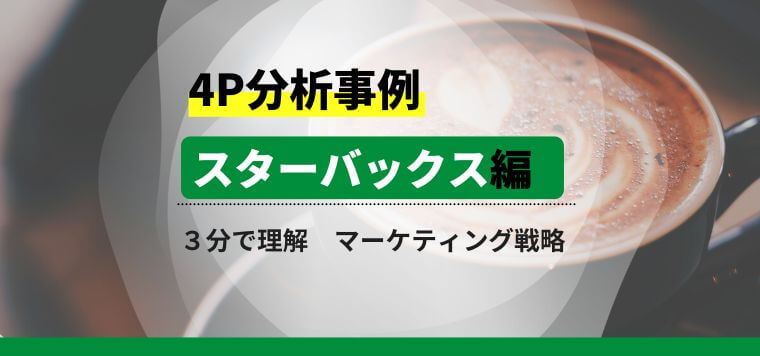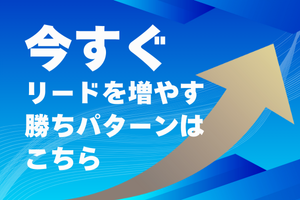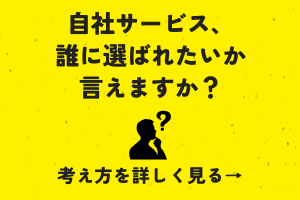【3分で理解】4P分析とは?事例から学ぶマーケティング戦略立案のヒント
最終更新日:2025年05月09日
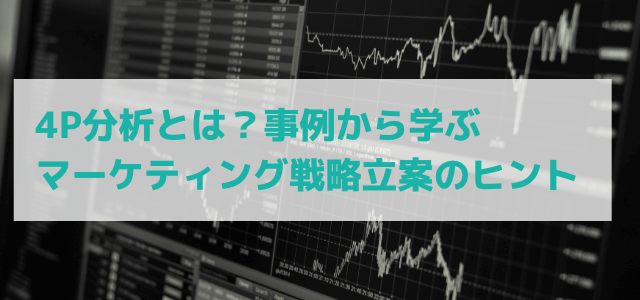
この記事では、自社のマーケティング戦略の明確化に役立つ「4P分析」とその事例について解説していきます。
なお、4P分析はあくまでもマーケティング戦略を策定する一連の流れの一部で、ターゲット顧客や競合環境などが把握できた後で行う作業です。自社のマーケティング戦略を全体的に見直したいという方には、自社・顧客・競合を整理していく「3C分析」から始めることをおすすめします。
競合にはない、自社だけの強みをどの顧客にアピールすべきかを明確にしてからマーケティングミックスを決める4P分析を行うことで、一貫性のある戦略ができやすくなります。
下記のページには4P分析が記入するだけで簡単に進められるテンプレートも用意しておりますので、ぜひ活用してみてください。
「4P分析」の成功事例からわかること
「4P分析」や「4C分析」などのマーケティング用語で検索をすると、さまざまなメディアが取り上げており、マーケティングの基本であることが分かります。
「4P分析」について、フレームワークのアウトラインと成功事例、解説しているメディアについてご紹介します。
そもそも「4P分析」とは

理解をしている方も多いかもしれませんが、4Pを簡単に解説します。4Pとは販売する側から分析するフレームワークで下記4つを分析することです。
- Product(商品・サービス)
- Price(価格)
- Place(流通)
- Promotion(販促)
4P分析はマーケティングミックスで利用される
4Pはマーケティングミックスでよく使われます。ターゲットやポジショニングの戦略を決めてから、消費者が行動してもらうように仕掛けるために複数のフレームワークを使い考えるのがマーケティングミックスです。
4Pは市場やポジショニングを調査した上で活きる
マーケティングで4Pは欠かすことができません。しかし4Pだけを分析すればよいというのではありません。
マーケティング戦略を大きく分けると下記があります。
- リサーチ
- 市場細分化
- ターゲティング
- ポジショニング
- マーケティングミックス
- 施策の実行
マーケティングミックスは施策の検討段階にあたります。
2、3、4を総合してSTP分析と呼びますが、STP分析ができている状態で初めて活きてくるのが4Pです。プレジデントオンラインでも下記のように記載されています。
戦略は、4Pの前に策定されていなければならない。市場をグループ分けして自社に合った市場を探し(セグメンテーション Segmentation)、どの市場を狙うのか絞り込み(ターゲティング Targeting)、その市場で他社と差別化を図るためのコンセプトを決める(ポジショニング Positioning)。この手法は、それぞれのプロセスの頭文字をとって「STP」と呼ばれる。経営学者フィリップ・コトラーが提唱した、マーケティングの代表的な手法の一つだ。このSTPがあってはじめて4Pがトップ逆転の有効な手段になりうるのである。
引用元:PRESIDENT Online(https://president.jp/articles/-/7533?page=1)
「4P分析」と「4C分析」の違い
4P分析と4C分析は似ている言葉ですが、主な違いは提供側の目線か、消費者側からの目線で考えるかという点です。
分かりやすい部分として飲食店のPrice(価格)で考えてみましょう。お店側としては利益をだせる価格設定を考えるのが当然です。しかし、4Pの消費者側の目線で考えると、1,000円以内で食べられる、商圏内で最安値など値段に対する視点が変わってきます。
このように顧客側の視点で考えるのが4C分析です。マーケティングミックスにおいては4P分析だけではなく4Cと合わせて分析する必要があります。
「4P分析」と「3C分析」の違い
3C分析は、競合他社と市場(顧客)と自社の立ち位置を把握する分析手法です。
3C分析の3Cは
- Customer:ターゲット顧客や市場
- Competitor:競合他社
- Company:自社
の頭文字を指しており、自社を取り巻く競争環境を把握できるような構成になっています。
4P分析は、3C分析後にどのような
- Price:料金
- Place:流通
- Product:製品
- Promotion:流通
を組むかを考える手法であるため、3C分析で自社はどんな売り方をしていくかあらかじめ決められなければ4Pを決めることは難しいと言えるでしょう。
4P分析の具体的な進め方:7つのステップ
効果的な4P分析を行うためには、以下のステップで進めることが推奨されます。
ステップ1:ターゲット市場と顧客の明確化
まず、誰に対して製品・サービスを提供するのか、その顧客層のニーズや特徴を明確に定義します。ペルソナ設定も有効です。
ステップ2:Product(製品・サービス)戦略の検討
顧客に提供する製品やサービスの価値、品質、デザイン、ブランド、バリエーションなどを詳細に分析・定義します。
ステップ3:Price(価格)戦略の検討
製品・サービスの価格設定方針を決定します。コスト、顧客の価値認識、競合価格などを考慮し、最適な価格帯を見つけます。
ステップ4:Place(流通・チャネル)戦略の検討
顧客が製品・サービスをどこで、どのようにして入手できるようにするかを計画します。オンライン、オフラインのチャネル、物流体制などを検討します。
ステップ5:Promotion(販促)戦略の検討
製品・サービスの存在や魅力をターゲット顧客にどのように伝え、購買を促進するかを計画します。広告、広報、販売促進、人的販売などの手法を組み合わせます。
ステップ6:4P間の一貫性の確認と調整
上記4つのPが相互に矛盾なく、一貫したメッセージを発信し、戦略目標達成に貢献するように調整します。例えば、高級製品を高価格で、限定されたチャネルで、品格あるプロモーションで展開するなどです。
ヒント: 各Pの要素を一覧表にし、それぞれの関連性やターゲット顧客へのメッセージが一貫しているか客観的に評価してみましょう。
ステップ7:定期的な見直しと改善
市場環境や顧客ニーズの変化、競合の動向に合わせて、4P戦略を定期的に見直し、必要に応じて改善を行います。これにより、マーケティング戦略の陳腐化を防ぎ、持続的な成果を目指します。
「4P分析」の事例としてメディアに取り上げられたもの
4P分析で事例として、メディアによく取り上げられる商品やサービスを見てみましょう。
スターバックス
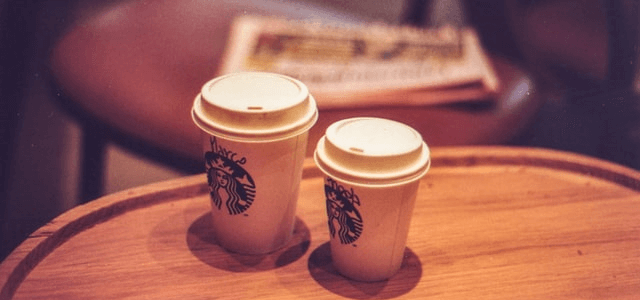
シアトルで生まれ、現在では日本でもカフェといえば思い浮かべる方も多いほど広がったチェーン店。
【成功ポイント】
特に注目するべきは、海外企業でありながらも日本に合わせたProduct部分です。
スターバックスの製品は国によって商品の種類やサイズが異なります。
例えば一番小さいショートサイズは日本人に合わせて独自に作られたサイズで、海外にはありません。抹茶に関連する商品も提供されていますがこれも日本独自で、各国の文化に合わせているのです。
■Price
ホテル内にて提供されている喫茶店や、コーヒー専門店よりも安い価格が設定されています。しかしファーストフード店よりは高く設定されており、ある程度高価格帯のコーヒーを楽しむ人をターゲットとしています。
■Promotion
プロモーション方法として、CMなどの広告は打たずに口コミで広めると言う戦略をとりました。店舗のコンセプトとしては、家と職場以外に落ち着ける場所というものです。
■Place
日本でも高級な立地とされている銀座に最初の店舗をオープンしています。立地がよいなかで安い価格で提供されているというブランディングに成功しています。
ヘルシア緑茶

画像引用元:花王株式会社公式サイト(https://www.kao.co.jp/healthya/)
花王から販売されているヘルシア緑茶は、花王が販売した初めての飲料商品であり、健康飲料としての新しい市場を開拓したといえます。
【成功ポイント】
ポイントはProductでお茶を選んだこと、Placeでコンビニを選んだ部分にあります。
花王は従来からの研究で茶カテキンに体脂肪の効果があることを知っていました。当初は何を開発するかまでは決まっておらず、茶カテキンを多く使い普段の生活で無理なく続けられるものとして製品検討を進める上でお茶が選ばれています。
さらに味も苦すぎると継続が難しいため、お茶飲料として飲める程度の味にしています。
■Price
通常の緑茶よりも高い価格で設定することにより、他の緑茶とは異なる効果の期待が大きくなることにつながりました。
■Promotion
特定機能食品の表示許可を取得していることで、効果があることの説得力をもたせています。当時他に特定機能食品の表示許可を取得しているお茶はありませんでした。
■Place
元々花王は飲料水を販売しておらず自動販売機の流通はもっていないため、発売当初はコンビニのみの販売を選んでいます。健康機能食品を販売するのであればドラッグストアなどが向いているとも思えますが、日々とり続けるためには仕事で忙しい方でも購入しやすいコンビニが適していたのです。
またコンビニでは基本的に定価で販売されるため、他のお茶とは違うというイメージアップにもつながっています。
ドモホルンリンクル
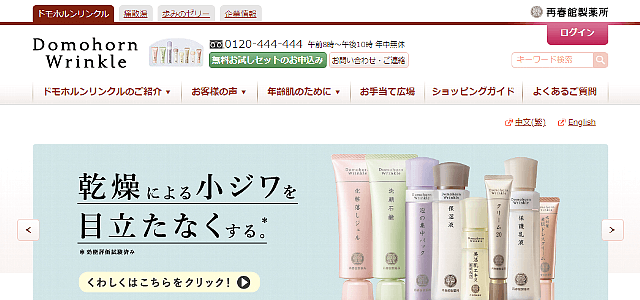
画像引用元:株式会社再春館製薬所ドモホルンリンクル公式サイト(https://www.saishunkan.co.jp/domo/)
ドモホルンリンクルはインターネット通販が当たり前ではない時代から、実店舗をほぼもっていない状態で売り上げをあげていることに成功している化粧品です。
【成功ポイント】
二段階のPromotion、通販に絞ったPlaceに売り上げを高めている秘密があります。
ドモホルンリンクルは年齢が高めの女性に対して、肌の悩みを解決するという化粧品です。
■Price
1ヶ月ほどで利用できるセットが約3万円と、高価格帯。高くて良質な化粧品というイメージを与えています。
■Promotion
基本的に店舗をもたないドモホルンリンクルのプロモーションは大きく2段階に別れています。まずはテレビや新聞などさまざまな媒体で広告を展開し、商品の知名度を上げるという点です。そして興味をもった方が電話をした際にオペレーターが顧客の悩みに寄り添って商品の提案をしてくれます。
■Place
電話での営業が中心のためコールセンターの問い合わせ窓口は午前8時から午後10時までと長い時間で、休みもありません。
さらに発信元電話番号から判断し利用期間に応じて対応するオペレーターを分けています。
ひとつの電話番号にかけるシステムではあるものの、初回購入の顧客と何度も購入している顧客はそれぞれ最適なスキルをもった担当者へつながるシステムで、待たせる時間を減らしています。
ユニクロ

ファストファッションを提供するアパレルショップとして大きな知名度をもっているユニクロ。
【成功ポイント】
なんといってもPrice部分が重要視されますが、ただ安いブランドだけで終わらなかったのは考えられた戦略が活きています。
製品は手頃な価格でありながら高品質なファッションを提供。特に普段着に力を入れています。
■Price
ユニクロといえば低価格というイメージをもっている方ばかりでしょう。材料調達や生産などを自社でおこなうことで商品のコスト削減に成功しています。
展開方法として新しいブランディングを打ち出して定番商品となった後、商品を絞り込むという戦略も低価格で提供できる大きなポイントです。
しかしユニクロの価格で注目するべき点は、他社の価格競争に巻き込まれないようにするためさらに低価格のブランドとしてGUをつくったことです。
「ユニクロは安物」というイメージにならないようにし、良質なファッションとしての印象を残すため他の低価格ブランドと競争しない位置で提供しています。
■Promotion
広告展開をする際にはシーズンごとにもっとも売り出したい商品を絞り込んで宣伝しています。TVのCMではモデルの動きがあるものが多く、「動きやすさ」を印象づける広告です。
■Place
全国で多くのユニクロの店舗に加え、ECサイトでも販売をおこなっています。また日本よりも海外の店舗数のほうが多く、世界的にも良質なファッションとしてブランディングに成功しています。
ライザップ
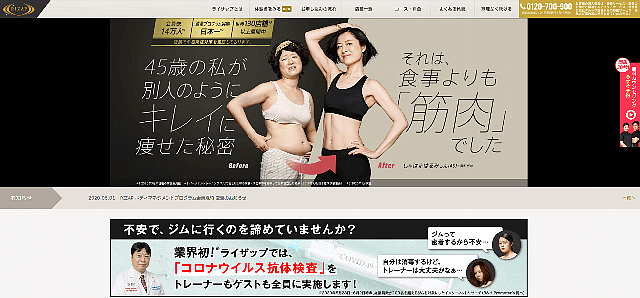
画像引用元:RIZAP株式会社公式サイト(https://www.rizap.jp/6/)
パーソナルトレーニングのフィットネスとしてライザップの名前を知らない人はほとんどいないでしょう。
【成功ポイント】
Productの食事チェックやPromotionのインパクトが注目するべきポイントです。
マンツーマンのパーソナルトレーニングが提供するサービス。他にもパーソナルトレーニングを提供するジムやフィットネスはありますが、ライザップの特徴は食事指導も合わせている点です。体を作る栄養の元になる食事は理想の体づくりには欠かせません。
何を食べるとよいか程度のアドバイスなら他のジムでも受けることはありますが、ライザップでは食事を全てチェックしてアドバイスをおこなうこともサービスの一貫としています。
■Price
もっとも安いコースでも298,000円、コースによっては1,000,000円を超えるほどフィットネスの講師としては高価格帯です。
■Promotion
TVCMで、トレーニングを受ける前後で比較する広告を展開。ダイエット前後のプロポーションを比較するのはよくある広告手法ですが、多くの有名人を起用していることでインパクトを感じやすい特徴をもっています。
■Place
動画などではなくライザップのジムに直接来てもらいトレーニングサービスを提供。かつチャットで食事の状況など日々コミュニケーションをとっています。
自身のメディアを4P分析している事例
4Pの理解を深める場合に、理論だけでなく上記のような事例で考えると分かりやすいです。さらにより分かりやすい事例としてひとつのメディアをご紹介します。
4P分析が具体例で分かりやすい事例:さくマガ
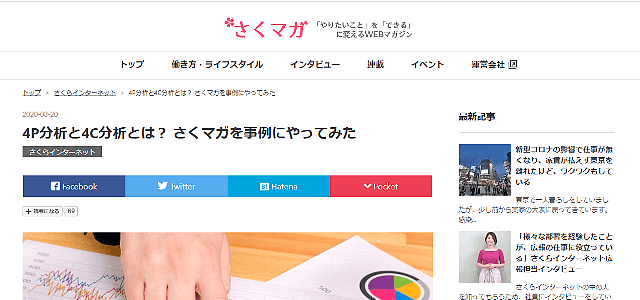
画像引用元:さくらインターネット株式会社Webマガジン「さくマガ」(https://sakumaga.sakura.ad.jp/entry/2020/03/20/100000/)
レンタルサーバーが提供するさくらインターネットが運営する「さくマガ」では、4Pと4Cのどちらも分かりやすくするために自分のメディアを事例にして分析しています。
分析することでメディアとしてもっている強みを認識できたという点まで解説されており、4Pと4Cが大切であることが伝わる記事です。ユーモアも交えて紹介されており、他のメディアでは4Pの必要性が理解が難しい方におすすめです。
| メディア名 | さくマガ |
|---|---|
| 運営元 | さくらインターネット株式会社 |
| 引用元 | さくマガ |
4P分析の事例まとめ

4P分析を解説し、よくメディアで取り上げられる事例を含めてご紹介しました。
4Pをまとめると下記です。
- 4Pはマーケティングのなかで施策を考えるためのフレームワーク
- 提供する側の視点から考えたマーケティングミックス
- 4つの視点で分析する
マーケティングミックスで考える際、提供する側の4Pだけでなく消費者側の視点からみる4Cも切り離せません。
別ページにて4C分析について掲載しているので、合わせてご覧ください。
4P分析後の戦略立案がもっとも重要
4P分析をして満足してはいけず、分析結果をもとに戦略を立てることがマーケティングでもっとも重要です。
自社で戦略を立てるか外部に委託するかは迷う部分ですが、委託すると自社にはない発想を取り入れられるという点でメリットがあります。
自社で戦略を立てると商品やプロジェクトの内容に縛られてしまいがちですが、外部委託なら顧客のニーズも踏まえて客観的に課題の解決方法を提案してくれます。
弊社にはこれまで7000件以上のコンサル実績があり、積み重ねてきたノウハウで課題解決のお手伝いが可能です。下記フォームよりお気軽にご相談ください。
集客やWeb戦略に関する
ご相談はコチラWeb戦略・広告戦略の立て方
重要なフレームワークも紹介
4P分析に関するよくあるご質問
4P分析を初めて行うのですが、各Pを分析する際に役立つ具体的な「質問リスト」のようなものはありますか?
例えば、Productでは「顧客のどのような未充足ニーズに応えるか?」「競合製品と比較した独自性は?」「品質、デザイン、機能、ブランド名はターゲットに響くか?」など。Priceでは「顧客が感じる価値と価格は釣り合っているか?」「価格設定の根拠は(コストベース、価値ベース、競合追随)?」「支払い方法の多様性は顧客の利便性を高めているか?」など。Placeでは「ターゲット顧客はどこで情報を得て、どこで購入することを好むか?」「オンラインとオフラインのチャネルはシームレスに連携しているか?」「物流コストと顧客満足度のバランスは?」など。Promotionでは「最も効果的なメッセージは何か?」「ターゲット顧客にリーチできる最適な媒体は?」「プロモーション活動の成果(例:認知度向上率、リード獲得数)をどう測定・評価するか?」といった具体的な問いを立てて深掘りします。ご要望があれば、詳細なワークシートも提供可能です。
BtoBビジネスで4P分析を活用する場合、BtoCとの違いや特に注意すべき点はありますか?
BtoBの場合、顧客の購買決定プロセスが組織的かつ合理的である点がBtoCと大きく異なります。
Productでは、製品自体の機能や品質に加え、導入後のサポート体制、カスタマイズ性、他システムとの連携性が重視されます。
Priceは、単なる価格だけでなく、TCO(総所有コスト)やROI(投資対効果)が重要な判断基準となります。
Placeでは、直接販売やパートナー経由の販売が多く、長期的な関係構築が求められるチャネル戦略が重要です。
Promotionでは、業界展示会、専門誌広告、ウェビナー、事例紹介、ホワイトペーパーなど、信頼性と専門性を示すコンテンツを通じた情報提供が効果的です。 顧客との継続的なコミュニケーションが鍵となります。
4P分析と4C分析の違いは理解できましたが、実際の戦略立案ではどちらを優先的に考えるべきですか?
一般的には、まず顧客視点の4C(Customer Value:顧客価値、Cost:顧客コスト、Convenience:利便性、Communication:コミュニケーション)を深く理解することから始めるのが効果的です。
顧客が何を本当に求めているのか、どのような負担を感じているのかを把握した上で、それに応える形で企業視点の4P(Product, Price, Place, Promotion)を設計していくという流れです。
つまり、「顧客が欲しいもの(4C)」を起点に、「企業が提供するもの(4P)」を最適化することで、より顧客中心で成功確率の高いマーケティング戦略が生まれます。
4Pの各要素が一貫していることの重要性が説明されていましたが、例えばどのような状態が一貫性がないと言えるのですか?
一貫性がない状態とは、各Pの方向性がバラバラで、顧客に矛盾したメッセージを送ってしまう状態です。
例えば、「最高級の素材を使ったプレミアム製品(Product)」を「格安価格(Price)」で「駅前の雑多な安売り店(Place)」に並べ、「限定タイムセール!(Promotion)」と宣伝していたら、顧客はブランドイメージを正しく認識できず、購入をためらうでしょう。
逆に、アップルのように、革新的な製品(Product)、プレミアムな価格(Price)、洗練された直営店とオンラインストア(Place)、シンプルでスタイリッシュな広告(Promotion)が一貫していると、強力なブランドイメージが形成され、顧客の信頼とロイヤルティを高めます。