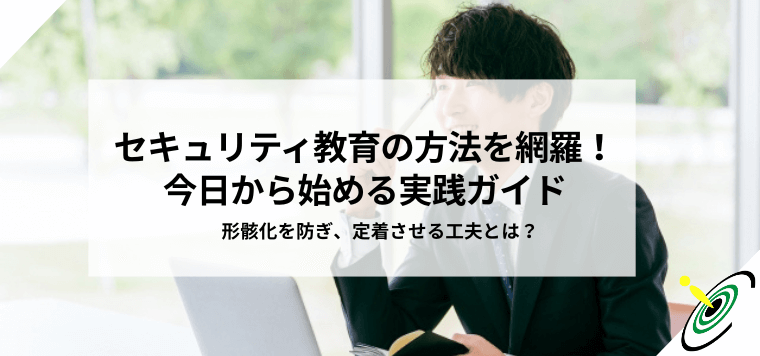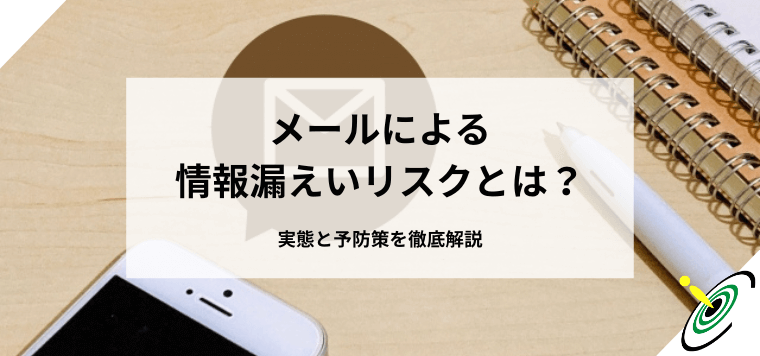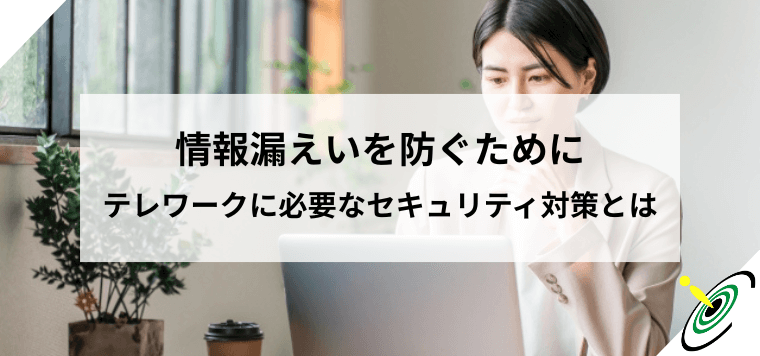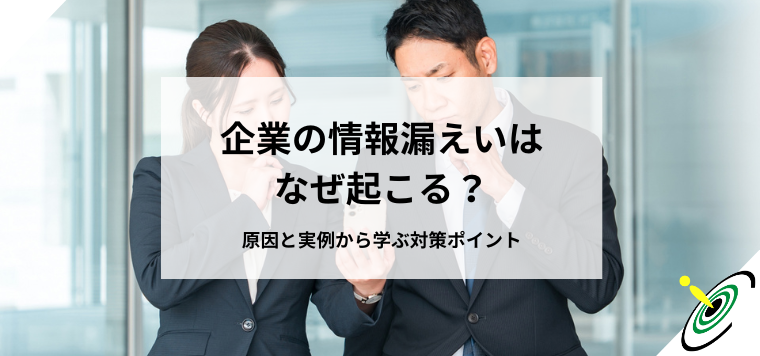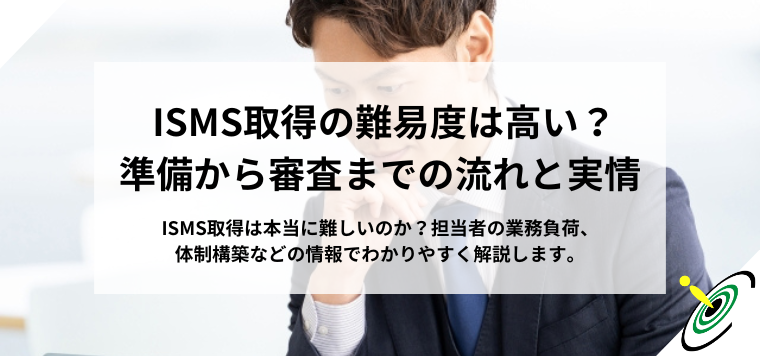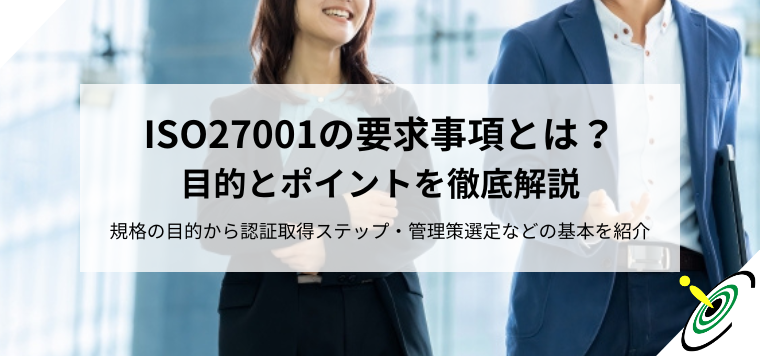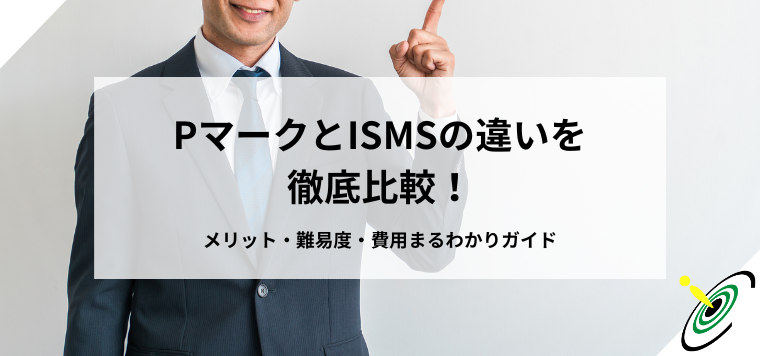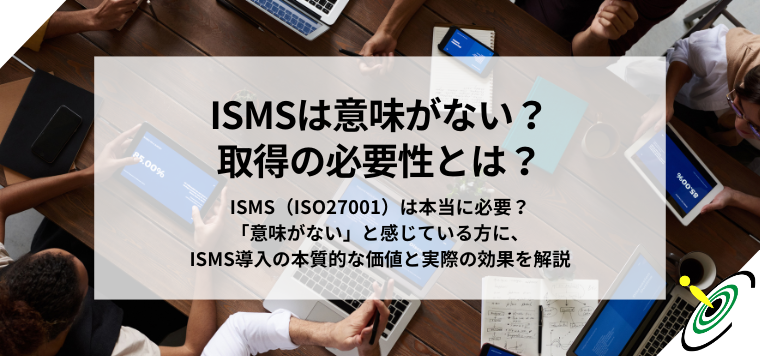校正支援ツールとは、Webサイトやパンフレットなどのさまざまな制作物におけるデータをツール上で共有し、誤字脱字や表記ゆれなどをチェックするツールです。
人の目だけでは気付けないようなミスでも指摘してくれますので、文章の精度を効率的にアップさせることができます。
校正支援ツールを導入すれば、文章力を向上させられたり、業務を効率化できたり、企業のブランディングを強化できたりするメリットがあります。
キャククルでは、校正支援ツールを取り扱う企業の特徴や選ぶべき理由、導入事例などと併せて、メリット、選び方などについても解説しています。校正支援ツール導入を検討している方は、ぜひ参考にしてみてください。
各企業のより詳しい情報は、下記の資料にてご確認いただけます。貴社の検討にお役立てください。
校正支援ツール一覧
| 会社名 | サービスの特徴 |
|---|---|
CRUNCH |
動画校正に特化!現場目線を大事にした校正支援ツール
|
文賢 |
複数作成できるチェックリスト、音声読み上げ機能などもあり |
Just Right!6 Pro |
クオリティを維持したまま素早くチェック、校正にかかる負担を軽減 |
ATOKクラウドチェッカー |
高度な日本語処理技術を用いて間違っている点を素早く発見 |
Press Term |
誰でも簡単に操作できるツール、校正作業における時間と手間を大幅に削減 |
UI Collabo |
すべての校正指示を1つのページに集約、リアルタイムでわかりやすく表示 |
AKAPON |
「動画・LP・画像・PDF校正」に対応、修正箇所にオンラインで校正できる |
Naoshite |
伝わりやすい修正依頼を簡単に作成可能、ツールの種類も豊富 |
AUN |
サイトや画像にふせん紙の感覚で気軽にメモを貼り付け、すぐに共有できる |
IMAGE WORKS PRus |
校正作業をウェブブラウザ上で行って一元管理、やり取りもスムーズ |
Brushup |
すぐに共有してフィードバック可能、校正作業を効率化 |
APROOVE |
データをプレビューして指示を送信、スムーズにコミュニケーションできる |
Ziflow |
レビュー・承認に特化したシンプルで使いやすいオンライン校正ツール |
proofrog |
編集前後の違いをクラウド上でチェック、スピーディーに結果を共有できる |
TOPPAN PRINT ONLINE |
校正業務、ワークフローをクラウドで一元管理、手間と時間を大幅に削減 |
EQUIOS Online |
リモートでスムーズに入稿・校正を実施、効率的な進捗管理を実現 |
PRUV(プルーフ) |
違和感のある文章に対して指摘精度が高い、オリジナルのユーザー辞書も作成可能 |
ENNO(エンノ) |
完全無料で利用可能、あからさまなエラーをチェックしてくれるツール |
AdFlow(アドフロー) |
多彩な機能で制作管理を一元化!案件起票から校了までこれ1つで完結 |
校正支援ツールとは
校正支援ツールとは、Webサイトや出版物、パンフレットなどの多彩な制作物のデータをツール上で共有し、誤字脱字、重複表現、表記ゆれ、言葉の誤用など、さまざまな項目をチェック。誰もが読みやすく、正しい文章の作成をサポートしてくれるものをいいます。人の目だけでは気付けないようなミスまで細かく指摘されますので、文章の精度を効率よく向上させられます。
これまでの校正業務は、紙で印刷し、ペンで直接修正箇所を記載するとうもので、印刷コストや手間がかかっていました。初校・再校を管理したり、印刷会社をはじめとする各ステークホルダーとのやり取りが非常に煩雑であったりするなどという課題がありましたが、クラウド型の校正支援ツールがあれば、オンライン上で修正指示をしてすぐに共有できますので、確認作業も効率よく行えます。
今述べた「クラウド型」と、PCにソフトをインストールして利用する「インストール型」があり、種類も豊富。ツールによって特徴も異なり、無料で利用できるものもあります。
校正支援ツールを利用するメリット
文章力を向上させられる
多くの校正支援ツールでは、文章作成にありがちなミスを指摘してくれたり、代表的な言い換え表現を提案してくれたりします。その指摘や提案を見るだけでも勉強になりますし、文章力・語彙力をアップさせることも可能です。
業務を効率化できる
業務を効率化できるのも、校正支援ツールを利用するメリットの一つ。目視で校正する場合、文章が長ければ長いほど時間がかかり、段々集中力が低下してしまって校正の精度も下がることが予想されます。そんな時、校正支援ツールを利用すれば、クリックするだけで文章のミスを自動的に指摘。効率的な校正が行えるようになります。
ブランディングを強化できる
企業のブログなど、社外向けに発信する文章には統一性が必要で、安定した品質の文章を作り続けることが欠かせません。そのため、校正支援ツールを利用して適切な校正を行えば、企業のブランディング強化にもつながるといえます。
校正支援ツールの選び方
まずは導入する目的を明確にしておく
校正支援ツールを導入する際、そのツールでなにを達成したいのかを明確にする必要があります。自社のルールに沿ってチェックしたいという場合は、メンバー間で共有できる自社独自の辞書の作成や、細かいチェック項目などをカスタマイズできるツールをおすすめします。
また、誤字脱字を徹底的に減らしたい場合は、無料のツールより、有料の方がおすすめ。有料ツールは、誤字脱字のデータを蓄積してチェック精度を高められるからです。さらに、複数のツールを併用するとさらに精度が向上します。
校正に対応する媒体・ファイル形式・デバイスを確認する
それぞれのツールが、どんな媒体やファイル形式に対応しているかを確認しておいてください。PDFや画像などの静止画データの他、HTMLメール、Webサイトなどのコンテンツにも対応しいているツールもあります。
また、校正支援ツールを導入しても使わなければ意味がありません。そのため、自社の業務フローのどこに組み込み、誰が使うのかを決めることも必要です。さらに、リモートで外出先からもチェックを行いたい場合は、スマホやタブレットなどにも対応しているツールを選ぶようにしましょう。
セキュリティ対策もチェックしておく
校正支援ツールを利用して、公開前の文章や、高い機密性がある文章をチェックすることもありますので、それぞれのツールのセキュリティ対策についても確認しておく必要があります。社内にセキュリティ部門があれば、連携させておいてください。
サポート体制もチェック
有料の校正支援ツールは、導入前後のサポートが充実しているのが特徴です。導入を検討している人を対象に、基本機能だけでなく、活用方法を説明するオンライン説明会を開催しているところもありますので、サポート体勢についてもチェックしておくことをおすすめします。
校正支援ツール導入に関するよくある質問
Q1. 校正支援ツールを導入するメリットとは?
校正履歴をリアルタイムで確認できることや、画面データに直接修正指示可能で印刷は不要なこと、修正前後のデータをツール一つで照らし合わすことができること、修正箇所に関するやり取りをツール内で共有できることなどがあります。
Q2. 校正支援ツールの選び方のポイントとは?
誤字脱字だけでなく、誤った敬語、話し言葉・砕けた表現のチェック機能があるツールを選ぶことをおすすめします。また、辞書作成・共有機能、チェック項目のカスタマイズ機能があれば、より便利です。
Q3. 無料・有料の校正支援ツールの違いは?
利用できる機能や文字量に制限がありますが、基本的なチェックを行う際は無料のツールでも役立ちます。有料ツールなら、検出項目、解析速度、解析手段、辞書の数などが格段に向上しますので、分析結果の精度も高いのがポイントです。特に、企業の機密情報を扱う文書を校正する場合は、有料ツールを活用することをおすすめします。
校正支援ツールのまとめ
校正支援ツールとは、Webサイト、パンフレット、出版物などの幅広い制作物におけるデータをツール上で共有し、チェックするもの。誤字脱字や表記ゆれ、重複表現、言葉の誤用など、さまざまな項目をチェック可能です。
目視では、どんなに時間をかけてチェックしても、漏れがあるもの。校正支援ツールなら、人の目だけでは気付けないようなミスまで細かく指摘してくれますので、文章の精度を効率的にアップさせられます。
校正支援ツールには「クラウド型・インストール型」があり、ツールによって特徴も違ってきます。クラウド型の校正支援ツールなら、オンライン上で修正指示をしてすぐに共有可能。社外のライターなどと大人数で使用する場合は、クラウド型が便利です。
校正支援ツールを利用するメリットには、「文章力を向上させられる・業務を効率化できる・ブランディングを強化できる」といった点があります。検討する際は、まずは導入する目的を明確にするところから始めてください。その上で、校正に対応する媒体・ファイル形式・デバイスを確認し、セキュリティ対策、サポート体制もチェックしておきましょう。
校正支援ツールを導入する際は、メリットや選び方をしっかりと確認し、理解しておいてください。
- 免責事項
- 本記事は、2024年1月時点の情報をもとに作成しています。掲載各社の情報・事例をはじめコンテンツ内容は、現時点で削除および変更されている可能性があります。あらかじめご了承ください。


 会社詳細を見る↓
会社詳細を見る↓

.png)