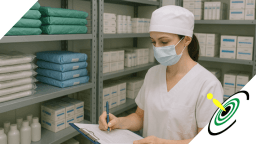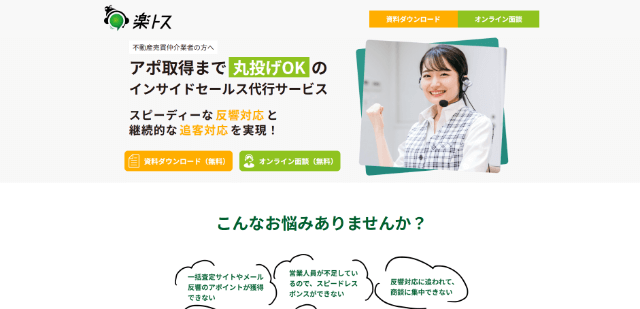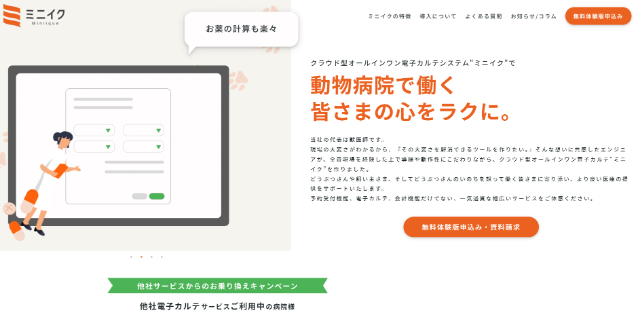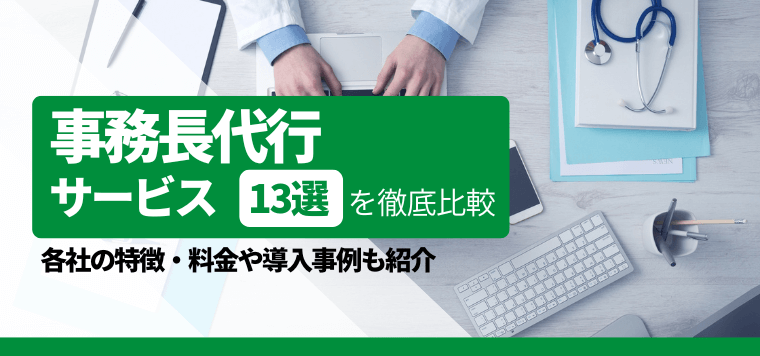この記事では、各社の院内物流管理(SPD)システムの特徴や機能、料金、導入事例などを比較しやすいようにご紹介します。
「在庫が足りない」「期限切れが見つかった」「看護師が備品探しに追われている」… こうした院内物流にまつわる問題は、日々の悩みのタネとなっているのではないでしょうか。「院内物流管理システム(SPDシステム)」は、そういった課題の解決策として注目されています。院内物流(SPD)システムを導入すれば、事務作業や管理業務を減らし、患者対応に集中できる時間を増やすことができます。
院内物流(SPD)システムの導入を検討している方は、院内物流管理システムを選定する際にぜひこの記事を参考にしてみてください。
院内物流管理(SPD)システムの一覧表
ここでは、おすすめの院内物流管理(SPD)システムの特徴を一覧で紹介しています。それぞれのシステムの詳細を確認したい方は、下記のボタンをクリックしてください。(※記事のサービス紹介部分に移動します)
| 会社名 | サービスの特徴 |
|---|---|
Medilia |
【小~中規模向け】充実した導入サポートで迷わず使いこなせるシステム
|
スズケン |
システムと人材を組み合わせたアウトソーシング型SPD |
Medical Stream |
使った物品を自動で記録し入力作業を削減 |
Medyus3 |
その場で読み取り登録!在庫と請求を一括更新 |
JoyPla® |
インターネット経由で導入も運用もかんたん |
ゼロサプライ |
複数病院の在庫を一画面で見える化 |
東亜システム |
請求漏れを自動チェックし、収入の取りこぼしを防ぐ |
Mr. SPD |
登録はカードを集めてスキャンするだけ |
Mediboard |
在庫・発注・契約書をひとつの画面で管理 |
MASTY |
全国の拠点から安定供給!アウトソーシング型のSPD |
X-SPD |
300床~400床の大学病院の導入実績もある院内物流管理システム |
キシヤ物流センター |
現場主義に基づくサポートで円滑なシステム導入を実現 |
Logistics Service System |
施設の運用実態に応じて柔軟に構築可能なシステム |
院内物流管理(SPD)システムとは?
.png)
SPDはSupply(供給)、Processing(加工)、Distribution(分配)の頭文字をとった略語です。その名の通り、医薬品や診療材料、手術器械から事務用品まで、あらゆる物品の調達、在庫管理、各部署への供給を一元的に管理することを目指します。
SPDの目的は、院内の物品管理を最適化し、病院経営の強さや柔軟性を高めることにあります。コンピューターシステムを活用することで、複雑で多くの作業が必要な物流業務を効率的に進めることができるようになります。
院内物流管理システムが求められる背景
1990年代初頭、中央材料室の滅菌業務や物品供給を外部業者が担う形から導入が始まりました。特に2000年代以降は、医療材料費の削減や看護師の業務負担軽減を目的に、国公立病院や中〜大規模の民間病院を中心に普及が加速しました。
2020年代に入ると、働き方改革や医療安全の強化、DX(デジタルトランスフォーメーション)推進の文脈でも注目され、SPD導入は業務改善の中核施策として位置付けられています。現在では病院の約半数以上がSPDを何らかの形で導入※しており、特に大規模病院では、SPDなしには物品管理が成り立たないケースも増えています。
※参照元:独立行政法人福祉医療機構 | 2020年度(令和2年度)病院における医薬品・医療材料・医療消耗器具備品の購入に関するアンケート結果について【PDF】(https://www.wam.go.jp/hp/wp-content/uploads/210310_No014.pdf)
また、2024には2019改正された労働基準法に基づいて、医師や看護師にも時間外労働の上限が設けられました。その上限を守り、患者が中心になっているコア業務に集中するためにも、SPDシステムによる手間の削減や業務効率化が注目されています。
| 医療機関に適用する水準 | 年の上限時間 |
|---|---|
| A(一般労働者と同程度) | 960時間 |
| 連携B(医師を派遣する病院) | 1,860時間 ※2035年度末を目標に終了 |
| B(救急医療等) | |
| C-1(臨床・専門研修) | 1,860時間 |
| C-2(高度技能の修得研修) |
※参照元:厚生労働省「医師の働き方改革 ~医療を未来に繋ぐために~」【PDF】P.33(https://www.mhlw.go.jp/content/10800000/001128607.pdf)
院内物流管理(SPD)システムと一般的な物流管理システムの違い
一般的な物流管理システムは、商品や資材の入出庫・在庫管理・配送など、主に製造業や小売業の業務効率化を目的に設計されています。一方、院内物流管理システムは、医療機関の特性に合わせて最適化されたシステムです。
SPDでは、医療材料や医薬品など命に直結する物品を対象とし、ロット管理・使用期限の徹底や患者ごとの使用履歴の記録など、より高度なトレーサビリティ(追跡可能性)が求められます。また、電子カルテや会計システムと連携し、保険請求漏れの防止や院内業務の一元管理も実現できます。単なる物流の効率化ではなく、医療の安全性と経営効率の両立を支えるシステムになっていることが、一般的な物流システムとの決定的な違いです。
院内SPDと院外SPDの違い
院内物流管理システム(SPD)の他には、院外物流管理システムもあります。院内SPDは、病院内に設置された物流センターで運用され、現場と近い場所のリアルタイム物品管理に特化しています。
一方、院外SPDは、病院外の拠点に物流機能を置き、広域で複数の施設をまとめて管理するためのシステムです。院外SPDはスケールメリットやコスト面で優れていますが、緊急時に対応フローが複雑になるなど、院内SPDに比べて課題もあります。
院内物流管理(SPD)システムの主な機能
ここでは、SPDシステムの一般的な機能とそのメリット・使い方をまとめています。
| 機能 | 説明 | 効果 |
|---|---|---|
| 在庫管理 | 医療材料や医薬品の入出庫をバーコードやRFIDで記録し、残量を随時確認できる | ・コストを削減しながら、安定供給を実現 ・期限切れによる廃棄リスクの防止 |
| 発注・補充管理 | 必要量を自動的に算出し、医療材料・医薬品が少なくなってきたタイミングで発注できる | ・担当者の負担軽減 ・発注ミスの防止 ・コストの適正化 |
| ロット・トレーサビリティ管理 | 製品ごとのロット番号やシリアル番号を管理できる | ・リコール対象製品の早期特定と使用状況確認 |
| 使用実績・コスト分析 | 医療材料や医薬品の使用履歴をデータとして蓄積し、部門別や患者別に分析できる | ・無駄な使用の削減や適正配布の徹底 |
| 請求・会計システム連携 | 医療材料・医薬品の使用や発注に関するデータを院内の会計・請求システムに反映できる | ・入力作業の手間削減 ・請求漏れや二重計上のミスを防止 |
SPDシステムの活用による作業時間短縮のイメージ
SPDシステムを導入することで、在庫管理や発注業務などの作業時間は大幅に短縮されます。手作業で行っていた在庫チェックや補充発注はシステムにより自動化され、現場スタッフの業務負荷が軽減します。また、SPDシステムで蓄積された消費データを活用することで、コスト分析や予算管理もスムーズになります。
以下は、SPD導入の「前」と「後」で各業務に要する時間削減イメージをまとめてみました。(※あくまで目安)
| 業務項目 | 導入前の作業時間(目安) | 導入後の作業時間(目安) |
|---|---|---|
| 在庫管理 | 約20時間/月 | 約5時間/月 |
| 発注・補充管理 | 約16時間/月 | 約4時間/月 |
| 請求関連作業 | 約10時間/月 | 約2時間/月 |
院内物流管理(SPD)システムにかかる料金・費用
SPDシステムの導入には、初期費用と月額運用費用の2つが発生することが一般的です。初期費用にはシステム構築・端末導入・データ移行などが含まれており、規模によって数百万円から数千万円までの幅があります。月額運用費も規模や機能ラインアップによって10万円前後から数百万円まで大きく異なります。
以下の表に「中小規模(100〜300床程度)」と「大規模(500床以上)」での目安をまとめました。
| 病院規模 | 初期導入費用(目安) | 月額運用費(目安) | 特徴 |
|---|---|---|---|
| 中小規模病院(〜300床程度) | 300〜800万円 | 10〜50万円 | 必要機能を絞り導入、コストを抑えやすい |
| 大規模病院(500床以上) | 1,000万円〜数千万円 | 100〜300万円以上 | 複数拠点・高機能システムが必要、投資規模も大きい |
小規模病院は、必要最低限の機能を安定的に利用できる定額プランがおすすめです。中間帯では柔軟なオプション追加が可能なケースが多く、規模拡大にも対応しやすくなります。高額なシステムは大規模病院向けになっており、在庫管理・経営分析・AI予測などを組み込んだSPDシステムが多く見られます。
院内物流管理(SPD)システムの選び方:導入パターンと選定ポイント
「システム単体型」と「業務委託型」の違い
.png)
| システム単体型 | 業務委託型 | |
|---|---|---|
| 運用主体 | 自院 | 委託業者 |
| コスト | ランニングコスト低め | 委託費用が発生 |
| ノウハウ蓄積 | あり | 院内では限定的 |
| 人材リソース | 必要 | 最小限で可 |
| 柔軟性 | 高い | 委託内容に依存 |
システム選定で失敗しないための4つのチェックポイント
院内物流管理システムの導入を検討するうえで、単に「どちらが良いか」ではなく、「自院の経営戦略や現場の状況にとって、どちらが現実的で効果的か」を見極めることが、SPD導入の成否を左右します。
判断に迷う場合は、複数のベンダーに相談し、提案を比較検討することをおすすめします。導入後に後悔しないためにも、丁寧な見極めが大切です。
1. 病院の規模(病床数・物品量)
まずは病院の規模に着目しましょう。病床数が多く、物品の取り扱い点数が多い病院では、物量に比例して業務の煩雑さも増すため、専門業者による業務委託型を検討する価値があります。
一方、100~300床程度の中小規模病院では、シンプルな運用でも十分に回せる可能性があり、自院で完結する「システム単体型」のほうが適していることもあります。
2. 既存システムとの連携
電子カルテや医事会計システムなど、既に運用しているシステムとの連携性も重要な判断材料です。
院内物流管理システムを導入しても、他のシステムと連携できなければ、二重入力やデータ整合性の問題が発生し、かえって業務の負担が増えることもあります。
事前に、自院が使っているシステムとの接続実績があるベンダーかどうかを確認しましょう。
3. 院内の人的リソース(担当者の有無・専門性)
SPDを自院で運用するには、専任の物流管理担当者やシステムの運用を任せられる人材が必要です。人員に余裕があり、現場の業務改善に前向きなスタッフがいれば、システム単体型を導入して自院にノウハウを蓄積していくのも良い選択です。
反対に、すでに人手が足りていない、または他業務で手一杯な状況であれば、業務委託型で外部に任せたほうが安定した運用につながります。
4. 費用対効果(初期コストとランニングコスト)
システム単体型は初期導入コストがかかるものの、運用後のランニングコストを比較的抑えられる傾向にあります。反対に、業務委託型は人件費やサービス費用が発生するため、継続的な支出が必要になります。
初期費用と継続的な費用、そして見込まれる効果(コスト削減、業務削減、人材育成など)をトータルで比較することが大切です。
病院タイプ別の選定パターン
SPDシステムは病院の規模や運営方針によって導入すべき製品が変わってきます。以下に病床数別のおすすめポイントを整理しました。
100床未満の病院
基本的な機能(在庫管理、発注支援)が搭載され、定額プランが選べるシステムがおすすめです。小規模向けSPDシステムを導入することで、最低限の人的コスト削減と在庫精度の改善を実現できます。また、スタッフに負担をかけずに導入するためには、シンプルで見やすい画面設計・デザイン(UI)も重要です。
100〜300床の病院
基本機能のラインアップがが小規模向けシステムに近く、オプション追加が可能な中間帯のSPDシステムを選ぶことで、コストを抑えつつ将来的な規模拡大にも対応できます。規模に応じて、在庫管理に加えて消耗品の自動補充や使用履歴閲覧ができるシステムが効果的です。
500床以上の大規模病院
複数拠点の連携や、RFID・AIを活用した高度な在庫管理を行える高機能システムがおすすめです。リアルタイムデータ分析やコスト削減効果の見える化、経営層向けのレポート機能を備えたSPDシステムを選ぶと、物品管理の最適化が経営全体の改善に繋がりやすくなります。初期費用・運用費は高額になりますが、長期的には効率改善による大きな投資対効果(ROI)が見込めます。
各社が提供する院内物流管理(SPD)システムの詳細情報
ここでは、各社が提供している院内物流管理(SPD)システムの特徴や導入事例を詳しく紹介しています。選定の際はぜひ参考にしてみてください。
院内物流管理(SPD)システムに関するよくある質問
院内物流管理システムの導入や運用を検討していると、「本当に現場で使いこなせるのか?」「きちんと定着するのか?」といった不安の声が多く聞かれます。ここでは、実際によく寄せられる質問とその回答をわかりやすく解説します。
Q1. スタッフが新しいシステムを使いこなせるか不安です。
A:導入時の丁寧な研修と継続的なフォローがあれば、問題なく運用できます。
院内物流管理システムは一見難しそうに感じるかもしれませんが、操作自体は非常にシンプルに設計されています。多くの現場では、ハンディターミナルでバーコードを「ピッ」と読み取るだけで在庫管理が完了するなど、誰でも扱いやすい工夫がされています。
また、導入時にはベンダーによる操作説明会や実地研修が行われるほか、導入後も定期的なフォローや相談窓口が設けられるケースが一般的です。現場スタッフの「使いやすい」という声を反映しながら、運用にフィットする形で徐々に慣れていけるので、心配しすぎる必要はありません。
Q2. スタッフがスキャン作業を面倒がって使わなくなるのでは?
A:使うメリットが実感できれば、自然と定着します。
現場での「面倒くさい」「忙しくて後回しになりがち」といった声は、どの病院でも起こりうる課題です。しかし、それを防ぐポイントは、「システムを使うことで自分たちの仕事が楽になる」と感じてもらえるかどうかです。
「在庫が自動で補充される」「棚卸がすぐ終わる」といった実感が持てれば、スタッフの間で自然とシステム利用が習慣化されます。導入初期は少し根気がいりますが、管理者やリーダー層が積極的に声をかけ、活用メリットを伝えていくことが効果的です。
Q3. 導入当初に整えた物品データが、数年後には古くなって使えなくなってしまわないか心配です。
A:定期的なチェック体制と管理ルールの明確化で、データの鮮度は維持できます。
院内物流管理システムの精度を保つうえで欠かせないのが、物品マスタ(品名・単価・ロットなど)の更新です。「最初は正確でも、その後のメンテナンスが行き届かない」という事例は少なくありません。
ベンダーによっては、物品マスタを提供してくれるところもあり、製品の追加・更新作業を支援してくれる場合もあります。もし「自院だけで管理していくのは不安」という場合は、こうしたサポートがあるベンダーを選ぶことで、より安心して運用を続けることができるでしょう。
Q4. 委託業者に任せた場合、サービスの質が安定するか不安です。
A:事前に契約内容とサービス水準をしっかり確認することが大切です。
業務委託型SPDでは、外部の業者が物品管理を担うため、「ちゃんとやってくれるのか?」「トラブル対応は?」といった不安を感じる方も少なくありません。
委託契約を結ぶ際には、サービス水準(SLA)を明確にしておくことが大切です。たとえば、「欠品率は月0.1%以内」「緊急対応は30分以内」などの具体的な指標を契約書に盛り込んでおけば、万一の際も改善要求をしやすくなります。
また、導入後も定期的にレビュー会議を開き、現場の声を業者に伝えながら運用をブラッシュアップしていくことで、良好なパートナー関係を築くことができます。
まとめ
院内物流管理システムは、単なる「在庫管理ツール」ではありません。院内のすみずみにまで物品を行き渡らせ、スタッフの業務を支え、患者さんに安心と安全を届けるための、見えないインフラとして病院運営の根幹を支えています。
導入にあたっては不安や課題もあるかもしれませんが、それら一つひとつにしっかりとした解決策があります。自院の状況や体制に合わせたシステムや運用方法を選ぶことで、確実に成果を上げることができるはずです。
これからの病院運営をもっと前向きに、もっとスマートにするために、今こそ、自院に合った導入を前向きに検討してみてはいかがでしょうか。
また、この記事で紹介している製品以外のSPDシステムも確認したい方は、SPDサービス事業者専門メディア「MediLogi(メディロジ)」もぜひご確認ください。
他の医療系システム・サービスはこちら
- 免責事項
- 本記事は、2025年7月時点の情報をもとに作成しています。掲載各社の情報・事例をはじめコンテンツ内容は、現時点で削除および変更されている可能性があります。あらかじめご了承ください。


 公式サイトで詳しく見る→
公式サイトで詳しく見る→