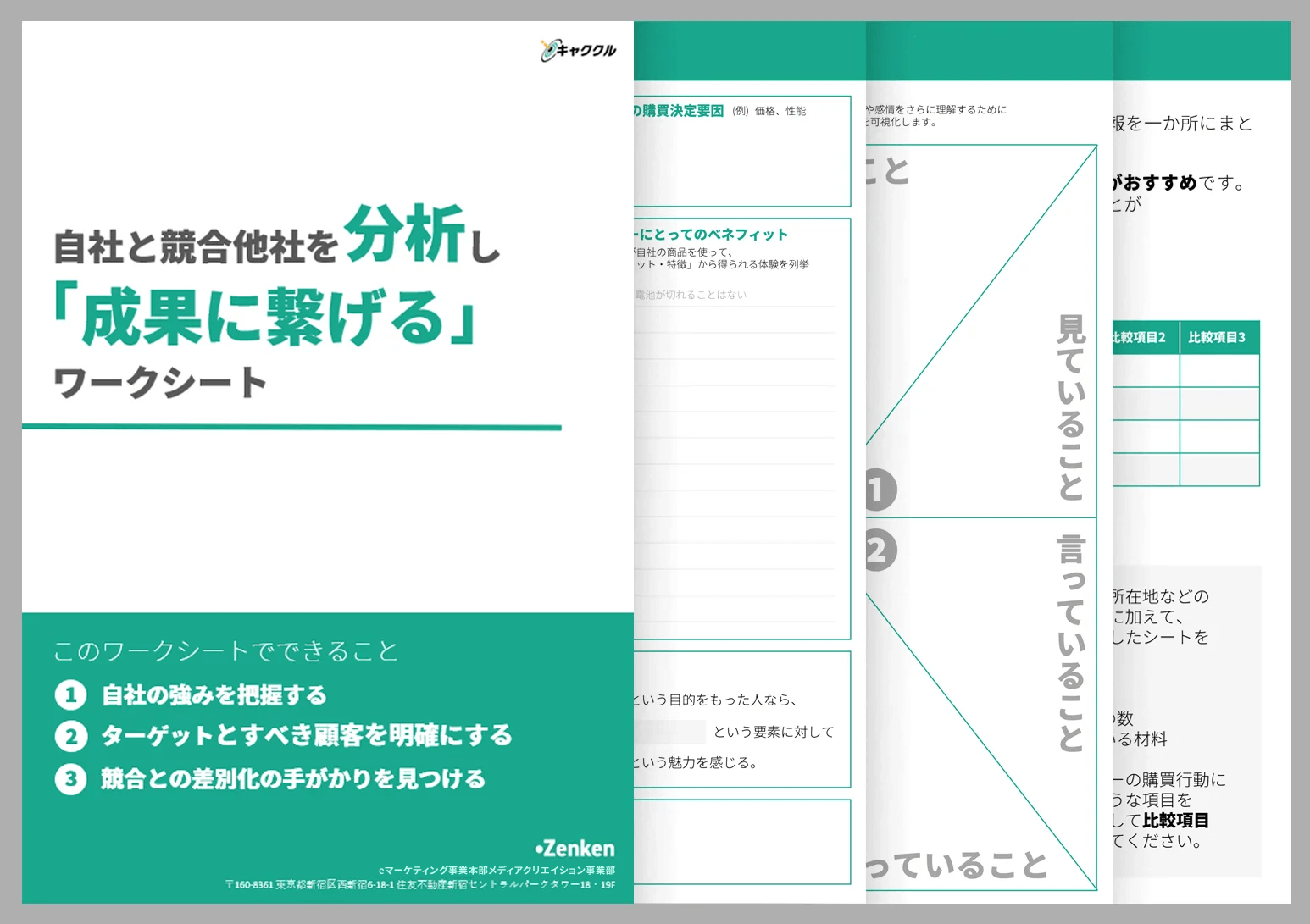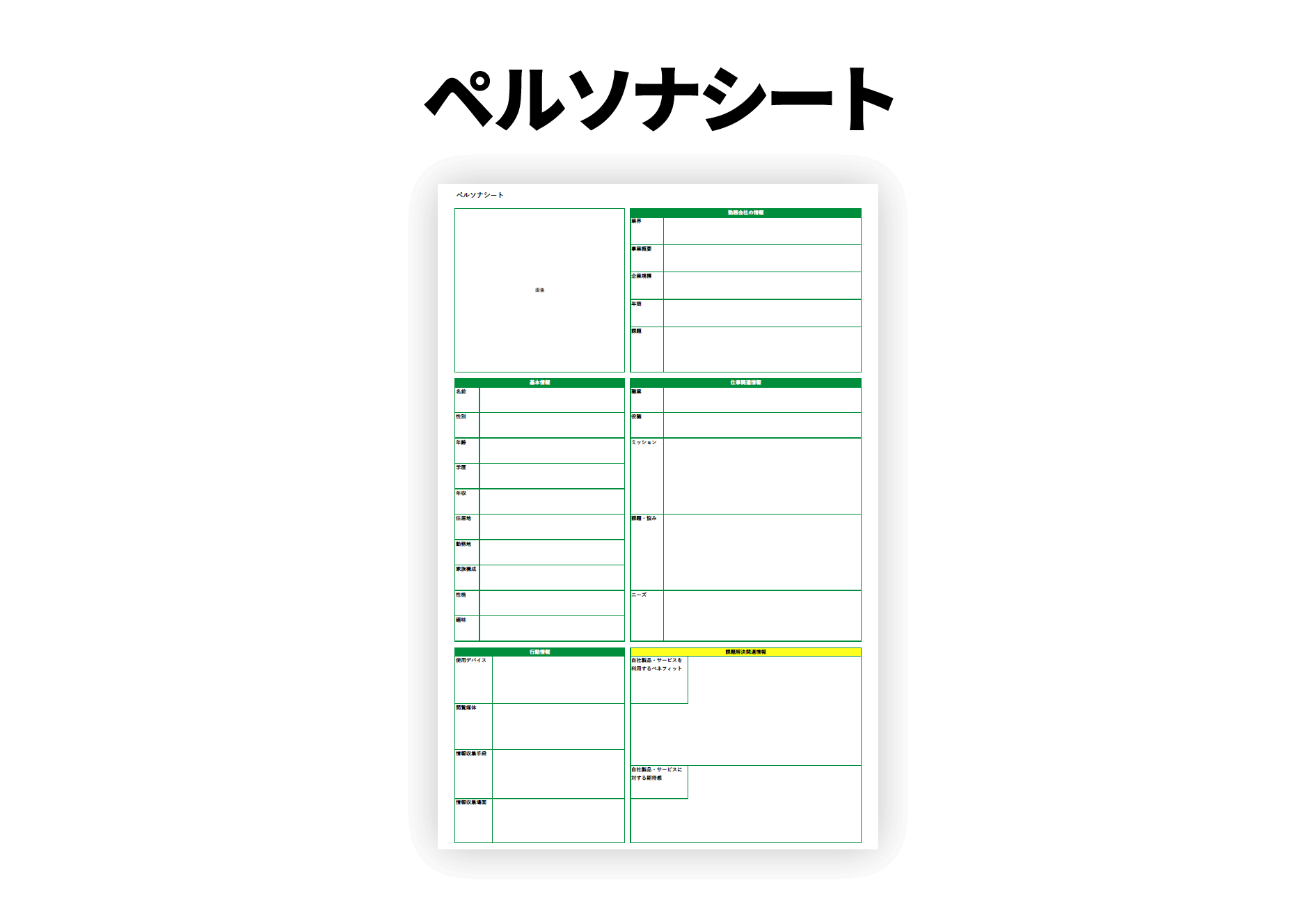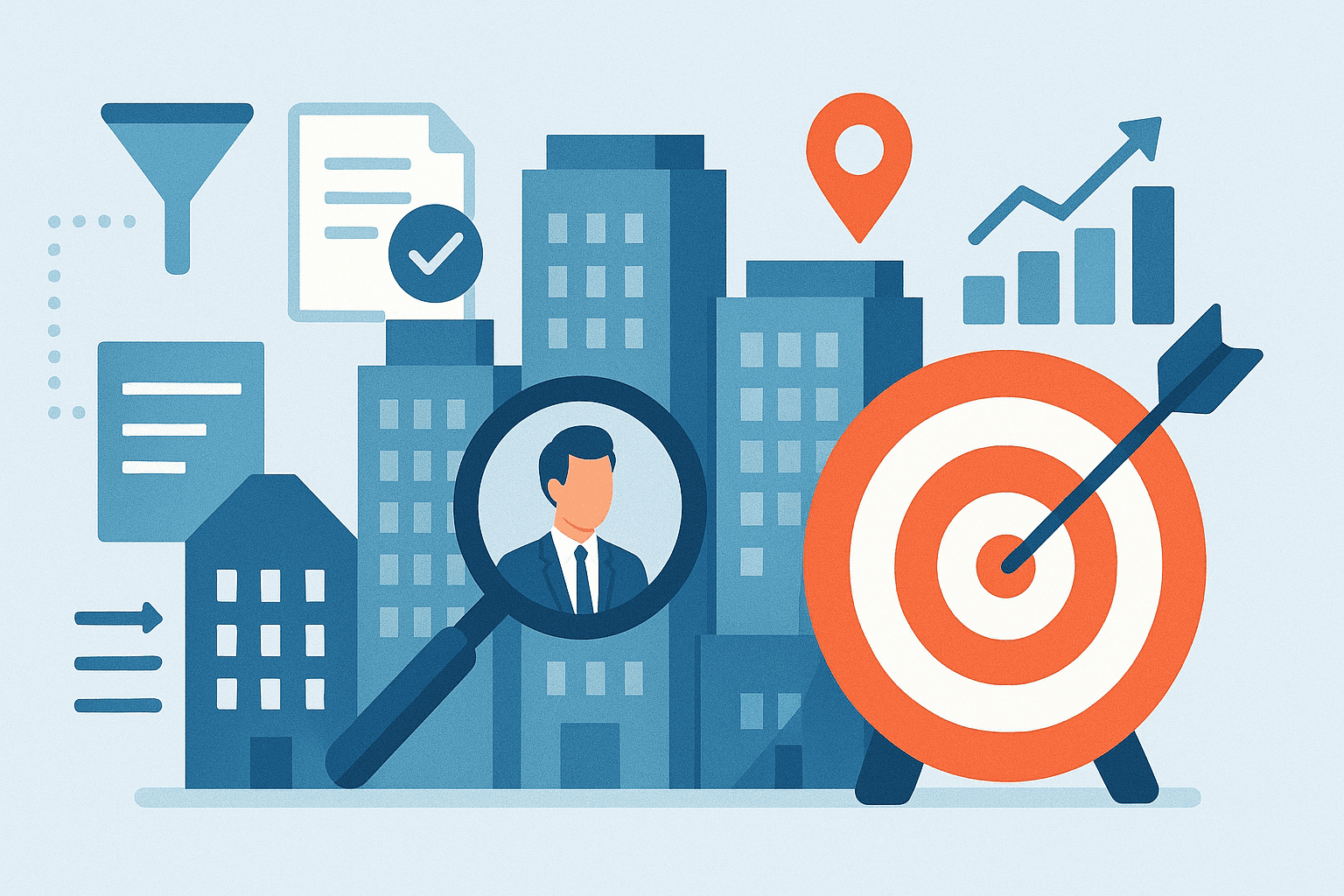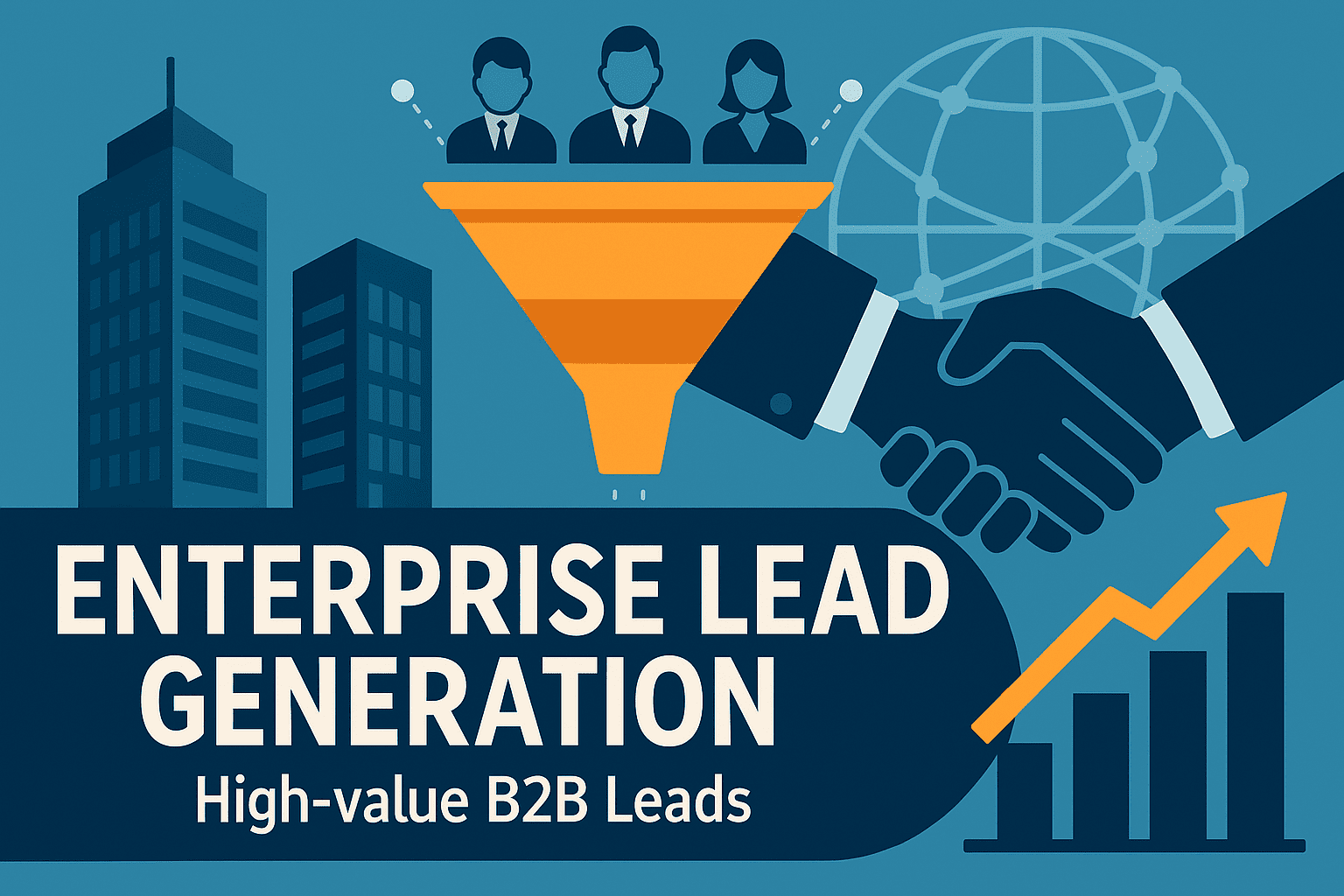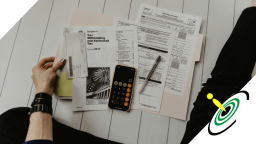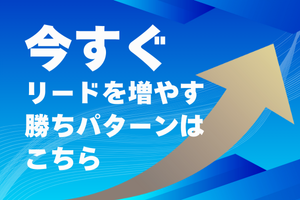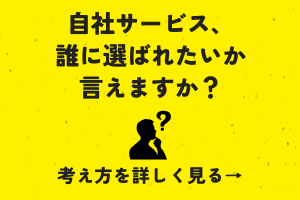BtoBセグメンテーションを事例で学ぶリード獲得と商談率を最大化する戦略的アプローチ
最終更新日:2025年06月16日
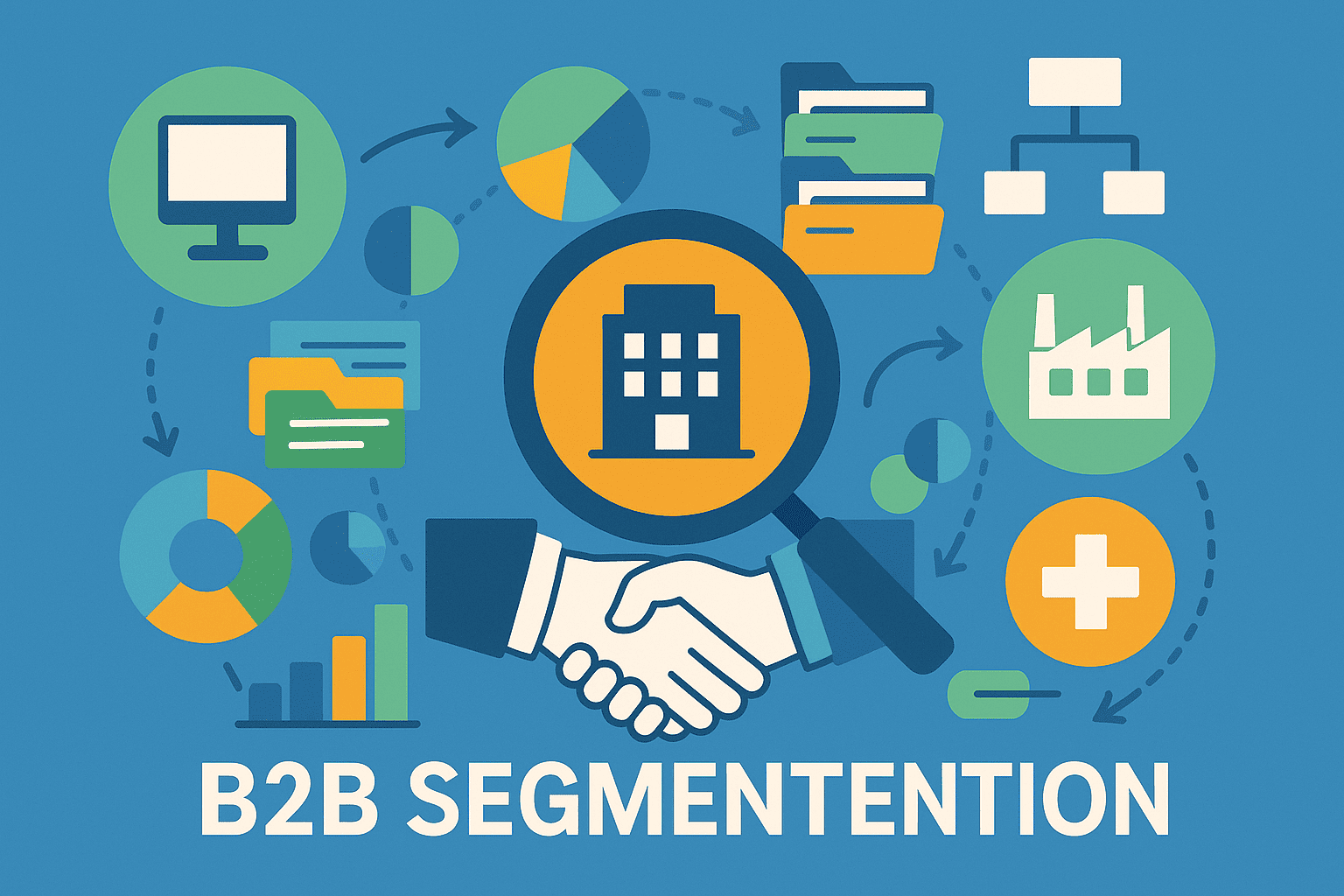
1. BtoBセグメンテーションとは何か?全体像と重要性
BtoBビジネスの現場で、「リードは集まるが、なかなか商談につながらない」「広告費ばかりかさみ、効果を実感できない」といった悩みを抱える企業は少なくありません。その根本原因は、多くの場合「市場や顧客をひとまとめにした画一的なアプローチ」にあります。
このような課題を解決するカギとなるのが「セグメンテーション」です。セグメンテーションは単なる区分作業ではなく、自社が本当に勝てるフィールドを見つけ、競合に差をつけるための戦略的なプロセスです。
BtoB領域でのセグメンテーションは「誰に何を届けるか」を明確にし、リード獲得・商談率アップ・営業効率化の実現に直結する、極めて重要な基盤となります。
この章ではBtoBセグメンテーションの全体像、重要性、そしてSTP分析との関係について分かりやすく解説します。
1-1. BtoCとの違いから見るBtoB独自のセグメンテーション
BtoBとBtoCのマーケティングは「対象」「決定プロセス」「購買理由」など多くの面で異なります。
BtoCが個人の感情や好みに強く左右されるのに対し、BtoBの意思決定は合理性や組織の課題解決を重視します。しかもBtoBでは複数人が意思決定に関わり、部署や役職ごとに関心事が異なるため、より多角的な視点が求められます。
| 軸 | BtoB | BtoC |
|---|---|---|
| 意思決定者 | 複数(担当者・利用者・決裁者) | 本人/家族 |
| 購買理由 | 課題解決・収益性・効率化 | 感情・好み・流行 |
| 購買プロセス | 長期・複雑・段階的 | 短期・単純 |
BtoBでは「企業単位の深い理解」と「多角的な分類」が不可欠です。
1-2. BtoBセグメンテーションの最新トレンド
市場環境やデジタルシフトの進展により、BtoBのセグメンテーションも進化を遂げています。従来の「業種」「規模」だけでなく、企業の行動データやインテントデータ(検索やWeb閲覧の履歴)、ゼロパーティデータ(アンケート等による自発的情報)など、より細やかな分類が可能になりました。
また、競争が激しい現代においては「特定のニッチ市場で第一人者となる」アプローチや、AIを活用した動的なセグメンテーションも急速に普及しています。
現場で成果を出すには、時代に合った軸でセグメンテーションを見直すことが不可欠です。
2. セグメンテーションの切り口を徹底解説|分類軸の全体像
BtoBのセグメンテーションでは、「誰に」「どのような価値を届けるか」を明確にするために複数の分類軸を組み合わせて考えます。
ここでは、BtoBマーケティングで用いられる主要な分類軸を具体的に解説します。
- 企業属性(ファーモグラフィック)
- ビジネスモデル・商流
- 部署・職種・役職
- 購入歴・利用状況
- 社風・価値観
- 行動・ニーズ・課題
2-1. 企業属性による分類(ファーモグラフィック変数)
企業規模、業種、所在地など、「客観的なプロフィール」による分類です。
たとえば「従業員1000人以上の製造業」「首都圏のIT企業」などが該当します。
2-1-1. 業種・業界別の分類例とアプローチの違い
業種や業界によって、導入されやすいサービスや重視されるポイントは大きく異なります。
| 業種 | アプローチ例 |
|---|---|
| 製造業 | 設備投資時のコスト・効率化 |
| IT業界 | 最新技術への対応・テレワーク支援 |
| 医療機関 | 規制対応・セキュリティ強化 |
2-2. ビジネスモデル・商流による分類
事業会社、代理店、OEM供給先、SIerなど、「ビジネスモデルや商流」による分類も重要です。
たとえば、「代理店経由の販売が多い業界」「直販モデルが主流の分野」など、モデルによって求められるサポートや施策が変わります。
2-3. 部署・職種・役職による分類
同じ企業でも、部署や役職によって「重視するポイント」「求める成果」が異なります。経営層はROIや全社戦略、現場責任者は使いやすさや運用負担、人事部門は導入・定着などを重視する傾向があります。
2-4. 購入歴・利用状況による分類
新規顧客・既存顧客・休眠顧客、LTV(顧客生涯価値)、サービス利用状況など、「これまでの取引実績や利用状況」も有効な分類軸です。
過去の購入履歴や利用サービス数をもとに、最適なアプローチや再提案がしやすくなります。
2-5. 社風・組織文化・価値観による分類
「イノベーション志向」「保守的」「多様な働き方」など、社風や価値観も重要な分類軸です。
たとえば「新しい取り組みに積極的な企業」には、最新技術の提案や導入サポート型のアプローチが効果的です。
2-6. 行動・ニーズ・課題による分類(ビヘイビアル変数)
「Webサイトの訪問頻度」「セミナー参加歴」「直近で抱える課題」など、行動やニーズベースで分類します。
- 価格ページの閲覧
- 競合比較の資料ダウンロード
- 課題に関するアンケート回答
これらを組み合わせることで、単なる「属性」から「今、本当に必要としている企業」へと精度を高められます。
3. 実務で活用できるBtoBセグメンテーションの事例・パターン集
ここからは、実際に現場で活用されているBtoBセグメンテーションの事例を紹介します。自社の業種・サービスに応じて参考にしてみてください。
3-1. SaaSビジネスでのセグメンテーション事例
SaaSビジネスでは、以下のような多層的な分類が成果につながります。
-
業界特化型:
IT業界・小売・介護など、各業界ごとに異なる業務課題や法規制、現場のニーズに合わせてサービスや提案内容を最適化します。
例えばIT業界向けには「API連携やセキュリティ機能」を強調、小売業界向けには「在庫管理やシフト管理機能」を充実させるなど、業界の特性に寄り添ったソリューション設計が有効です。
介護業界の場合は、「複雑なシフト作成や法制度対応」「スタッフの勤怠把握」といった現場の負担軽減に直結する機能の訴求が反響を得やすいでしょう。 -
規模別パッケージ:中小企業向け/大企業向け
企業の規模により必要な機能やサポート内容は大きく異なります。
中小企業には「手軽な価格設定」「シンプル操作」「導入サポート付き」など導入障壁を下げる工夫が効果的です。
一方、大企業向けには「複数拠点の統合管理」「カスタマイズ性」「外部システム連携」など、より高度な要望に応えるパッケージを用意しましょう。
規模ごとのパッケージ分けにより、最適な価値を届けやすくなります。 -
テレワーク導入状況:リモート重視・オフィス重視
近年の働き方改革や感染症対策により、テレワーク対応は必須となっています。
「リモート重視」の企業には、クラウド型・モバイル対応・オンライン打刻・セキュリティ対策などを重視し、場所に縛られない業務環境を提案します。
一方で「オフィス重視」の企業には、ICカード打刻・現場向け端末の導入支援など、従来型の運用をサポートする機能が求められます。
勤務スタイルの違いに応じて最適な導入事例やメリットを伝えることが重要です。
このように、「業界」「企業規模」「働き方」といった複数の切り口を組み合わせることで、SaaSビジネスにおいては顧客の解像度を高め、ニーズに合った提案ができるようになります。 自社サービスがどのセグメントに最も強みを発揮できるかを見極めることが、成果につながる第一歩です。
3-2. 製造業向けのセグメンテーション事例
製造業では、地域密着型・用途別・設備投資のタイミングなど、現場の事情に即した切り口が効果的です。
| 分類軸 | 例 |
|---|---|
| 地域 | 関東/関西/地方都市 |
| 用途 | 自社工場用/外部委託用 |
| 投資フェーズ | 新設/増設/入れ替え |
たとえば「地方都市の新設工場向けにIoT導入を支援」「既存工場の設備入れ替えに対応したメンテナンスパッケージ」など、状況に応じた細やかな訴求が成果を生みます。
また、設備投資のタイミング(年度末・新工場稼働時など)を捉えて提案活動を強化することで、受注率の向上にもつながります。
3-3. サービス業におけるセグメンテーション事例
サービス業は多様な顧客層・提供形態が存在するため、分類軸も幅広くなります。
- 契約形態(定期契約/スポット契約/サブスクリプション)
- 提供地域(全国展開/特定地域特化)
- 業種・業態別(飲食・宿泊・医療・教育など)
- 顧客課題(人手不足解消/業務効率化/新規顧客獲得)
たとえば、飲食業向けには「人材不足を解消する自動予約システム」、医療機関には「法規制に対応した記録管理サービス」など、課題別にアプローチを最適化することで訴求力が高まります。
また、サブスクリプションモデルやスポット契約モデルなど、契約形態ごとの提案を分けることで成約率も向上します。
3-4. ITベンダーにおけるセグメンテーション事例
ITベンダーの場合は、導入先のITリテラシーやシステム環境、予算規模、業界ごとの課題に応じてセグメントを切り分けることがポイントです。
- 導入済みシステムの種類(ERP/CRM/基幹系システムなど)
- IT予算規模(年間予算1000万円以上/1000万円未満)
- 業界特有の要件(製造/物流/金融/自治体など)
- クラウド志向かオンプレ志向か
- 社内IT担当者の有無・外部委託の状況
例として、既存のオンプレミス型システムからクラウド移行を検討している中堅製造業向けに、段階的な移行サポートパッケージを提案するなど、導入状況や課題に応じて個別最適化されたソリューションが成果に直結します。
また、SIerやパートナー経由での販売チャネルを分けて施策を打つことも有効です。
3-5. AI・データ活用型の最新セグメンテーション事例
最近では、AIやデータ分析によって「Web閲覧履歴」「資料DL」「セミナー参加」など、行動履歴をもとに自動で分類・スコアリングを行い、高精度なリード抽出を実現する事例が増えています。
たとえば、価格ページを複数回閲覧した企業や、競合サービスの比較資料をダウンロードしたリードに対して優先的にアプローチすることで、商談率を大幅に高めた企業もあります。
AIによるリードスコアリングやMA(マーケティングオートメーション)と組み合わせた運用は、今後ますます重要性を増していくでしょう。
4. 成功するBtoBセグメンテーションの進め方・実践プロセス
成果につなげるためには、正しい手順でセグメンテーションを進めることが重要です。ここでは、具体的なプロセスとポイントを解説します。
4-1. 現状分析とターゲット仮説の立て方
BtoBセグメンテーションの第一歩は、「自社の強みが最も活かせる市場はどこか?」を客観的に見極めることです。そのために不可欠なのが、既存顧客や失注顧客データの徹底的な分析と、現場からのリアルな声の収集です。
1. 既存顧客データの分析
まずは自社の顧客データベースやCRMに蓄積されている情報を洗い出します。 特に注目したいのは、LTV(顧客生涯価値)が高い優良顧客や、成約までのプロセスが短かった案件です。
これらの顧客を「企業属性(業種・規模・地域)」「担当者の役職」「導入理由」「利用サービス」など多角的な軸で一覧化しましょう。
- どの業種や業界で成約率が高いか
- 受注単価やLTVが高い企業の共通点
- 担当者の決裁権限や部門
- 導入の決め手となった課題・要望
このようなデータ分析によって、「どんな顧客層に自社の価値が一番響くのか」を可視化できます。
2. 失注顧客・滞留リードの分析
次に、「商談まで進んだが受注に至らなかった顧客」や、「獲得後に動きが止まってしまったリード」も分析対象とします。
チェックすべきポイント:
- 失注した理由(価格、競合、タイミングなど)
- 検討段階での課題や懸念点
- アプローチ内容や提案内容とのミスマッチ
失注分析を行うことで、「避けるべきセグメント」や「今後アプローチ方法を変えるべき層」も明確になります。
3. 営業・マーケ部門から現場の声を集める
数字だけでなく、実際に顧客対応をしている営業やマーケティング担当者の「現場感」も非常に重要です。
- どのようなセグメントで商談がスムーズに進んだか
- 逆に苦労したセグメントや、反応が薄い層の特徴
- お客様がよく口にする課題や、不満・要望
- 現場から見た“理想の顧客像”や“ターゲットになり得る新しい市場”
こうした現場のリアルな情報を定性データとして集めることで、数値データだけでは見えないインサイトを発見できます。
4. 仮説立案とセグメント仮説のリストアップ
データと現場の声をもとに、「どのような顧客セグメントなら自社が最も価値を提供できるか」を複数パターン仮説としてまとめます。
例えば、
- 「従業員300人以上、全国に拠点を持つ小売業」
- 「既に他社SaaSを導入済みで乗り換えを検討しているIT企業」
- 「テレワーク制度を強化中の中堅製造業」
この段階では、できるだけ幅広く仮説を立て、根拠となるデータや現場の感覚とセットで整理することが重要です。
5. セグメント仮説を比較・絞り込み
仮説リストができたら、「市場規模」「到達可能性」「競合状況」などの観点から優先順位をつけていきます。
ここで重要なのは、「理想的だが実際にはリスト化できない層」を除外することです。
たとえば「DXに課題を感じている企業」は定性的すぎるため、「DX関連のウェビナー参加歴がある企業」といった、具体的なリスト化ができる条件に言い換えることがポイントです。
現状分析とターゲット仮説の立案は、「データ」と「現場感覚」の両輪で進めることで、より確度の高いセグメント設定が実現します。
まずは自社で取り組みやすい部分から、分析とヒアリングを始めてみてください。
この地道なプロセスが、リード獲得や商談率アップへの最短ルートとなるでしょう。
4-2. セグメント候補の洗い出しと優先順位付け
次に、「どのセグメントを優先してアプローチすべきか」を決めます。
その際は、6Rなどのフレームワークを活用し、「規模」「成長性」「競合状況」「優先順位」「到達可能性」「測定可能性」など複数の観点から総合評価しましょう。
| 評価項目 | 例 |
|---|---|
| Realistic Scale(市場規模) | 十分な売上・利益が見込めるか |
| Rate of Growth(成長性) | 市場の拡大傾向 |
| Rival(競合状況) | 競合の多寡・強さ |
| Rank(優先順位) | 顧客の課題解決の優先度 |
| Reach(到達可能性) | 具体的なリスト化が可能か |
| Response(測定可能性) | 成果が定量的に測れるか |
4-3. ペルソナ・カスタマージャーニー設計との連携
BtoBセグメンテーションで導き出した「ターゲットセグメント」を、より具体的かつ現場の営業・マーケティング活動に落とし込むためには、ペルソナ設計とカスタマージャーニーマップの作成が欠かせません。
ペルソナとは、特定のセグメントを代表する“理想的な顧客像”を、実在しそうな一人の人物にまで具体化したものです。
たとえば、IT業界向けクラウドサービスの場合、「首都圏の中堅SIerでシステム導入を担当する40代課長、現場効率化とセキュリティ強化を課題に感じている」など、氏名・年齢・役職・抱える悩み・業務上のミッション・情報収集手段・最終決裁権の有無まで詳細に設定します。
ペルソナ設計のポイント:
- 企業属性(業種・規模・地域)
- 所属部門・役職・職務内容
- 日々の業務課題・優先順位
- どこで情報収集をしているか(例:Web検索/業界イベント/同業者の口コミ など)
- 導入判断に影響を与える要因(価格・社内稟議・同業の導入実績 など)
ペルソナは1つのセグメントにつき1人とは限らず、現場担当・決裁者・経営層など複数設計すると効果的です。
次に、そのペルソナが課題認識から情報収集、比較検討、導入判断、社内提案、最終決裁まで“どんな行動を取り、どこで何を感じているか”を時系列で整理するのがカスタマージャーニーマップです。
カスタマージャーニーマップ作成のステップ:
- ペルソナごとに「課題発生→情報収集→比較検討→社内稟議→導入決定」の流れを整理する
- 各段階での思考・感情・行動・利用チャネル(Web/セミナー/展示会など)を時系列で可視化する
- 「どこでどんな情報が欲しいのか」「どんな不安や障壁があるのか」を具体的に明らかにする
- ジャーニーの各フェーズで自社が提供すべきコンテンツやサポート、アプローチ手段を設計する
これにより、「見込み顧客が本当に求めている情報や提案」を最適なタイミングで届ける設計が可能となり、無駄な営業活動や機会損失を大きく減らせます。
4-4. MAツールやCRMを使ったセグメント管理・自動化
近年のBtoBマーケティングでは、MA(マーケティングオートメーション)やCRM(顧客管理)ツールの活用が当たり前になりつつあります。
これらのツールを使いこなすことで、セグメントごとの顧客管理・施策運用が効率化・自動化できます。
MAツール・CRMの主な活用ポイント:
- 顧客の属性(企業規模、業種、導入済みシステムなど)と、Web行動(資料ダウンロード・セミナー参加・メール開封状況など)を一元管理
- あらかじめ設定した条件でリードを自動セグメント化(例:「IT企業×従業員300人以上×価格ページ2回閲覧」など)
- スコアリング機能で、購買意欲や確度の高いリードを自動で抽出
- セグメントごとに最適化されたメールやコンテンツを自動配信し、リードナーチャリングを省力化
- 営業担当者にホットリード通知、CRM連携によるスムーズなパスアップ
これにより、「今、本当に必要としている企業」に最適なタイミング・チャネル・コンテンツでアプローチでき、リード獲得から商談化までの歩留まりを飛躍的に向上させることが可能です。
5. BtoBセグメンテーションとリード獲得・商談率向上の関係
「勝てるセグメント」を見極めた後は、そのセグメントに対して最適なマーケティング・営業施策を設計し、確実に成果につなげる段階です。
まず、セグメントごとに「誰に・何を・どのように届けるべきか」を明確化し、コンテンツやアプローチ方法を設計します。たとえば、情報収集段階の企業には「課題整理に役立つホワイトペーパー」や「トレンド解説のセミナー案内」を、導入を検討している層には「導入効果シミュレーション」や「比較検討資料」など、ニーズに合わせた情報提供が効果的です。
さらに、営業部門とマーケティング部門がターゲット・KPI・情報共有の仕組みを共通化することで、リードの質と商談化率を同時に高めることができます。
近年は、アカウントベースドマーケティング(ABM)など特定企業に特化した戦略的アプローチも普及し、重要顧客には営業とマーケが一体となったカスタマイズ施策を実施するのが主流です。
BtoBセグメンテーションを軸にした取り組みは、「数を追う」営業活動から「質にこだわる」戦略的営業へと進化させ、結果的にリード獲得数の増加と商談率の大幅アップを実現できます。
5-1. セグメントごとのマーケティング施策設計
BtoBセグメンテーションを活用したマーケティングでは、ターゲットごとに施策やコンテンツを“最適化”することが成果の分かれ目となります。
各セグメントのニーズや行動に応じて、LP(ランディングページ)、ホワイトペーパー、セミナー等のコンテンツを最適化しましょう。
例えば:
情報収集段階:「業界トレンド解説」や「課題の可視化ができるチェックシート」など、まず“気づき”を促すコンテンツが有効です。
比較検討段階:「機能比較表」「第三者の導入事例」など、検討材料になる詳細な資料やFAQコンテンツが響きます。
導入直前:「ROIシミュレーション」「コストダウン事例」「無料トライアル」など、“一歩踏み出す後押し”となる施策が効果的です。
ターゲットの検討段階や役職ごと(現場担当者/決裁者/経営層など)に、「何を・どのタイミングで・どう伝えるか」を設計することで、商談率が大きく向上します。
5-2. 営業活動との連携・ABM(アカウントベースドマーケティング)
商談率・受注率を最大化するには、営業とマーケティングの緊密な連携が不可欠です。
特に、売上インパクトが大きいLTV(顧客生涯価値)の高い企業や、業界で影響力を持つターゲット企業に対しては、「アカウントベースドマーケティング(ABM)」が効果を発揮します。
ABMでは、営業・マーケが一体となり、特定企業ごとの課題や担当者に合わせて、施策やコンテンツを“パーソナライズ”して提供します。
- ターゲットとなる“狙うべき企業リスト”を明確化(業種・規模・キーパーソンまで特定)
- その企業ごとに「キーパーソンの課題」「導入の障壁」「情報収集チャネル」などを調査
- 提案書・ホワイトペーパー・セミナーなども、その企業専用にカスタマイズして作成
- 営業とマーケが一体でアプローチ内容を設計し、反応や進捗を常に共有・改善
このような「一点集中型」の取り組みは、リソース効率も高く、競合との差別化・高単価案件獲得にも直結します。
5-3. 成果指標と効果測定のポイント
BtoBセグメンテーションの実践効果を最大化するには、「正しいKPI設定」と「継続的な効果測定」が必須です。
セグメントごとにKPI(成果指標)を設定し、PDCAサイクルで継続的な改善を行うことが重要です。
| セグメント | 主なKPI例 |
|---|---|
| セグメントA(大手IT企業) | 資料DL数/商談化率/LTV |
| セグメントB(中堅製造業) | セミナー参加率/成約率 |
| セグメントC(既存顧客のアップセル) | アップセル率/契約更新率 |
PDCAの具体例:
Plan: 目標値と施策(例:セミナー参加率10%UP)
Do: 施策の実行(例:特定セグメント向け招待メール配信)
Check: 効果測定(例:参加率や反応率のデータ集計)
Action: 改善案の実施(例:メール文面改善・ターゲットの見直し)
数字を「セグメントごと」に切り分けて管理・分析することで、“どのターゲットにどの施策が一番効果的か”が明確になり、効率的なリソース配分が可能になります。
6. 失敗しやすいBtoBセグメンテーションの注意点と解決策
6-1. ありがちな失敗例
BtoBセグメンテーションは成果に直結する一方、よくある失敗パターンも多いです。
- 自社都合の分類(「大企業だから狙う」など顧客ニーズ無視)
- 市場規模が小さすぎて、リソース投入に見合った成果が得られない
- 到達可能性(リスト化や実際のアプローチ)が曖昧で施策が形骸化
- データや事例に基づかず、思い込みだけでターゲットを決定
6-2. 解決策・リカバリー方法
失敗しないためには、「顧客の課題起点で再定義」する視点が大切です。
- 常に顧客の声やデータを元に分類軸を見直す
- 社外データや顧客ヒアリングを積極的に活用する
- 定期的にチームでセグメントの見直し・レビューを実施する
- 外部の専門家やコンサルティングの意見も取り入れる
「最初に立てたセグメントは変わる前提」で、柔軟にアップデートする体制が成果を生みます。
7. データ活用・AI/MAを使ったセグメンテーションの最新動向
7-1. データドリブンセグメンテーションの進め方
近年では、CRM(顧客管理システム)やSFA(営業支援ツール)、外部データベースを統合活用し、データに基づいて“本当に成果が出やすい企業”を抽出する動きが拡大しています。
- 過去の受注・失注データ、Web行動履歴、アンケート結果を分析
- 顧客属性×行動データの掛け合わせで、見込み度の高いリードを発見
- 定量的なデータにより、「感覚」ではなく「根拠あるターゲティング」が可能
7-2. AI/MAツールによる自動分類・スコアリング
AIによるリードスコアリングや、インテントデータ活用(Web上の行動や関心データの分析)など、ツールを活用した“自動・高度”なセグメンテーションが一般化しつつあります。
- MA(マーケティングオートメーション)が自動で見込み顧客をセグメント化
- AIが過去データから「受注確度の高い特徴」を学習し、優先アプローチ先を提案
- リアルタイムで変化する顧客行動に即応した、動的セグメントも実現
「人手でできない精度・スピード」でターゲティングし、成果に直結させるのが最新潮流です。
8. 成功事例・インタビューから学ぶBtoBセグメンテーションのコツ
たとえばパナソニック「レッツノート」は、営業担当者向けというニッチなセグメントに特化したことで、競争の激しい市場で独自のポジションを築きました。
また、SaaSやIT業界でも、「既存顧客データを徹底的に分析し、新たなセグメントを発見したことでV字回復を果たした」など、成功の裏には必ず“データドリブンな意思決定”があります。
- 定期的にデータを見直し、セグメントを進化させている企業が成果を上げている
- 小さな仮説検証からスタートし、失敗も次の改善に活かしている
「既存顧客の声」「過去のデータ」「新しい気づき」を掛け合わせることが成功のカギです。
9. BtoBセグメンテーションの今後の展望・トレンド
今後もBtoBセグメンテーションは、「市場のさらなる細分化」「顧客ごとの個別最適化」へと進化し続けます。
AI・インテントデータ・ゼロパーティデータ(自社に直接提供される顧客の意向データ)の活用がますます重要になり、“1社ごと”に合わせたハイパーパーソナライゼーションが主流となっていくでしょう。
業界や競合環境が変化する中で、「今、この瞬間に最も成果を上げられるターゲット」を動的に見つけ出す力が、BtoBマーケティングの成否を分けます。 今から始めることが、将来の競争優位につながります。
10. よくある質問(FAQ)
セグメント数はどう決めれば良い?
セグメント数の基本は「マーケ・営業施策を実行できる最小限かつ十分な単位」です。過剰な分割は施策疲弊に、過少な分類はパーソナライズ精度の低下を招きます。
最初は3〜5分類からスタートし、リード数・CV率・営業対応状況などのKPIを見ながら四半期ごとのセグメントリフレッシュを行うのが実務的です。
営業・マーケ部門の連携のポイントは?
最も重要なのはセグメント単位で共通の「ペルソナ」と「目標指標(KPI)」を定義することです。マーケ部門が獲得したリードが、営業から「質が悪い」と言われないよう、
フォーム設計・リードスコア設計・営業進捗共有までを1枚の管理表に落とし込むと、属人化せずに連携が定着します。
自社だけでやるべき?外部に委託すべき?
データ整備・CRM設計・シナリオ策定までは、フレームが得意な外部パートナー(BtoB専門のマーケ会社)に設計支援を依頼し、運用フェーズは徐々に内製化がおすすめです。
特に業界経験のある制作会社や、ポジショニングメディアなどセグメント特化型メディアを運営している企業と組むと、セグメント戦略が加速します。
情報収集はどうすれば?
有効なのは3階層のデータ設計です:
- ①顧客属性:企業規模・業種・導入製品など(CRM/SFAより)
- ②行動データ:開封率・クリック・資料DL・セミナー参加など(MA/GA4より)
- ③主観情報:営業ヒアリング・カスタマーインタビュー・FAQ集約
「データで分かること」と「言語化しないと伝わらないこと」のハイブリッド設計が、良質なセグメンテーションを支えます。
11. BtoBのセグメンテーションまとめ
BtoBビジネスにおいてはセグメンテーションは成功する市場を見極める大事なポイントです。
セグメンテーションを考える上では、フレームワークを使用して整理することがおすすめです。ぜひ下記の資料をダウンロードして自社ビジネスのセグメンテーションを考案にお役立てください。