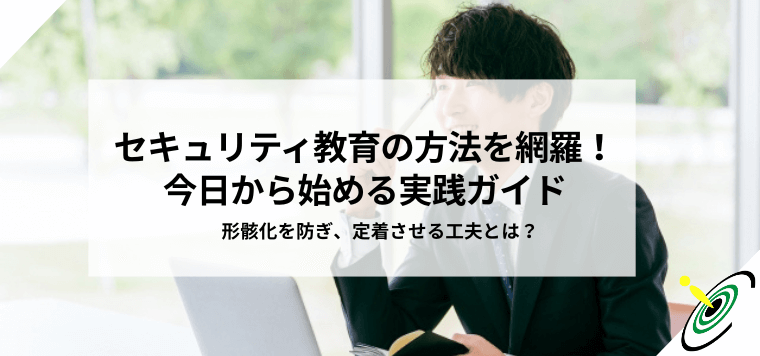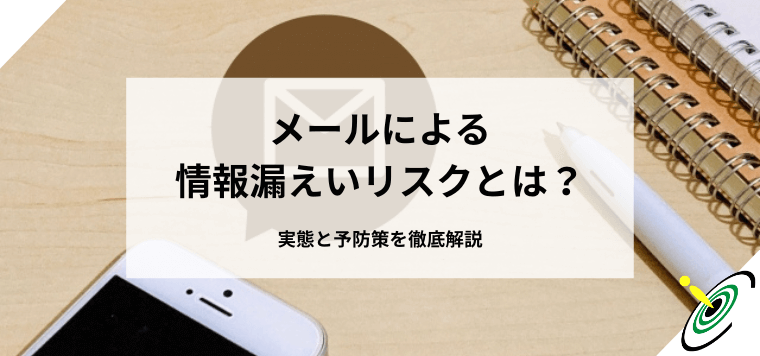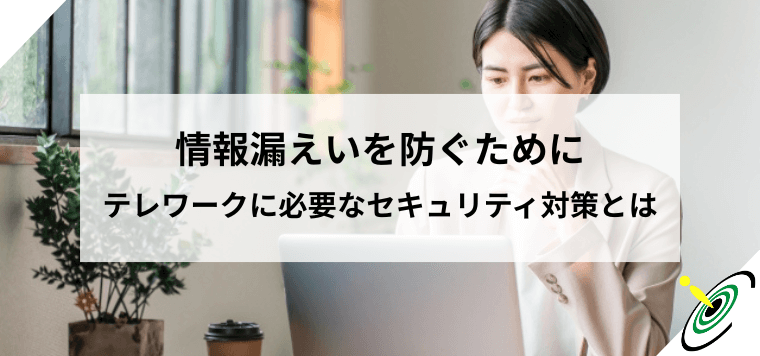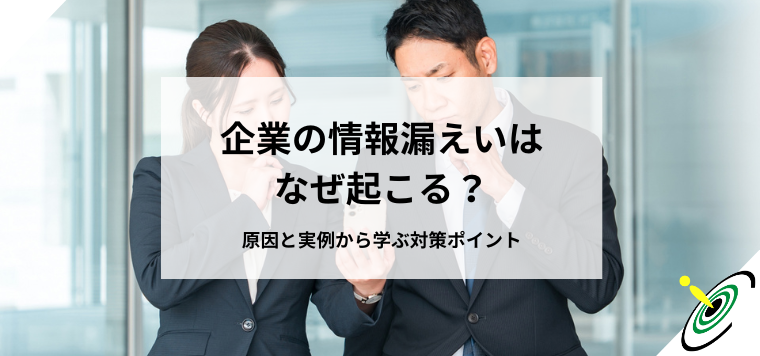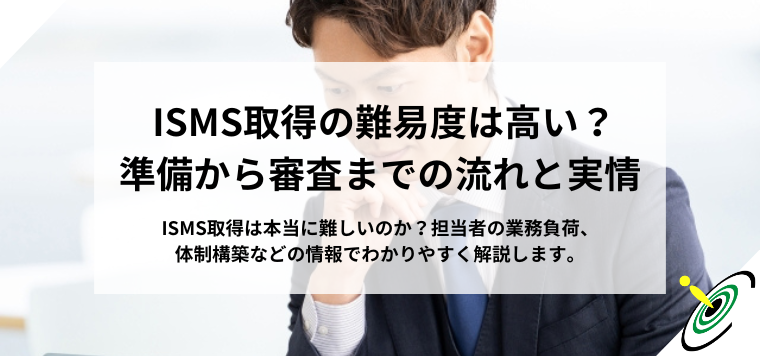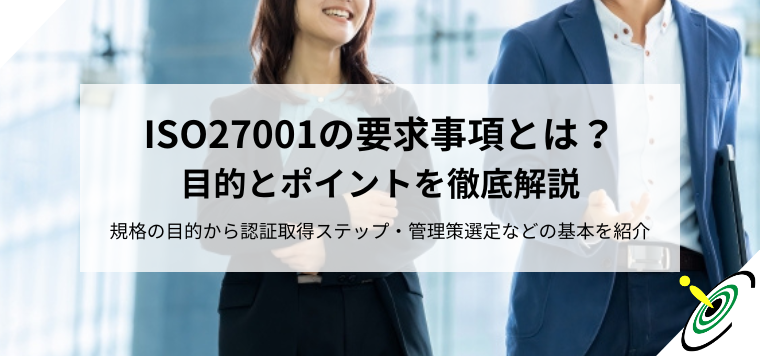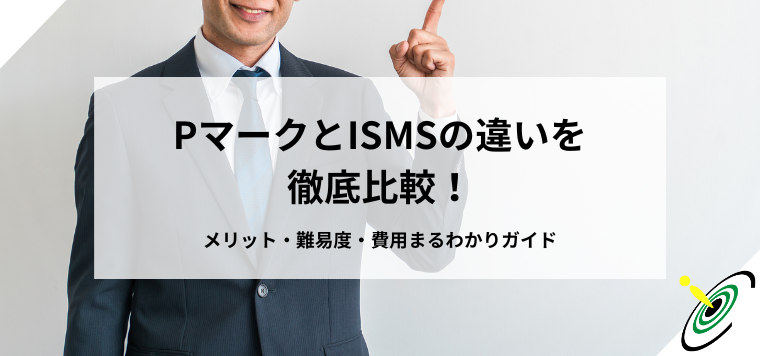ストレスチェックは「義務対応」で終わらせず、受検率・集団分析の質・事後フォローまで含めて選ぶほど成果が変わります。
この記事では、コスト重視の実施効率型、医師面談やコンサルまで備えた対応フォロー型、健診や勤怠と統合できる健康経営型など、様々な種類の17サービスを徹底比較。価格・機能・運用負担・多言語対応・導入事例や口コミまで整理しました。
法改正動向も踏まえ、初めての企業も乗り換え検討の企業もいま選ぶべき一社が見つかるはずです。この記事で紹介されているサービスは全て法制度に準拠しています。
紹介している掲載企業のうち、一部の資料は下記よりダウンロードが可能です。比較検討の参考にご活用ください。
ストレスチェックサービスの一覧表
ここでは、ストレスチェックサービスについてご紹介していきます。それぞれのサービスが持つ強みや特徴をご紹介していきますので、自社のニーズに合ったサービス選びにお役立てください。
| 会社名 | サービスの特徴 | 料金 | こんな企業におすすめ | 対応言語 |
|---|---|---|---|---|
|
個人と組織の健康をチェック!全国・業界比較で自社の状況を把握できる
|
要問い合わせ
|
ストレスチェックをきっかけに
職場改善まで進めたい |
日本語・英語
|
|
|
メンタル不調のケアから人材育成まで!1人110円※で充実のストレスチェックサービス
|
110円 / 1人
※別途基本料がかかります。 |
コスト最優先の小規模事業者
|
日本語
|
|
|
総合心理教育研究所 |
30万件以上の臨床データを基に開発!アフターケアまでワンストップで提供 |
要問い合わせ
|
離職率の高さや人材流出に課題を抱えている
|
日本語
|
|
HoPEサーベイ |
離職リスク×生産性低下を未然に防ぎ、組織のストレス課題を丸ごと解決 |
初期費用:~462,000円
月額:~308円 / 1人あたり |
人材定着・生産性向上狙いの企業
|
日本語
|
|
ストレスチェッカー(HRデータラボ) |
初期費用0円。無料で利用できるプランも用意 |
初期費用:0円
無料プラン:0円 WEB代行プラン:275円 |
まず費用をかけず試したい
|
16か国語対応
主要欧米・アジア言語 |
|
LLax forest |
ヘルスケアの専門職が制作したオンラインコンテンツを100種類以上用意 |
2,640円×利用人数
|
離職率低下や多角的分析を重視
|
日本語
|
|
COCOMUストレスチェックサービス |
企業にフィットしたサービスを提供する「セミーオーダー対応型」である点が特徴 |
基本利用料:22,000円
用紙版:495円~ / 人 Web版:275円~ / 人 |
自社の運用に合わせて柔軟に対応してほしい
|
紙は7言語対応
(英・中・ポルトガル語等) |
|
WELSA |
健康セミナーやフィットネスアプリといったコンテンツを通じた健康増進施策も提案 |
要問い合わせ
|
健康経営を推進したい
|
日本語
|
|
HM-neo |
健診に関連する管理業務が一元管理できるシステム |
要問い合わせ
|
自社で産業保健体制を整える大企業向け
|
日本語
|
|
ドクタートラスト |
ストレスチェックの実施料金のみでスタッフによる事務サポートや集団分析も提供 |
要問い合わせ
|
産業医サービスと併用したい企業向け日本語
|
日本語
|
|
リモート産業保健 |
産業医+産業看護職の2名体制で行われる完全リモートストレスチェックサービス |
要問い合わせ
|
専任産業医が不在の中小企業向け
|
日本語
|
|
Carely |
使いやすさにこだわった設計のシステム。保健師や臨床心理士によるサポートも可能 |
要問い合わせ
|
IT活用で健康管理を効率化したい
|
日本語
|
|
M-Check+ |
ストレス耐性に関する独自項目の追加によりより深い気づきを得られる仕組み |
初期費用:2万円
年間システム利用料:12万円 チェック実施料(Web):500円 |
高ストレス者が多く発生して困っているが
社内に専門知識がない |
日本語
|
|
ORIZIN |
14ヶ国語以上の外国語受検も可能 |
年間費用:880円~
|
外国人労働者が多数いる製造業・建設業
|
15言語以上対応
(東アジア・東南アジア含む) |
|
中災防 |
個人リポート・グループ集計リポートの2パターンの報告書を提出 |
297円~ / 人
|
信頼性重視で手堅く実施したい
|
日本語
|
|
同友会 |
ストレスチェックに加え運用体制や実施方法についてのアドバイスも提供 |
660円〜880円 / 件
|
健診もストレスチェックもまとめて任せたい
|
日本語
|
|
ソシキスイッチ ストレスチェック |
東京都や仙台市、宇治市など自治体の導入実績も豊富。外国語14言語をカバー |
6,800円~
※税不明 |
担当者の負荷を減らしたい
|
14言語対応
(主要欧米・アジア言語) |
ストレスチェックサービスとは?

「ストレスチェックサービス」は、従業員に対するストレスチェックを実施し、さらにチェックを行った後の対策まで行うサービスを指しています。ストレスに関する質問に対し従業員が回答し、集計・分析することによって、労働者が抱えているストレスについて把握できます。
ストレスチェックは、従業員の精神面における不調を未然に防ぐためにも大切な取り組みです。取り組みを行う場合には、産業医との連携や判定基準選定、高ストレス者への対応といったように、チェック以外にも行う業務が多くありますが、サービスの活用によってスムーズにストレスチェックを行えます。
50人未満の事業場も対象に!義務化に向けて準備を
2025年5月に可決・公布された労働安全衛生法の改正により、これまで努力義務とされていた従業員50人未満の事業場にも、ストレスチェックの実施が義務化されることになりました。
施行日は「公布日から3年以内に政令で定める日」とされており、遅くとも2028年5月までにはすべての事業場において義務化される予定です。
ただし、政令によっては前倒しされる可能性もあるため、厚生労働省などからの発表を随時確認し、早めに準備を始めることが大切です。
精神障害の労災認定、初の1,000件超え
2024年度(令和6年度)の「精神障害」に関する労災〈支給決定件数〉は1,055件に達し、初めて1,000件を超えました。請求件数も3,780件といずれも過去最多を更新しています。
支給決定件数に寄与した主な要因は、「上司等からの身体的・精神的攻撃(パワハラ)」が224件(全体の約21.2%)で最多で、長時間労働との関連も示唆されています。(※1)
要因として挙がるパワハラ対策には、ハラスメント対策サービスやハラスメントeラーニングが有効です。
※1参照元:厚生労働省「過労死等の労災補償状況」(https://www.mhlw.go.jp/stf/newpage_59039.html)企業も従業員も得をする!ストレスチェック導入のメリットとは

従業員自身が自分のストレスに気づける第一歩に
ストレスは知らないうちに溜め込みやすいものですが、なかなか自分では気づきにくい場合も。ストレスチェックサービスの活用により、従業員自身が自分の心身状態を把握できるといった点が大きなメリットといえます。ストレスに早めに気づき、対処できるようになれば健康を守ることにもつなげられます。
労働環境改善につなげられる
ストレスチェックサービスを利用すると、その結果の集計・分析が可能となります。年代や職種、部署別といった形で集計が行われるため、この結果をもとにして負荷の高さやストレスの原因などを把握して労働環境の改善につなげられます。原因の把握によって、より良い対応につなげられます。
企業側の負担を軽減できる
ストレスチェックにはさまざまな業務が発生するため、サービス利用により企業側の負担軽減にもつなげられます。
従業員との面談や高ストレス者への対応など、企業が独自に行った場合には大きな負担となると予想されますが、サービスの活用によって関連業務をお任せできます。このことにより企業への負担が軽減されて他の業務に注力できるため、業務の効率化にもつなげられます。
従業員の率直な回答を得やすい
自社内でストレスチェックを行った場合には、従業員の率直な回答が得にくい可能性もあります。これは、上司にチェック結果を共有されることを考えてしまい正直に回答できないといったケースがあるためです。
しかし、ストレスチェックサービスを導入した場合には外部業者がチェックを実施します。この場合の担当者には守秘義務があり、人事権をもつ者に結果が開示されることはないといった点から率直な回答を得やすくなるといったメリットもあります。
失敗しないサービス選び!目的別にチェックすべき3タイプ
ストレスチェックサービスは一見どれも同じように見えますが、実は目的や活用の仕方によって適したサービスが異なります。自社が何を重視したいのかを明確にすることで、最適なサービスを選ぶことができます。
ここでは、主なサービスを目的別に3つのタイプに分類し、それぞれの特徴やおすすめの企業像を紹介します。
あなたの企業に合うのはどれ?3つのタイプ早見表
| タイプ | 主な目的 | 特徴 | おすすめ企業 |
|---|---|---|---|
| 実施効率化 (コンプライアンス重視型) |
法令遵守とコスト削減 | Webシステムで手間を削減 簡単な集計機能 |
初めて義務化の対象になる中小企業 |
| 対応フォロー (リスク対策・事後措置重視型) |
高ストレス者への対応と職場改善 | 医師面談やeラーニング、コンサル付き | メンタル不調の休職・離職対策を重視する企業 |
| 健康管理一元化 (健康経営推進型) |
戦略的な人事施策・健康経営 | 勤怠・健診データとの統合管理 | 従業員の健康を経営資源と考える大企業 |
タイプ1:実施効率化(コンプライアンス重視型)
このタイプは、ストレスチェックを低コストで効率的に実施したい企業に適しています。Web上で受検を完結でき、担当者の負担も最小限で済みます。- メール通知や集計が自動で行える
- 基本的な集団分析レポートが含まれている
- 料金が安価または無料プランがある
まずは法令をクリアすることを優先したい企業におすすめのスタートラインです。
タイプ2:対応フォロー(リスク対策・事後措置重視型)
メンタルヘルス対策を実質的に機能させたい企業には、対応フォロー型が適しています。高ストレス者への医師面談の手配や、職場環境改善に関するコンサルティングまでサポートが受けられます。
- 専門家による分析・解説付きのレポート
- eラーニングによる教育プログラム
- 面談代行や相談窓口などのオプションが充実
単なる制度運用で終わらせず、改善につなげたい企業に最適です。
研修は、実務に落とし込みやすいハラスメントのeラーニング研修を組み合わせると、受講・管理の負担を抑えられます。
タイプ3:健康管理一元化(健康経営推進型)
このタイプは、ストレスチェックを経営戦略の一環として活用したい企業に向いています。健診データや勤怠情報など、他の健康データと統合して分析できます。
こうしたデータ連携には健康管理システムを活用する方法も有効です。
- 人事・労務システムと連携可能
- 生産性や組織状態との相関を可視化
- 高リスク者の早期発見と予防にも活用可能
健康経営を推進したい企業にとって、将来を見据えた投資となるでしょう。
ストレスチェックサービスでできること
外部サービスを活用すると、実務の手間を抑えつつ制度を効果的に運用できます。受検から結果活用、事後フォローまでを一気通貫で支援する仕組みが用意されています。社内の負担を小さくしながら、データに基づく改善と高ストレス者のケアを両立しやすくなります。
実務の効率化と中立性の担保
調査票の準備、対象者への案内配信、Web・スマホでの受検、結果の自動集計までを一連で自動化できます。未受検者には自動リマインドが送られるため、担当者が個別に追いかける場面は少なくなります。紙とWebの併用にも対応でき、従業員の環境に合わせた受検方法を選べます。
外部機関が運用することで、従業員は評価への影響を過度に心配せずに回答しやすくなります。法律上、個人結果は本人の同意なく事業者が閲覧できません。第三者による実施は、この点での信頼感につながり、より正直な回答を引き出しやすいといえます。結果として、集まるデータの質が安定し、後続の分析や対策に活かしやすくなります。
集団分析で組織課題を可視化
部署・職種・役職・年齢層などの属性単位でストレス状況を集計し、どこにどの要因があるのかを把握できます。全国平均や同業他社とのベンチマーク機能、見やすいレポートや「仕事のストレス判定図」を提供するサービスもあり、経営層や衛生委員会が優先順位を判断しやすくなります。
たとえば、ある部署では「仕事の量的負担」が強く、別の部署では「上司の支援」が不足している、といった違いがデータで明らかになります。勘や経験に頼らず、客観的なエビデンスをもとに施策を設計できる点が強みです。施策の後は同じ指標で再測定しやすく、改善の前後比較にも使えます。
高ストレス者への適切なフォロー
高ストレス者が申し出た場合、企業は医師による面接指導の機会を設ける必要があります。特に従業員50人未満で産業医選任の義務がない事業場では、実施体制を整えること自体が課題になりがちです。サービス側で、結果通知→本人の申し出→面接指導の申込み→医師との面談設定までをスムーズに連携できる仕組みを備えていると、対応が途切れにくくなります。
面接指導体制の整備が難しい場合は、外部の産業医紹介サービスを活用して、産業保健体制を補完する方法もあります。
継続的な支援にはメンタルヘルスケアサービスと組み合わせることで効果が高まります。高ストレス者を特定して終わらず、必要な専門的ケアへ確実に橋渡しできるかどうかは、サービス選定で見逃せないポイントです。
ストレスチェックサービスでよくある質問

Q1. ストレスチェックサービスの費用相場は?
ストレスチェックサービスの費用相場は、こちらの記事で紹介しているサービスを参考にすると「1人あたり年額300〜2,500円程度」といったサービスが多いようです。
ただし、サービス内容によってはそれ以上の費用が必要になる場合や初期費用が必要な場合などもありますので、自社のニーズと予算に応じたストレスチェックサービスを選ぶことがおすすめです。
Q2. ストレスチェックサービスを選ぶ際の注意点は?
ストレスチェックサービスを選択する場合には、まずどのような点を重視するのかを考える必要があります。
例えば「ストレスチェック受検率を上げたい」といった場合にはスマホやPCから受検できるタイプのサービスがおすすめですし、「チェックを実施した後のアフターフォローを重視したい」場合には、面談調整機能や分析機能が充実したタイプのサービスを選ぶとしっかりとフォローが行えるようになります。
また「業務効率を重視したい」というニーズがある場合には、データ管理や報告書の作成などを含め、クラウドでデータを一元管理できるサービスがおすすめです。
一方で、自社だけでの対応が難しい場合はストレスチェック代行業者に委託する方法も検討してみてください。
ストレスチェックサービスのまとめ
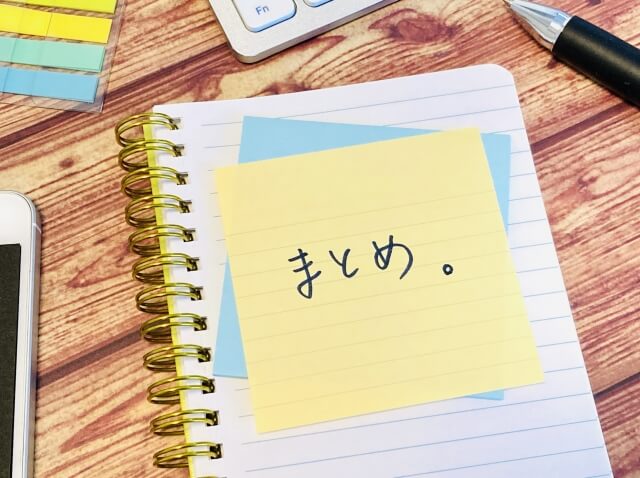
ストレスチェックサービスを導入したい企業向けに、さまざまなサービスを紹介してきました。それぞれのサービスにより内容が異なってくるため、自社ではどのような点を重視したいのかといった点をまず明らかにしてからどのストレスチェックサービスを導入するかを検討することがポイントです。
さらに、ストレスチェックと併せて従業員のストレス耐性を高める取り組みも検討してみてください。レジリエンス研修のような能力開発プログラムを組み合わせることで、予防的なメンタルヘルス対策として、より広い効果が期待できます。
ストレスチェックサービスの導入は、企業側には職場環境改善や生産性向上、従業員側には自己理解の促進やメンタルヘルス意識の向上といったメリットをもたらします。これからサービスの導入をお考えの企業様は、ぜひ本記事でご紹介した内容を参考に、最適なサービス選びにお役立てください。
- 免責事項
- 本記事は、2023年8月時点の情報をもとに作成しています。掲載各社の情報・事例をはじめコンテンツ内容は、現時点で削除および変更されている可能性があります。あらかじめご了承ください。


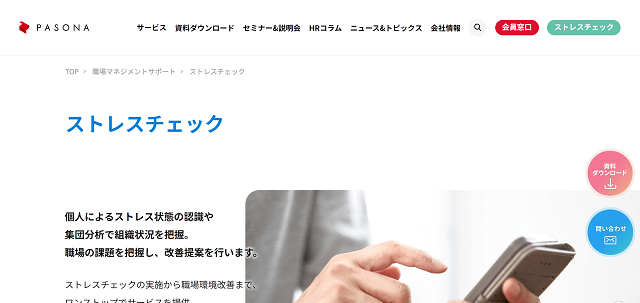 会社詳細を見る↓
会社詳細を見る↓
 会社詳細を見る↓
会社詳細を見る↓


.png)